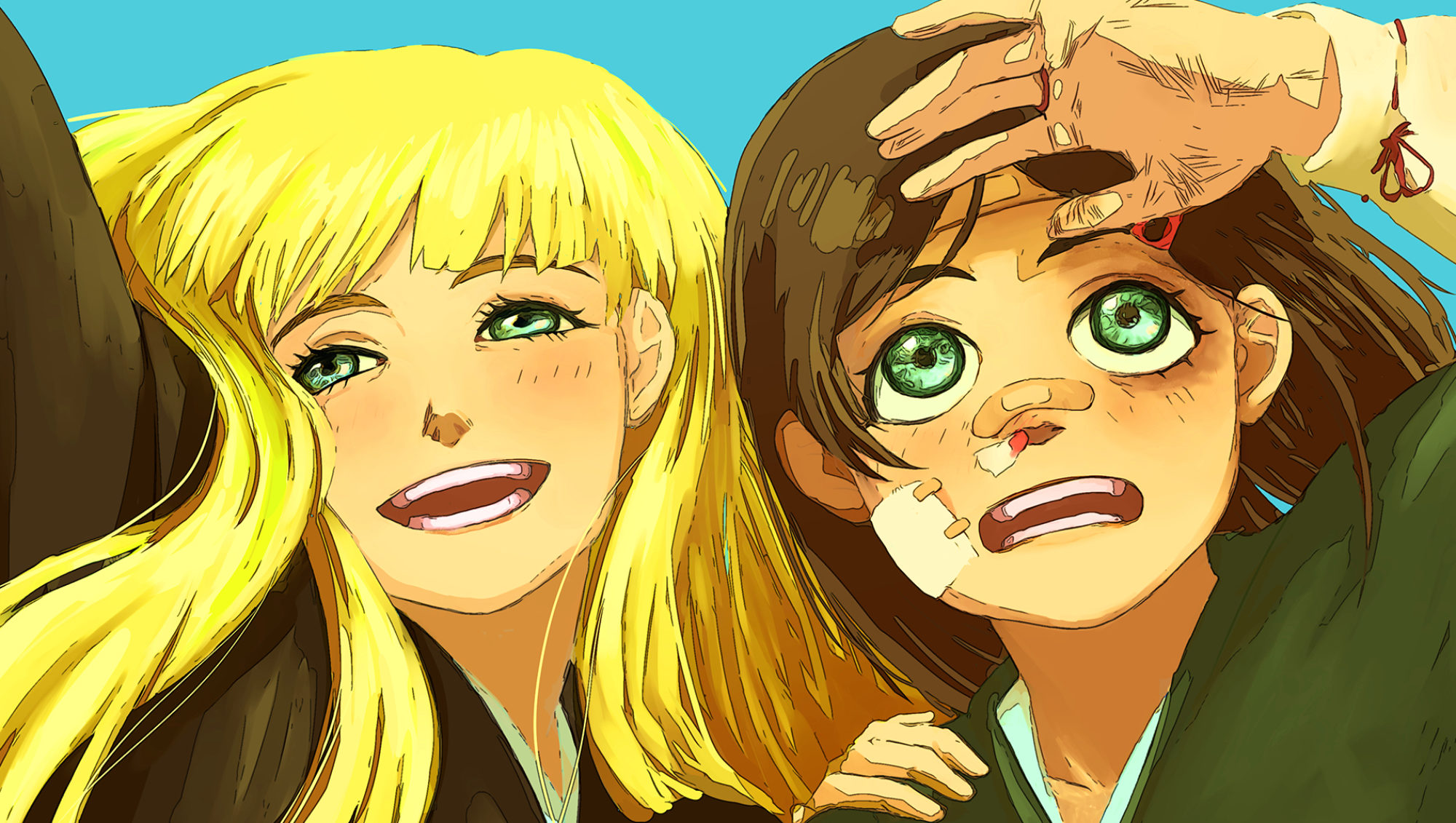進捗報告
ハルカにとって、ユキカゼにとっての愛宕とは何か。何が彼女達にとって〝見上げる〟ほどの愛宕だったのか。〝溺れる〟ほどの愛宕だったか。見下ろすことのできない国だったか。愛宕は客人(まれびと)としてやってきた彼女達に、どう触れていったのか。
今はそこを考えている。
みすずの国をリメイクするために、みすずの国を紐解いた。シナリオを読みつつネームを書き直し、10年前では定められてなかった設定や、10年の間に変わってしまった設定を加えたり引いたり。みすずの祖父の在所などが変わり、愛宕国境まわりも以前に比べ細かく設定がつめられた。
そうしてみすずの国をなおしながら思うのは、みすずの国で描かれた愛宕ではハルカやユキカゼを溺れさせることは出来ないということ。
16歳の少女が新境地として脚を踏み出す愛宕は、あれで良かった。目に飛び込んでくるもの全てが新しく、迫力をもっている。彼女が見上げた愛宕は、十分に大きなものだったと思う。
しかしハルカやユキカゼはみすずとは違う。住み慣れた家を初めて離れたティーンエイジャーの少女ではない。化けとして長く居着く土地をもてず、放浪を続けた人々。その彼女たちが旅の最後に辿り着いた土地である。
そうして彼女たちは、辿り着いた愛宕で数十年を過ごした。大正の終わりから、戦後の昭和まで愛宕で暮らし、ハルカは為政者として愛宕を導きもした。
そんな彼女達が見上げる愛宕とはなんなのか。国として、茫漠と彼女達に覆い被さる〝それ〟は何か。
彼女達が溺れる〝そこ〟の正体とは何か。歴史、風土、時、文化、あらゆるものが深々とした色彩を発し、その混色として見えてくる本当に暗き色。漆黒、玄妙の色彩。
彼女たちがついに溺れてしまうほどの深き何かとしての国。それを今、我輩は探している。
そういうものは必ずある。我輩の中では既に感じている。恐らくそれは「山岳」という土地に由来するはずだと睨んでいる。
「山岳」と「平地」に流れた時、速度の違いが、時代を生み、隣接する国を生んだ。お互いとの接触感を自らの輪郭とする国が生まれたのだと思う。
この〝国の感じ〟を織りなすものを掴めれば、ハルカとユキカゼが溺れる場所としての愛宕を表現できると思う。
ハルカの国が、最後、愛宕で閉じられるのは意味があるのだ。
その意味は、越冬編の明治より始まったこの物語を通底していなければならない。その意味がハルカやユキカゼの感情として、物語のなか鮮やかに現われてこなければならない。
全てが響きあうような物語とするため、国たるものを考え続けているところであります。
ちなみに。
先日、岡山の奥地にあるベンガラの里を訪ねてみたが、そこでも愛宕を見つけきることは出来なかった。
ハルカ、ユキカゼ。背の高い人々。彼女たちを埋没させるほどの世界をつくるのは、本当に難しいことでありまさ。
犬去りし日々
以下は飼い犬を見送ったオッサン(我輩)の個人記録なので、創作には関係ない。お暇な方のみ、飼い犬とその家族が織りなす家族模様として楽しんで頂ければと思う。
くるりん
彼の名前はくるりん。2009年、オヤジに連れられ我が家にやってきた。目がくりくりして可愛いと祖母によって名付けられた、ヨークシャー・テリア。
呼び辛いので皆は「くる」だとか「くるちゃん」だとか呼んだ。我輩は「くる坊」を縮めて「くるぼ」と呼んだ。一番にオヤジになつき、叔母にもよくなついたが、我輩にはたいして懐かなかった。
郵便配達員と二件隣の柴犬を憎み、オヤジに抱かれて嗜む夕食のつまみ食いをこよなく愛した犬だった。
彼の登場は我が家を震撼させたものだった。
我が家は当時家庭問題を抱えており、詳細は省くがゴチャゴチャしていた時期だったのだ。我輩も沖縄で仕事をしており、実家には不在。
そんな中、神経をすり減らしていた叔母は、仕事帰りに見知らぬ子犬が自分を出迎えたことに「ぷちん」と切れてしまい、涙をにじませ部屋に引き籠もったという。
くるぼは、オヤジが家族に何の相談もなく独断で迎えた犬だったのだ。
オヤジも家庭問題に擦り切れており、息子の我輩にむかって「家に帰りたくない」など思春期の若者のような相談を持ちかける始末で、相当まいっていたのだとは思う。
そんなオヤジの心境にどう入り込んだのか、そのヨークシャーテリアの子犬はある日突然、我が家にやってきたのだ。
我輩も遠方の沖縄にいて、叔母から「家に犬がおるんよ」と悲しく疲れ果てた声で告げられたのを覚えている。
どれだけ腹が立とうとも子犬を憎んでも詮無きこと、子犬は「くるりん」と名付けられ仕方なしに迎え入れられた。
ただ家族の腹立たしさは子犬に向けられない分オヤジに向けられ、オヤジはしばらく家の中で孤立無援、自分が連れてきた子犬以外に話相手もなかったそうだ。
子犬の方は複雑な家庭問題など知る由もなく、新しい家にて自分を可愛がる老いた男に懐いていった。
その後、家族のわだかまりも風化していき、問題は解決しないまでも色々なことが諦められ受け入れられていく過程で、人々の煩雑な人生や悩みなどどこ吹く風の儘放題だった子犬は他の家族からも愛されていった。
ただ我輩には懐かず、たまに実家に帰ると毎度初めてのような態度で吠えつくのだった。
いつのまにだったろうか。
今こうしてふり返ってみると、子犬だった頃の生意気な彼がありありと思い出される。ぬいぐるみのようだった子犬だったのに、いつのまに時は過ぎ去ったのだろうか。
それでも、いつのまにか時は流れ、彼を小さな「くるちゃん」のままではいさせなかった。
我輩が大阪から実家に戻ったのが、2017年、六年前のこと。
その頃には、以前の我が儘くるぼとは少し違っていた。二度の手術をうけ体力がおち、縦横無尽に駆け回っていた我が家でも、二階の階段をあがることが難しくなっていた。
我輩との散歩も歩調が合わなくなり、疲れるからだろう、嫌がるようになってしまった。
立ち止まる度に「あんた歳とったねえ」と話しかけ、体力を取り戻そうと長めの散歩にも連れ出してはみたが、結局、そこからかつての姿に戻ることなく、少しずつ老いていく道を辿った。
出来ないことも多くなり、眠ることも多くなった。
ここ一年ほどは、すっかり爺さんになってしまったなと家族でも話していたもの。
それでも我輩たちは、まだ彼との時間は残されていて、別れは先のことだと思っていた。
予感はしていたものの、まだ考えなくてもよいものだと、未来のこととして今からは切り離していた。分かってはいても、了解はしていなかった。
それこそ今年の初めなどには毎年叔母が募る「くるちゃん募金」に一万円を投じ、「これ使わんええように元気におれよ」と声をかけたものだったか。
ある日突然、彼の体調が崩れ始めた。
2月の中旬、餌を食べなくなり、寝込んだ。
寝込むのも寝ていると言うより、足腰が立たず倒れている有様でいつもとは様子が違う。
何度か点滴をうち、持ち直してはまた崩れてを繰り返す。かかりつけの獣医からは「もう歳なので」と完治が難しいことを告げられた。
元々、治療の難しいところに腫瘍のある子だったのだ。それが見つかってから五年が経っており、いよいよその腫瘍の影響が表出し始めたのかもしれないとのこと。摘出の難しい場所で諦めていたことだから、この度も打つ手は少なかった。
体調の浮き沈みを経ながら、彼は色々なものを失っていった。視力を失い歩いては壁にぶつかり、水を飲もうとしては水のないところで舌を動かした。
右後ろ足を引きずるようになって、歩く度に爪が擦れシャリシャリと鳴った。痛くないのかと問いかけると、彼はよく分からないよう顔で声のする方、我輩を見上げていた。
再び体調が大きく崩れた時には、もう駄目だろうという気配が家族の中で漂った。
一体、誰が最後を看取ることになるだろうか。オヤジに懐いているから、オヤジと一緒の時に迎えられたらよいのだけど。
我輩は願っていた。本心を言えば、恐れていた。
我輩だけが家に残る日中に急変したら、どうしようか。具体的な何かを恐れていたわけではなく、ただ我輩の目の前で彼の最後がやってきたらどうしようかと、その立ち会いに本能の部分で恐れ、出来ることなら我輩でなければ良いと願っていたのだ。
くるぼはオヤジの犬なのだ。オヤジに看取ってもらうのが、この子のためでもあろう。そう思い、我輩ではないことを祈った。
目が見えなくなっていく彼、歩き方を忘れていく彼、それでも我輩を見上げる彼。少しずつ小さくなって消えていくような彼を見つめ続けることに、我輩はもう疲れていて、その疲労感が未来のその日を恐怖していたのだと思う。
しかしどうしたことだったか。
そんな見送る気配とは裏腹に、彼は急に持ち直した。
目は見え辛そうにしながらも歩き回り、皆が気狂いのようになって買った缶詰もよく食べた。水もよく飲んだ。
これは峠を越したかもしれないと、皆喜んだものだった。目は見えず、脚も引きずったままだったけれど、それでも元気になってくれたのだと。
我輩と二人の時などには、すっかり元気な様子で外に出たがったから、連れて出してもやった。
2月の終わり。冬の明けようとする長閑な日のこと。ちょっと連れ出すつもりだったのが、思いの他よく歩いて、右足を引きずりながら懐かしそうにかつての散歩道を嗅ぎ回っていた。
あんまり歩くので心配になり「あんたまだ身体がもどらんので。元気になったらまたこようや」と帰宅をうながした。その帰り道に、何日ぶりかだろうか、大きなウンコをして我輩を喜ばせた。
オヤジに「こんな大きなのした」と話せば、オヤジも「だいぶ良くなった」と喜んでいたものだった。
その翌日はオヤジも休日で、久しぶりに元気な二人で過ごすこともできたようで。寝る前には歩きすぎて疲れたのか眠たげな目でオヤジに連れられ、寝室へ向かって行った。
我輩も彼の頭を撫でながら、元気になれよと見送ってやった。我輩もその時は、またくるぼは元気になってくれるものだと思っていた。
けれど、それが最後だったのだ。
翌日、昨日までの快調が嘘のように彼は体調を崩した。
立つことも出来ず、身体にも力が入らずに、ただ寝かされるままに倒れているしかなかった。
その日、家には我輩しかいなかった。
間の悪いことにかかりつけの動物病院も休み。今日だけは体調を崩さなければ良いがと願っていたが、彼はその日に、かつてないほど体調を崩した。
オヤジを見送るまでは、まだ元気があった。起き上がれないまでも首をおこし、丸まるとした目で仕事へ出かけていくオヤジを見送った。
出勤する叔母に撫でられた時、彼はいつもと違う鳴き方をした。呼び止めるようでもない。ただ疲れていながらも、叔母の言うことが分かると頷くように鳴いていた。叔母は「早く帰ってくるからね」と告げ、我輩に「頼むね」と伝え仕事に向かった。
そこから、体調は一気に崩れた。まるで二人を見送ったことで仕事を終えたかのように、力を失っていった。
我輩が見守る中、様態は悪化していく。苦し気な声とともに、舌は血の気が引き真っ白にかわった。我輩も一時期は介護職についていた身であれば、舌の色から血の気が失せる意味を知らないでもない。酸素がまわっていないのだ。だから苦しげに首をふり、呼吸をしようと試みる。しかしいくら喘げども楽にならない。彼の身体の中身が、機能していないのだ。
かかりつけ病院に電話をかけるがつながらず、他の病院を探してもどういうわけか休日だったり手術の予約でいっぱいだと断られる。大学病院にもかけあったが手術中で獣医の手があかないから連れて来てもらっても診てやれないと断れた。
一体、何件電話をかけたろうか。こんなにも断られることがあるのかと、世の中に背を迎えられているような孤独感を味わった。
我輩は祈るような思いで苦しむ彼を撫でた。明日になれば先生に診てもらおう。どうにか明日まで頑張れ。そう励ましてもみた。しかし「明日」などと言っている場合ではないことも分かってはいた。けれど出来る事がない。
ネットで調べてみても、今の彼にしてやれることは一つも載っていなかった。ただ「緊急で病院に向かえ」と我輩を脅すばかり。
様態は崩れ続ける。
呻くような苦しげな声が、だんだん悲鳴のように聞こえる。苦しそうに脹らむ肺、何かを求めては首をふる。首をふると苦しいのか、枯れた泣き声のような呻きが漏れた。
見ているのが恐かった。辛い悲しいという気持ちを飛び越えて、ひたすら恐い。胸が握りつぶされるようだった。それは我輩にとって単純に痛みで、味わいたくないとひたすら願う恐怖だった。
苦しむ彼を隣におきながら、また獣医で検索をかけ、片っ端から電話をした。どうしても診てもらえない。それでもどうにか14:00からなら診てやれるという獣医を遠方に見つける。
その時が12:00だったから、あと二時間。二時間、どうにか頑張ってくれ。頑張ったところで彼が助かるかは分からない。分からないがこの時間から逃げ出せる。
この二人の部屋で、苦しみ続ける彼を見つめ続けるのは我輩には無理だった。
聞いたこともない声をもらし、綿のように白くなっていく舌。彼の呼吸一つ、わずかな動き一つに脅されるような時間をさんざん過ごした。なんとか鳴き止んだと思い顔をあげると、まだ5分しか経っていない。時間がまったく進まない。唖然としていると、また彼が苦しみ始める。
耐えがたかった。
何も出来ないなら、いっそ目を逸らしたいと思った。ヘッドフォンをして耳もふさぎ、パソコンに向かいたい。こんな時間をあと一時間も続けたら、我輩の心が折れる。何かしない苦しさから逃れたくて、我輩はまた電話をかける作業へと戻った。
すると先ほどは留守電につながった一つの病院が電話口にでてくれる。様態を話すと、すぐに診てくれるとのこと。
ただもうその時から「難しいかもしれない」とは告げられていた。それでも我輩はすがった。とにかく、この部屋で彼の悲鳴を聞いているのは無理だ。
我輩は「俺の自己満足になったらごめん」と彼につげ、彼を抱いた。まったく力の入らないその身体は、抱き上げると手の中から零れおちそうだった。力の失われたその子をキャリーバックへ入れると、バックの形に合わせて首が曲がる。それでも自分の力では直せなかった。
我輩は彼を余計に苦しめている気もして、謝りながら車を走らせた。
病院についてすぐ、彼の意識がなくなり、心臓も止まった。
獣医に心臓マッサージをうける姿を窓越しに見ていると、足下がふらふらした。
強い薬をいれ、酸素室に入り、また心臓マッサージを繰り返して、なんとか一度は意識を取り戻し、心臓も打ち始める。
その間に検査が行われ、我輩のもとへと獣医が説明へと訪れた。
「やっぱり、もう難しいと思います」として始まった説明では、彼の肝機能が著しく低下しており、ほぼ循環機能が停止しているとのこと。そのために酸素がまわらず苦しんでいたとのこと。ただ心臓がとても強い子で、その心臓の強さ故に、他の機能が弱り切っても生きてこられたのだろうということ。
昨日まで歩いてたしご飯も食べていたことを告げると、獣医は驚いて「よっぽど心臓の強い子だったんだと思います」と教えてくれた。
ただその力強い心臓で牽引してきた身体も、とうとう限界を迎えてた。本当に最後まで頑張り通したために、ここまでの急変になったのだろうと獣医は教えてくれた。
「どうしますか」と聞かれた時、我輩は何を聞かれているやら分からなかった。何か選択肢があるのだろうか。
「もうこちらでしてあげられる事はないので、慣れ親しんだお家で迎えられた方がワンちゃんには良いかもしれません」
我輩はここに置いて、酸素室などに入れてもらえれば夕方まで持たないかと尋ねた。夕方になればオヤジが仕事から帰る。オヤジに会わせてやることが出来る。
そういう一つの目標のようなものを手に入れることで、我輩は何とかしようとしていた。獣医に「どうする」と問われている我輩自身を、何とかしようとしていたのだと思う。
「夕方まで持つこともあるかもしれませんが、もう今すぐだったとしてもおかしくない状態なので」
獣医は夕方まで持つとは言ってくれなかった。
その時、看護士が「先生」と施術室から飛び出してくる。獣医も「失礼します」と駆け戻っていった。
ややあって、看護士がやってくる。
「また今、意識がなくなりましたので心臓マッサージをします」
「強いお薬をいれて起こしますが、もしかしたらそのショックで」
看護士が告げられて、我輩はここまでだと悟った。思ったや感じたではない。ああここまでなんだと、分からされたのだ。
「もう大丈夫です」と告げると、看護士が獣医に伝え、彼の蘇生処置はそこで終わった。
「ワンちゃん、連れてきますので」と我輩は施術台に案内された。そこには持ってきた毛布がひいてあって、それはディズニーキャラクターのスティッチが描かれた毛布で、叔母が「耳と口が大きいのがくるちゃんと似てる」と集めたグッヅの一つだった。
スプーンだとか皿だとかトレーだとか。叔母は本当によくスティッチのグッズを買ったものだった。
獣医に抱かれ、彼が戻ってきた。目は開いたまま、まだ呼吸はしているようで微かな息も続いていた。
「頑張りましたよ。もう意識はありませんが、心臓はまだうっています。今、最後の呼吸が続いているところです」
と教えてくれる。どうぞ、と導かれるので胸に手をあてると、確かに彼がまだいた。
「本当に心臓が強い子で。今でもしっかり打ってます。止まるまで、しばらく時間があると思いますよ」
もう目は見えていないし、意識もないとのことだったが、我輩は彼の残る脈に手を添え、顔を見ては頭を撫でた。
今自分の手の中で去って行こうとしているその子を見つめながら「頑張ったね」と話しかけてみるのだけれど、声がつまる。涙も鼻水もでた。看護士がティッシュの箱を持ってきてくれた。
獣医には「お家に連れて帰られますか」と聞かれたが、「帰る途中になくなったら可愛そうな起気がして」と答えると、「ではここでどうぞ」と場所をかしてくれた。
「また何かあれば呼んでください」と獣医も看護士も去り、本来は休日だった病院であるから他の客もなく、我輩は彼と二人向き合うことができた。
心臓はしばらく脈をうち、獣医も何度か聴診器をあてに訪れては「ああ本当に心臓の強い子だ」と驚いていた。
やがてその鼓動も弱くなり、我輩の手では感じられなくなって、午後二時を過ぎた頃だったろうか、最後確認をしてもらった。獣医はしばらく聴診器をあてて「まだ、まだ」と頷いていたが、最後にはさぐるように聴診器を動かし、我輩に向かって頷いた。
「止まりました。眠られましたよ」
目は開けたままで、瞑らせてやることが出来なかった。
くるりんと名付けられたその丸まるとした目のままでいたから、本当にまだそこにいるようで。ただ少し疲れて横になっているだけのように見えて仕方なかった。
オヤジや叔母のことも見てから旅立ちたいようにも思えて、獣医にも「このまま連れて帰ります」と告げた。
綺麗にしてから戻りましょうね、と言われたので待っているとキャリーバックにおさめられて戻ってくる。「帰ろうか」と声をかけると、また涙がでた。看護士も獣医も涙を流してくれながらも、「家族の方に最後まで一緒にいてもらえて本当に良かった。最後、一人で亡くなる子も多いから」と我輩を慰めてもくれた。駐車場にまでスタッフ皆が出てきて、我輩の車が発進するまで待ち、最後には頭を下げて見送ってくれた。
「あんた人間のようじゃね」「よくしてもらったね」と声をかけると、本当に泣けてしかたなかった。
かかりつけでもないのが、最後の最後だけ休みの日に飛び込んできたと言うのに。どこまでも良くしてもらって。本当に有り難いことだった。
家に連れ帰ってからは、クッションに寝かしてやる。すると本当にまだそこにいるようで。「オヤジが帰ってくるから待っといで」と声かければ首を起こすような気もした。
我輩は残していたことにとりかかった。
布団に尿漏れがあったので、コインランドリーに出かける。洗濯機をかけてから駐車場で待つ間、みすずのネームを描いた。何もしないでいると考えてしまうんで、何かしておきたかったのだ。
その日が、三月二日。
二月が終わり春を迎えようとする頃。朝から降っていた雨もあがって、まだ半分暗い空に虹がかかっていた。
それが我輩には彼が向かうところにかかる橋にも思えた。すっかり軽くなった身体で、家にやってきたばかりのやんちゃな姿で旅立っていくのだと思えて、何度か手をふってみたりもした。
オヤジが叔母が帰れば何か慰めになるだとうかと思い、その虹は写真におさめておいた。
家に帰ると疲れ果てて眠ってしまってその場には立ち会わなかったのだが、オヤジが帰ってきた折のこと、くるぼがあんまり綺麗に眠っているのでオヤジが勘違いしてしまい、しばらく声をかけていたらしい。それからようやく気づいて驚いていたそうだ。目が覚めてオヤジに会うと、「苦労かけたね」と労いの言葉がかかった。最後は我輩と一緒に過ごし、獣医先生には本当によくしてもらったのだと、よくよく伝えておいた。
これだけで終われば寂しいながらも綺麗な話としてまとまったろう。しかし現実というものは、どういうわけか綺麗だけでは物事を終わらせないらしい。
叔母が涙ながら遂げた火葬の、翌日のこと。
叔母とオヤジが喧嘩をした。原因はオヤジで、次に迎える犬の下見をしてきたというから、涙にくれていた叔母が怒ったのなんの。
看取ったのは我輩で、葬儀場へ運び納骨したのは叔母で。そういう粛々とした時間を彼と過ごした身からすれば、オヤジがもう次の子の話をしているなど信じられなかったのだ。
オヤジの方はオヤジで、「くるは卒業したのだと思ったら気持ちが楽になった」「次の新入生を迎える」などと自分の気持ちの整理ばかりを話すから、叔母がブチきれて「誰が面倒みるんよ!」ともうギャンギャン。
オヤジも最後を他の家族に任せきりにした負い目もあったのだろう、いつもならやり返すところを「いや次の子を迎える」とぼそぼそと呟いた限りでその場は収まった。であるから、喧嘩と言うよりオヤジが叔母にキレられたというのが正しいかもしれない。
大事にならずに済み、我輩もその時は「またオヤジらしいデリカシーのなさよ」と呆れる程度で済んだのだが。
しかしどうしたことが、後から急にムカムカきて、腹が立ってたまらなくなった。
何が卒業だ。なにが新入生だ。俺にあれだけのことをさせてといて、なにを自分の気持ちばかり話しやがる。てめぇの気持ちが楽になる理屈に、彼と向き合ったこっちの気持ちまで巻き込むな。
百歩ゆずって我輩の気持ちはいい、叔母も良かろう。しかしくるぼはどうなる。あんたに懐いて、最後まであんたには元気な姿をみせて、あんたを見送った後に旅立っていったあの子は。最後まで脈をうっていたあの心臓の持ち主は。我輩の問いかけにに、見えなくなった目で見上げてきたあの子は。
なにが新入生だふざけやがって! 頭にきて仕方なく、頭冷やそうと散歩に出かけても冷えるものでもなく、握ってきたライトを川土手に投げつけても怒りが収まらなかった。
なんなのだあの野郎は。自分の気持ちの話などしやがって。あれで一人の大人か? あれで誰かの親か。あれが我輩の父親か? 自分が勝手につれてきて、さんざん可愛がっておきながら最後は卒業したなどとわけの分からん理屈で片付けようとしやがる。一体、どんな教育をうけたらあんなふざけた事を抜かせるのだ。
オヤジに怒り、オヤジをしつけた祖母に怒り、我輩の家の筋というものに怒った。どうしてこの家は自分の話しかしないのだ。どうして少しでも他人を思いやれない。去って行った人に敬意を表わすことが出来ないのだ。
あんなのが俺のオヤジか。
こんなしょうもないものが俺の歴史か。
そう思うと悲しくもなった。そうしてぐらぐらする心中を抱えながら、くるぼの散歩道を歩き、彼にも話しかけた。
もしオヤジがお前のことをさっさと片付けて、居場所がないなら俺のところにくればいい。俺と一緒にればいいんだ。行く場所がなければ俺のとこへこい。ずっと俺が悲しんでいよう。居なくならなくたっていいんだ。居場所がないなら俺のとこへこい。
オヤジへの怒りやら、可愛そうなくるぼへの同情やらで、頭も胸の内も沸騰しきり、家に帰ることも出来ない。
歩きながら、また何かオヤジがふぜけたこと言ってきたらキレてやろう、「なにを自分の話ばかりしやがる! あの子にどう顔向けするつもりだ!」とブチ切れてやろうと心に決めた。
そうして最大の盛り上がりを見せた後、感情が疲れたのか、我輩も次第に落ち着いてきた。落ち着いた頭で考えてしまうのは、どうしようもないオヤジのことで。それでも考えれば、やはりオヤジも寂しい人なのだと思いついてしまう。
家族に総スカンをくらいながらも抱いていた子犬、それからも友人として一緒に寝食をともにしてきた。オヤジが一番可愛がっていたのは明らかで、食欲がないとなれば高い缶詰や犬用のスポーツドリンクも買ってきたものだった。
そう言えばと思い出したことには、子供が熱を出しても休むこともなかった仕事人間のオヤジが、くるぼの調子が悪いとなれば半日で仕事をきりあげては病院にも通ったもので。
よくよく考えれば、あの人は冷たいだとか薄情だとか呼べるほどの大したものではなく、ただた弱い人なのだという気がしてきた。
とにかく辛くて仕方ないから卒業だとか新入生だとか自分なりの物語を編んで、なんとかかんとか乗り越えようとしているのかもしれないと思うと、怒りもおさまり我が父ながら情けない気もしたがまあ許せる気もした。
だいたい、我が家というものが、やはり弱い人達の集まりで。いよいよとなると手一杯になり、どうしたって自分ことで精一杯になる人々の集まりだったなとも思い出す。
それは薄情や自分勝手と言うよりも、ひたすら弱さ、小ささで。腹をたてても、憎んでみても仕方の無いものだと思い出した。
「まあ許してやってくれ」とくるぼに話しかけると、我輩のなかの彼も満足そうにしている。さすがオヤジの親友である。あの人を我輩よりも知っていたのかもしれない。
家に戻れば叔母とオヤジ、それぞれに話をしてみた。
叔母には「オヤジの相手をしてもらうのにもう一度、犬を迎えても良い気はしてる」と告げると、向こうも落ち着いていて「まああのめんどくさい人の相手になってくれるなら」ということで了承を得た。
オヤジには「また飼ってもええみたいやけど、それにしたってくるぼのお骨が帰ってきてからにしよう」と話した。「自分が外に出されて、新しいのが入ってきたと思ったらくるぼも寂しがるやろ」と話すと、オヤジは泣いていた。
さっきまで卒業だとかなんとか言って、気持ちが楽になれただとか言っていたのに。
それから数日がたっても、いまだに寂しいようで「おらんくなったらつまらんね」と話してはまたすぐ声をつまらせて煙草を吸いにいく。
案外、くるぼが最後の時を我輩に選んだのも、オヤジの弱さを見抜いていたのかもしれない。オヤジにたくせば、オヤジが大きく傷つくと思い、オヤジは元気な姿で送り出したのかもしれない。そう考えると、なかなか孝行な犬だったなと感心するのだった。
三月十一日。
オヤジがついてきてくれと言うので、霊園に預けていたくるぼを引き取りにいった。すっかり春めいた日で、丁度彼が旅立った日を境に冬は終わったような気もする。
家に連れ帰ってやった彼は、しばらくはかつての定位置だったオヤジの隣の席につく。それでオヤジの気持ちも落ち着いた頃、庭にサクランボの木があるのでそこに埋めてやろうということになった。
花が咲き実がなれば鳥もつまみ、風がふけば田にも落ちる。そうして少しずつ、彼は旅立っていくだろう。弱いオヤジを見守りながら。
彼の名前はくるりん。
我が家の大変な時にオヤジに連れられやってきて、我が家の一時代を明るくし、オヤジを支え、最後にはオヤジには元気な姿をみせて、去って行った。
ありがとう、くるぼ。我輩は君の貢献を忘れない。
いつかお前の大好きなオヤジも、あの虹をわたる日がくるだろう。
その時は迎えてやってくれたまえ。弱い人だから友達が欲しかろう。虹をわたっていったヨークシャテリア。我輩の手のなかで去って行った小さな弟。
いつかまた会える日もあるかもしれない。
その時まで、グッドバイ!