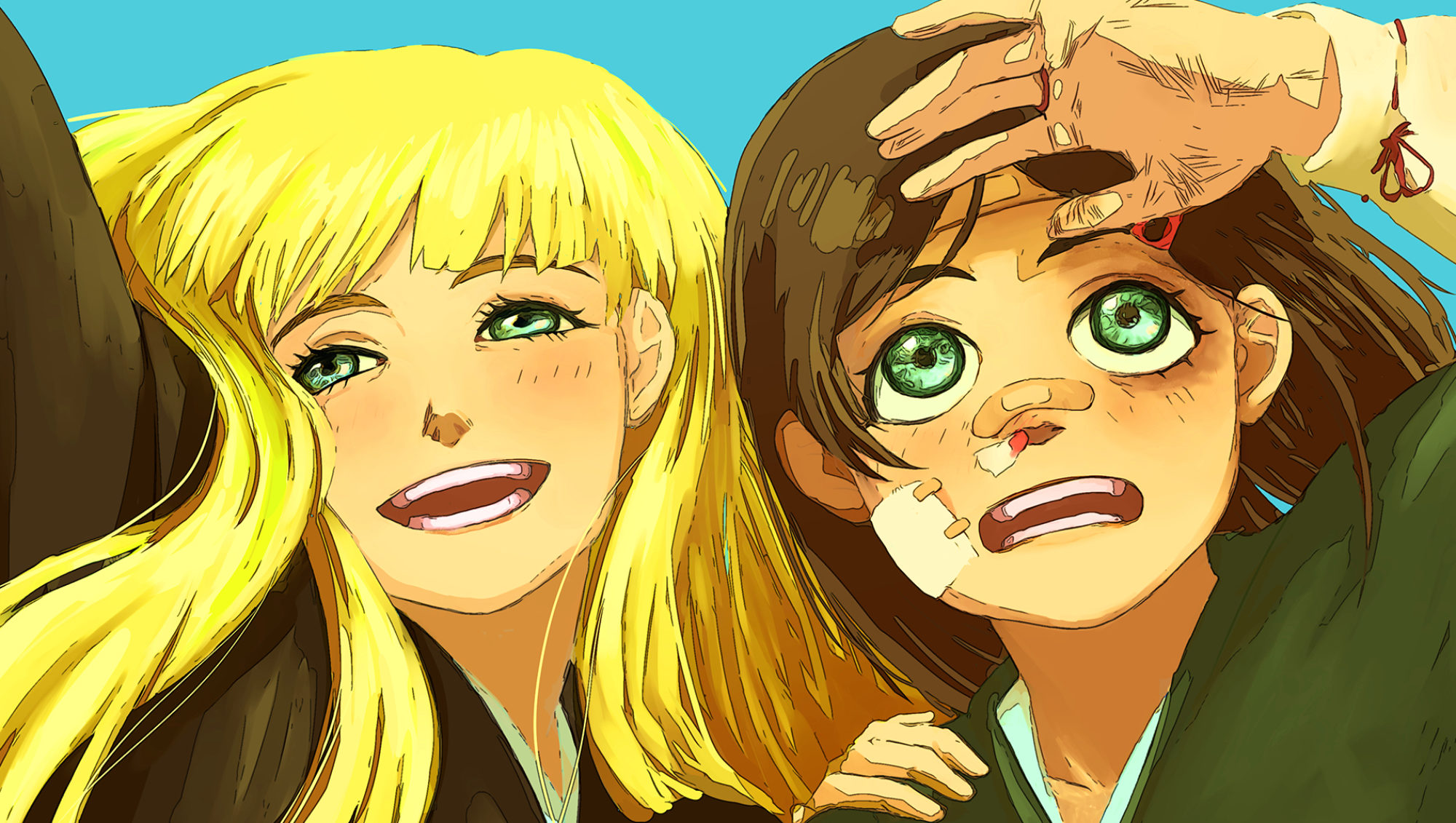進捗
ネーム 610枚(先月+140)
シナリオ 約110000文字(先月+0)
夏の時代として1970年代を書いている。この章の難しさは登場人物が増えること。それもまったくの新規ではなく、他のシリーズで登場した人物の若かりし頃だったり、誰かの親だったり。またそんな彼ら彼女等がそれぞれの青春時代として、瑞々しい感情を溌剌とさせて日々をおくるから、どう話をまとめたものやら。それぞれに動機があり、目的があり、行動がある。それを一つのカメラでとらえ、一つの物語として筋の上に仕立てていくのは難しい。
またこの章の主要イベントの一つであるEXPO70こと大阪万国博覧会の描写も困難を極める。
当時の様子を再現するため資料にあたるが、細かいところに手が届かない。たとえばソ連館のレストランメニューだとか。「モスクワの味」のキャッチコピーで知られていたパルナス運営によるレストラン「モスクワ」。1000席をほこる大レストランだったことは分かったが、そこでのメニューが分からない。仕方ない、パルナス経営の他レストランを調べ「だいたいこんなものか?」というメニューを考えた。そんなことを繰り返しながら大阪万博を再現しているので、フィクションで補強しながらの描写になる。そもそもフィクションの物語なのだからそれでいいのだけれど、リアリティを担保するためには嘘をつくにも努力がいる。それが手間だ。
夏の時代として描く1970年代。ネームにして240枚を超えたがまだ終わりが見えない。今月中にはなんとか形にしたい。いや、する。
苦しく暑かった夏も終わった。ここからは一気呵成の勢いで仕上げていきたい。
とりあえず、万博記念公園へのロケハンに近日行ってきます。
大阪万博
70EXPO、1970年万博の資料をあさりながら、一体この熱狂は何だったのだと考える。
あの時代に生まれず、そこから半世紀を経た今から振り返ると、いちいちの資料の暑苦しさに驚かされるのだ。
第一に、総来場者6421万人という数字が狂気だ。外国人来場者は170万人前後で、彼らを引いても六千万という数は無傷で残る。一人あたりの平均来場回数が2.8回あったことを考えても、2200万人以上の日本人が来場し、この祭典に参加したことになる。
たかだか一億人かそこらの日本人、その2200万人がこの祭典に参加したわけだから、コミケの人混みで音を上げている我輩からすればとんでもない。狂気。
1970年9月5日の土曜日には80万人を超える来場者があり、とうとう混雑のあまり帰宅難民をだして4300人もの人々が会場内で夜を明かしたともある。会場のそこここに転がる人々へトラックがまわって毛布をくばり、パンや弁当も配給されたという。
各国の国力と技術力をアピールするため、絢爛として現れたパビリオンたちの異相にも狂った熱意を感じる。
巨大であり、歪であり、いかに他者と違うかを誇る。違いとは優劣でありテーマとしてうたわれている「人類の進歩と調和」などどこふく風で見栄をはりとおし、競い合った。
来場者としてやってきた日本人も、それを待ち構えていた祭りの方も、どちらもとにかく暑苦しい、異様な情熱をもっていた。その軌跡を時代を隔てた今から振り返ると、今では理解しがたい熱量を感じ、それを狂気とも思うのだ。
何故、こんなにも暑苦しかったのか。
資料を読み進めるにつれ思うのは、このEXPO70への参加が、すなわち「日本人への参加」とみなされていたのではないかということ。
参加した人々の多くが、万国博覧会の意味さえ理解せず、「人類の進歩と調和」というテーマも諳んじることが出来ないまま、ただテレビや雑誌といったマスメディア越しの祭りに、「わたしもそちら側に行く!」という必死さをもって押し寄せたように思われる。
戦後25年がたち、テレビの普及率も9割を超えていた1970年。マスメディアによって作り上げられた「日本人」が全国津々浦々に浸透し、高度経済成長の風にのった消費を通して誰もがテレビの向こうの暮らし、雑誌のようなライフスタイルに参加出来た。農家の土間に洗濯機が持ち込まれ、床の間に茶箪笥のようなテレビが設置されては、「むこうがわ」へと漸次にじり寄っていく。
そういうマスメディア的「日本人」、「みんなであり私たち」への参加過程にあった人々が、一つの通過儀礼として挑んだのがEXPO70だったのではないだろうか。
つまりEXPO70への来場とは、最新の技術への関心や、月の石への好奇心でなしに、「私は日本人になったのだ」「テレビや雑誌の世界に参加したのだ」という憧れへの模倣行為だった。
そう考えれば、当時の人々の暑苦しさ、熱狂も理解出来てくる。
当時、日本には本当の意味でのマスメディアがあったのだ。そのメディアを通じた理想や憧れの暮らしがあった。そしてそこに、多少の無理をすれば、消費という方法を通して誰もが参加出来そうな気配がしていた。
どれだけ貧しくとも、今はまだ順番はまわってこなくとも、自分の時はくる。そういう期待に満ちていればこそ、機会に際して人々は狂った情熱をもって行動したのではないだろうか。
EXPO70に参加した人々の写真を眺めてみる。するとみんな、綺麗な一張羅を着ている。普段は畑でネギ束を担いでそうなカミさんが、ワンピースのスカートなどはいて笑っている。背に負う子供にも帽子をかぶせ、ストッキングなど履かせている。
けれどどうだろう、その姿勢と言えば背負い籠を負いつづけたあまりにか、前傾の癖がのこっている。服や靴ばかりが新しく、田舎で使い古された顔や手や足首が隠せていない。
数あるレストランを避け、ベンチに座って食べるのは、家で握ってきた手弁当である。卵焼きなど作ったろうが、握り飯に防腐のためしこんだ梅干しからは土間の暗い匂いがしたことだろう。
EXPO70の写真に写るのは、日本人になろうとしていた誰かたちだった。一張羅を着込み、弁当を下げて電車に乗り込んでやってきた、日本列島のあちこちにいた誰かたち。
その誰かたちの憧れへの参加の姿が、6千万という列をなして写っていた。
憧れへの参加を期待して来訪した人々をむかえた太陽の塔。その顔の不機嫌なことと言ったらない。岡本太郎は万博がかかげた「人類の進歩と調和」に強烈な「ノン!」を発するため、万博のどまんなかにあの巨体を突き立てた。文化人としての第一人者である彼からすれば、「進歩と調和」といって科学技術をかき集めては、それらで叶うとさせる水晶宮の未来像などは耐え難いものだったのだろう。
しかしそこへ参加したのは文化人などではない。幼い情熱をふりしぼって、憧れをたぎらせて、弁当をつくってやってきたのは、我が家に初めてやってきたテレビを床の間に飾る大衆なのだ。
その大衆性の萌芽、「テレビのむこうにいるのは私たちだ!」という嬉しさこそが、半世紀を経て我輩が感じる狂気の正体だったろう。
今、我々にはマスという同質性はない。国民として同じく追い求める憧れもない。信じている未来像もないし、参加を熱望する「みんな」というものもない。
そういう国民としての夢を見終えた時代にいるからこそ、半世紀前、国民として夢みていた人々の熱意に驚かされるのかもしれない。
EXPO70で語られた夢を見果てた後の我々は今、あの祭りのなかで一人不機嫌だった太陽の塔と同じような顔をしている気もする。