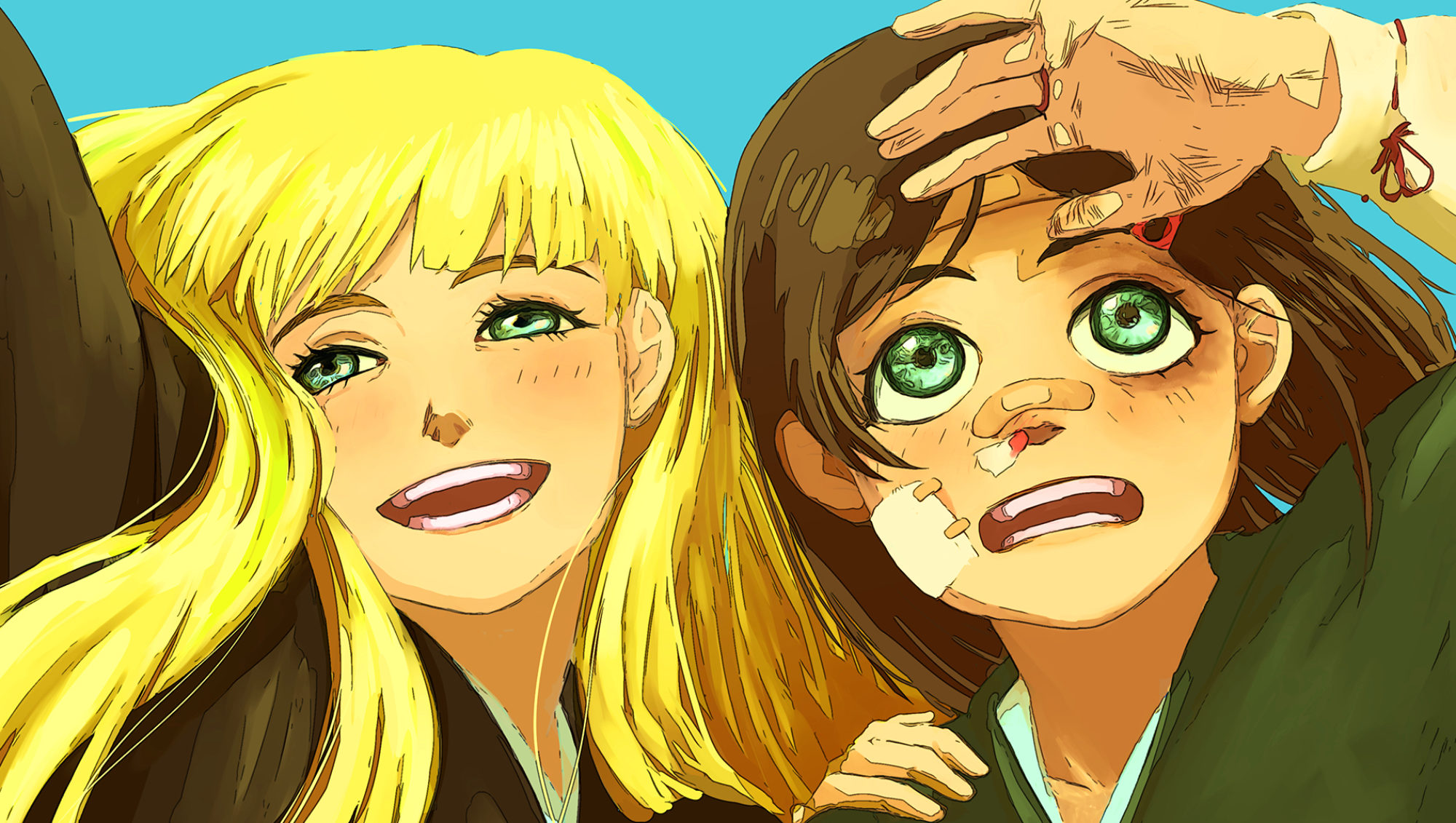決戦編のシナリオなおしがとりあえず終わり、オブザーバーへ提出を済ませた。
なおす段階でシナリオが脹らんだので、どうにか削れないかと模索している。最低でも一割は削りたい。
この度のシナリオ、書きすぎてはならない場所が多い。けれど書かなすぎて意味が分からんという指摘も多かった。
書かないことの匙加減でとても苦しんだシナリオとなった。
何度も繰り返すけれど、シナリオの真髄とは「何を書かなかったか」であり、「書いたもので、書かなかったものをいかに描けたか」であると我が輩は思っている。
それは「書ける」ものをわざわざ「書かない」のではなく、「書けない」ものを書こうと試みるために、「書けるものを書いて、書けないものをそれらで描く」ことを指す。
物語という時空間に構造をもつ情報群をわざわざ使用しているのだから、物語という伝達方法でしか伝わらない表現を試みるべきだと我が輩は考えている。
それが何かと言えば我が輩にとっては「体験」で、意図した体験を読者に提供出来ないかと日々頭を悩ませている。
プレイした読者の「体験」として思い出や記憶に残るような物語を作りたい。だからこそ書いてはならない。何故なら「体験」とはアクチュアルなものであり、その渦中にあっては「何が何やら分からない」ものであるために、「言葉で書く」というメタ行為を受け付けない。読者のアクチュアルな体験に対し、何か答えめいたもの、要約めいたものを差し出してしまえば、読者の掛け替えのない一人一人にとってオリジナルな体験は雲散霧消する。
言うなれば、体験しているという主体的読者の居場所を、物語から奪うことになる。
もちろん、登場人物が語ることはある。どう感じたとか、こう考えているとか、こう思うだとか。しかし語ることはあれども、それは人物の発言であって物語の発言ではない。あくまで物語渦中の出来事であって、体験している読者の隣で起こっていることだ。メタ構造的に上からの発言ではない。
登場人物を読者以上の存在にしたくない。
彼等は読者の隣で「こんなことがあって、こう思ったんだよね」と個人という適当な大きさによって発言するだけの存在に留めたい。
そうすることが、読者の物語体験を成立させる条件だと我が輩は思っている、現状。
またそのうち変わるかもしれないので、あまり真に受けずにどうぞ。
しかし物語を書き始めた十年以上前から「書きたくない」と言い続けているので、その理屈は変移していくだろうが、姿勢は変わらないと思う。
結局、我が輩は消費者の立場をとるとき、「書いてあるもの」が嫌いなのだ。
その根源的嫌悪故に、「書くこと」をなんやかやと理屈をつけ、避け続けると思う。
意図と人物の不協和
上記で物語のメタ的描写を嫌うとしながら、これ以後、おもっくそメタ的な話をする。
物語構造の話と言おうか。決戦編の執筆が「何故失敗したのか」を反省する時、どうしても「構造的挑戦」と「その挫折」を語らずにはいられない。
各編を飛び越えハルカの国という枠組みでの構造を考えた時、我が輩には目論む仕掛けがあって、決戦編にも「大構造上の役目」があった。それを果たそうとしたのだが失敗した。
それが決戦編の「失敗」の根幹だと分析している。
「失敗」と書くと決戦編は上手くいかなかったのか、と心配されるかもしれないが、そうではない。当初「こうしたい」と考えていた意図が機能せず、この機能不全を解消するために抜本的解決が必要となり、シナリオの大改変を行った。その結果として時間リソースが大きく削られた。この事を指して「失敗」と言っている。
物語のクオリティではなく、物語制作のためのリソース管理に失敗してしまったのだ。
過ぎてしまった時は戻せないので、せめてこの度の「失敗」がどのようにして起こったか、それを記すことで未来への投資に繋げたい。
星霜編は巨大な社会の中で、痛みもなく自己が崩壊していく身体性の喪失を描いた。(つもり)
ユキカゼは血を一滴も流すことなく、死の危険も一度として訪れなかったのに、恐怖にのた打ち回った。あんなに安全だったのに、寒くも痛くもなかったのに、空腹さえ覚えなかったのに、彼女は何を恐れたのだったろうか? 彼女が恐れたその「何か」を星霜編で描いた。(つもり)
だから決戦編は身体性を「もう一度思い出す」物語にしようと思っていた。ハルカの国、全編を通した構造上においても、此処らでもう一度「身体性」「アクチュアリティ」「肉体の復活」「身体的な生の実感」を描いておいた方が、最後に描かれる「自己の消滅としての死」にコントラストを与えるだろうから丁度良いと考えた。
それでこの度はユキカゼが忘れていたものを思い出す物語にしようと試みたのだが、それが全く機能しなかった。
物語を通して、ユキカゼは危険に晒され、血を流し、疲労し、暑さにうだり、寒さに震え、空腹を覚え、命の危険にあうのだけれど、それらは終ぞ星霜編で描いたもののカウンターとは成り得なかった。それだけのウエイトを持ち得なかった。
今更、ユキカゼの身体を痛めつけたところで、越冬編のような生々しさは演出出来なかったし、星霜編との対構造として意味があると思えるほどの体験には出来なかった。
ユキカゼを主体として物語を描いた時、あらゆる体感描写が滑りまくる。ユキカゼがかく汗も、流す血も、疲労や空腹もアクチュアルな体験とは思えなかった。痛みを与えたところで、疲労を与えたところで、ユキカゼは「今ここにある身体」を思い出すことはなかった。全ては「いつかの体験」という過去と相対化され、「今、ここ」の体験に夢中になれるほどのフレッシュさがなかった。
ユキカゼは「もう一度」「再び」と意気込んで新たな肉体体験に没頭できるほど、若くはないのだと痛感した。
我が輩が思っていた以上に、ユキカゼは老いていた。いや、「老い」というものが我が輩の思っていた以上に、人から瞬間の体験への集中力、アクチュアルの感受性を奪っていた。
想像した以上に、「老い」は人を自己の経験してきた物語(過去)の中に閉じ込めるようだ。
我が輩はユキカゼを再び「今、ここ」という現実(アクチュアル)に復活させうようとして、それを失敗した。
ユキカゼは「いつか、どこか」に囚われて復活出来なかった。
別にそれを悲観的に描いたつもりはない。と言って、おセンチに、ノスタルジックに描いて、懐古趣味にしたつもりもない。
まず「今、ここ」の身体性の復活を試みて、その失敗があり、我が輩がリアリティを感じられる描写に落ち着けた。それが「いつか、どこか」に囚われているユキカゼとなったのだ、結果として。
それ故に、我が輩はシナリオの大幅な改変を余儀なくされた。
物語体験の主体者をユキカゼからずらし、見えてくるものをずらし、見えた物の解釈をずらした。
そういう意味で、この度のシナリオ改変は不思議な体験だった。起こっている事はほとんどそのままに、違う視点で撮り直す。同じ時空間の出来事の中で、違うものを見て、違うことを考える。そんな体験だった。
何故、こんな失敗をしたのだろうか。
いや、そもそも問題はどっちだったのだろう。何処か失敗だったのだ?
ユキカゼの身体性を復活させられなかった事が失敗だったのか。
ユキカゼの身体性を復活出来ると思ったことが失敗だったのか。
現状、我が輩は後者だと思っている。
我が輩は「老い」あるいは「生きてきた時間」というものの力を甘く見ていた。だからこそ、根深い失敗になったのだと分析している。
人は老いていく過程で、自分の物語の中に〝否応なく絶対的に〟閉じ込められる。
この〝否応なく絶対的〟な力強さを、我が輩は舐めていたような気がする。それをユキカゼにガツンと分からされた気がするのだ。
我が輩はユキカゼの物語というものを、決戦編という新たな体験によって割ることが出来なかった。彼女から決戦編としての瑞々しさを引き出すことが出来なかった。
彼女からエネルギーが失せたわけではない。しかし彼女のエネルギーは、「今、ここ」という現実に依拠しない。過去の歯車より精錬される「遠くから歩いてきたもの」なのだ。
言うなれば歴史。
その堅さに我が輩の意図は跳ね返され、目論見は失敗したのだと思う。
作者は人物の経験に勝てない。作者の意図は人物の必然性に負ける。
構図的に上で思いついたアイディアは、下の賛成を得なければ成立しない。
その不成立、不況下をどの段階で感じ取れるか。何処で「上手くいっていない」と自覚出来るか。それが今後の課題だと感じた。
この度は最後まで書ききって、オブザーバーに指摘されて、気づいた。この自覚の遅さが、時間的リソースの損失につながったと思う。
今後は対策を模索しつつ、改善を図っていきたい。
もう十月かあ……。
物語って、なんでこんなに難しいのだろう。