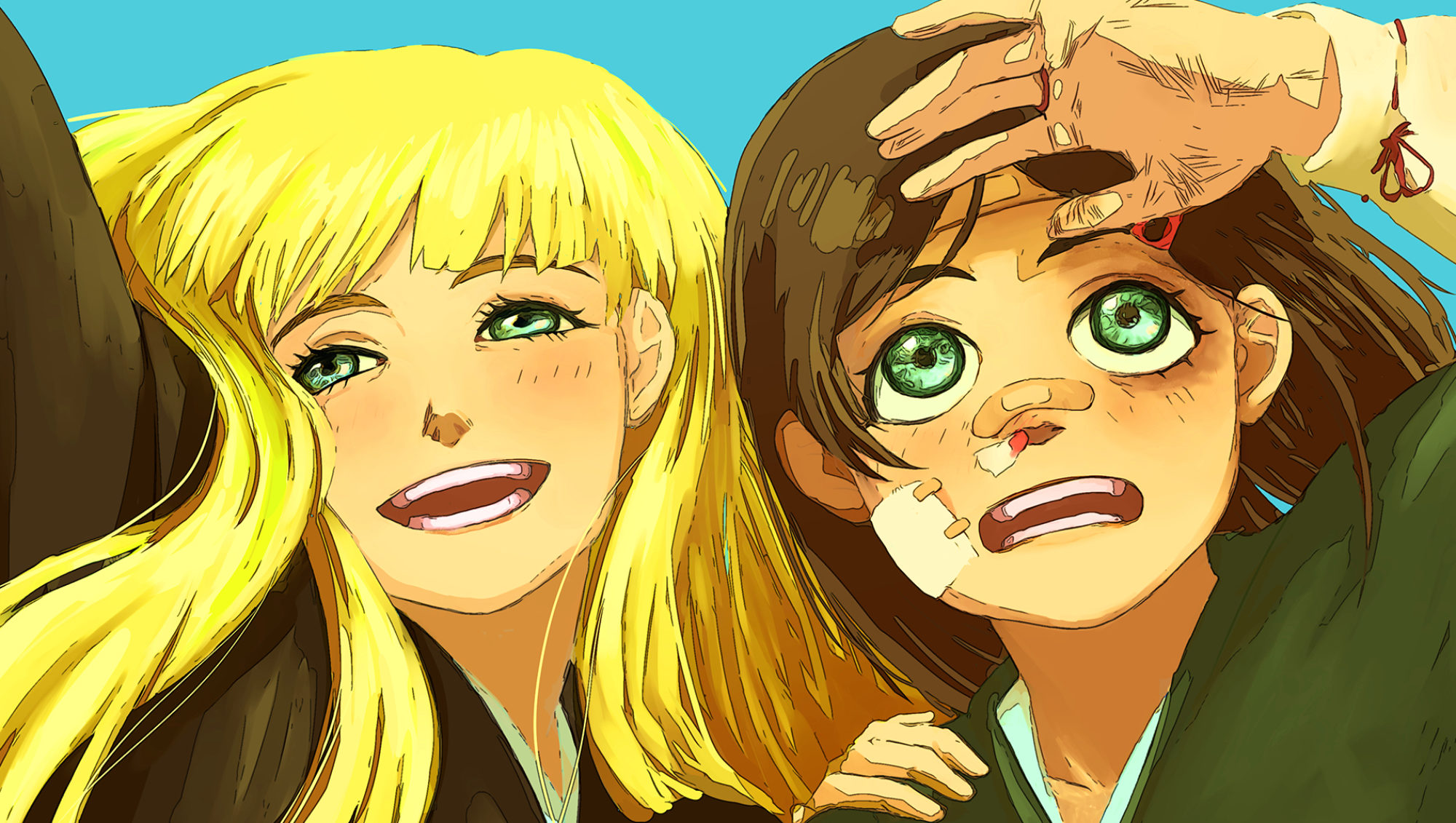進捗
ネーム 約700枚(先月+20)
シナリオ 約215000文字(先月+15000)
申し訳ない。
先月はほとんど進まなかった。数量的にプラスされたものも、物語上先に進んだわけではなく、既存箇所の変更と補強による。
水俣旅行を契機にスイッチが入り、もっと迫力あるものにしたいと改めて物語を見直したためだ。
もっとシンプルで、もっと強力な形がこの物語には必要だ。既存の物語を、より徹底的に我輩が理解しなければならない。春秋編は独立した一つの物語ではない。明治から始まったハルカの国が終わりを迎える物語だ。始まる物語ではなく終わっていく物語なのである。だから何が終わるのかを我輩が徹底的に、世界中の誰よりも高い解像度をもって理解しておかなければならない。終わるのはハルカの国だ。ではハルカとは誰だったのか、国とは何だったのか。ハルカの国とは、どういう意味なのだ。
十分と思い立ち止まっていた場所からさらに踏み込んで突きつめ、物語を描写する視座として磨きをかける。
春秋編はシンプルでなければならない。単純で強力でなければならない。
春秋編には間が必要だ。迫力を表現する間が必要。そのためにシンプルでなければならない。
迫力を演出するための間、そのための単純で強力な物語構造、そのための徹底的な理解。
寝ても覚めてもそのことばかり考えている。考えていると言うより、呪文のように唱え、願いのように祈っている。どうが我輩にこの物語を完成させる能力と幸運を授けてください。手を合わせては毎日、冒頭から読み返す。そんな日々を十一月は過ごしておりましたし、今なお過ごしております。
何が終わるのか見つけるために越冬編から決戦編までを見直した。
その中で、あらためて我輩の物語というものを知った。我輩の物語は面白いわけではない。我輩の物語の価値は、あるとすれば、迫力なのだ。あるシーンや、ある描写を、迫力をもって描く。そこだけが我輩の戦えるところ。
迫力あるものを見つける。迫力あるものを描く。それが出来てようやく我輩の物語は価値がある。
迫力あるものは見つけていると思う。今、我輩のなかにあって描きたいものは十分な迫力があるはず。圧倒的なものである気がどうしてもして、これを表現してみたい。
この迫力を否定できないのは、それが我輩の人生と直結しているからでもあろう。我輩が見つけたものだから、つまらないとは言えない。我輩は我輩が見つけたものに懸けるほかない。人は、その人が見たものによって、その人という座標を明らかにする。我輩は我輩が見つけたものによって我輩なのだ。
我輩が見つけたものは迫力があると思う。
けれどそれを十分に表現する方法と技術が、今の我輩にはない。
記憶力と画角が足りない。
我輩にもっと能力があれば、本当に凄いものを描けるような気がするのだけどなあ。
どうかそのチャンスを与えてくれないか。
毎日毎日、お願いお願いと、祈りながら作り続けております。
恐怖が終わり、祝福が始まる
春秋編の視座として、祝福という行為を突きつめている。
憧れは混乱し恐怖に転じる。その恐怖の克服は、祝福によって始まる。
これは時代区分だ。国や人や夢というものが、四季のように移ろっていく様だ。
憧れ、混乱し、恐怖したものが、祝福により一連のダイナミズムを閉じる。
憧れることも混乱することも恐怖することも勝手に始まる現象だけれど、祝福だけは意思によって始まる行為だ。最後の季節は、祝福という覚悟と行為によって始まる。
それ故に、我輩はこの時こそが、もっとも恐ろしい時代なのだと考える。
恐怖が終わるとき、もっとも恐ろしい時代が「祝福」によって始まる。逆説的ではあるが、祝福の時代こそもっとも困難な時なのだ。
祝福とは何か。
我輩がここで使うのは、日常生活の中で用いられる祝福とは目指すところが違う。我輩の言う祝福は、我輩なりの哲学用語だ。
めでたいことを祝うのに使うわけではない。祝福とは発見し、存在させ、存在することを了解するという一連の意思と行為を指す。
今、ここ、私というものを発見する。了解する。そこには諦めるという側面もある。
過去でもなく未来でもない今であること。何処かには行けないここであること。他の誰かにはなれなかった私であること。今、この瞬間、私であることを諦めて認める。そういう行為でもある。
祝福は良い悪いという価値を介入させない。祝福は良いことでも悪いことでもない。見つけて、存在を了解するというひたすら力強い行為そのものだ。
見つけること。見つけてもらうこと。私ここにいるね、貴方もそこにいるね、ここにいて他のどこにも行けなかったね、私たちはこんなだったね、という発見と了解が祝福である。
この祝福によって座標が発見され、座標の存在感(迫力)によって混乱と恐怖が克服される。祝福が恐ろしいと言うのは、見つけたものを認める勇気を必要とするからだ。もはや夢もみず、希望も抱かず、収穫の時を期待せず、「これであること」を諦める。諦めつくして祝福を始める。「これであったこと」という結末に触れて、祝福の心は動き始める。誤魔化しなくとことん見つけていき、それを認め、存在させていく。存在するものの迫力に正面からたちむかい、貫かれる。
その貫かれた感じを束ねて、ごうごうと吹きすさぶ中を生きるのが、祝福の時代の生というもので、その生は、夢を見るよりも、混乱し恐怖するよりも、ずっと厳しいものだと思う。
しかしどの時代よりも誤魔化しの少ない、迫力のある生を生きられるとも思う。
祝福の時は、一律には訪れない。ある夢にはある夢の、ある国にはある国の、その人にその人の時期として、祝福の時代は訪れる。祝福に挑むべき時がやってくる。
それでも大きな節目として、西洋近代から始まった「人間」というフィクションが祝福の時を迎えているような気もする。
人間というものを理想ではなく、限界のあった結末として認めることを強いられる日も近いのではないか。
そういう人間の集団である国も、美しい夢としての機能を失いつつあるのじゃないか。
古いものになっていきそうな人間や国が、退場を嫌って手足をバタつかせるヒステリックな様子が現代とも言えないか。いや自分の趣向にあまり大きなものを巻き込むのは止しておこう、我輩は我輩の範囲と向き合えばいい。それが我輩の限界というものだ。
恐怖は祝福によって次の季節へと移る。
ハルカの国は祝福によって次に進まなければならない。春秋編はこれまでの物語の、次なのだ。
祝福という迫力をいかに描き出すか。答えを見つけたと思っては見つかってないことに落胆を繰り返しもがいている。
いなくなった人たちへ。
これからいなくなる私へ。
いつかいなくなる子供たちへ。
やがて過去となる私たちの物語。
それは祝福という視座によって、締めくくられるはず。