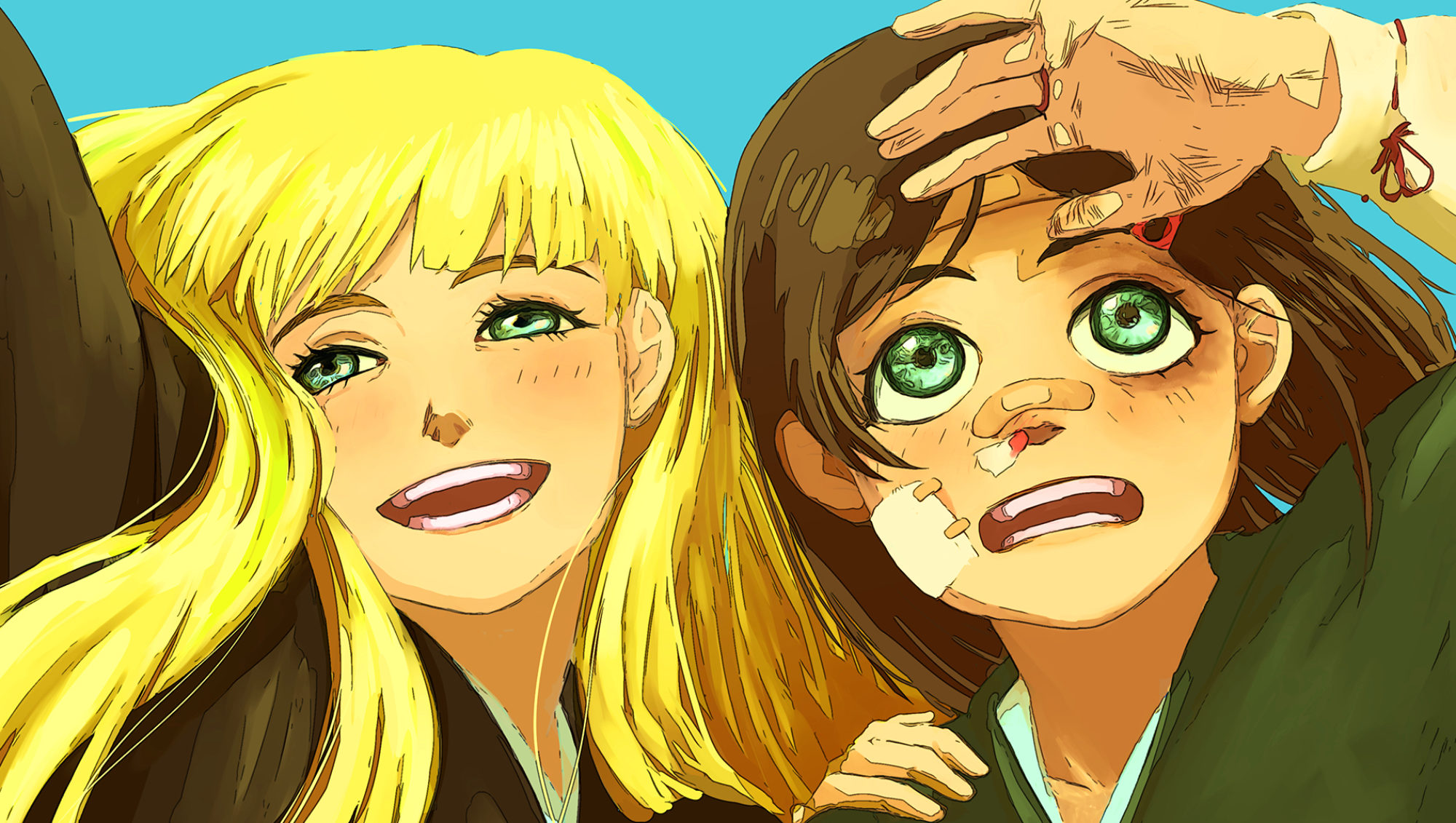進捗報告
スクリプトを組んでいる。
懐かしい立ち絵塗れ、立ち絵三昧の日々だ。毎日、毎日、会話の一つ一つに立ち絵をふっている。
立ち絵をふるのは本当に疲れる。どうしてこんなに疲労するのだろう? 思うに、人間の表情を伺うということは、人間にとってとても神経を使うことなのだ。相手の顔色を伺い、そこから内面を察するという行為には、観察力、注意力、また想像力がいる。
それらを活用するがために、立ち絵をふる作業には疲労困憊してしまう。そんな気がする。
星霜編の後半から立ち絵の振り方を変えた。
以前までは瞬間、瞬間に立ち絵をふっていたが、星霜編からはある程度の連続性をもたせるようにしている。眉の形が前の立ち絵はこういう形だったから、次はこういう形になるのが自然だろう、とか。表情変化に連続性を意識した。
立ち絵を使い回すために管理するのが面倒で、いちいちに立ち絵を作るようにしてから、こういうことも可能になった。前の立ち絵から眉の位置だけ動かす、口角だけ動かす、ゆっくりと笑顔にしていく、等々。
そんな微妙な変化をされても気づけないよ、と言われてしまうだろうが、気づかせないためにやっている。つまり、いつのまにか柔らかな表情になっていたり、いつのまにか悲しい目になっていたり。表情変化にグラデーションを持ち込んで、気づく人が、気づく時には気づけるような表現をしてみた。もちろん、そこまで注意深く見なくともストーリーラインの大筋は理解できるし、楽しめるようにはしている。ただ注意深く何かを探した時に、何かがあるような表現も置いておきたいなと思ったのだ。
また、このような静かな変化を持ち込むことで、大きな変化を目立たせることが出来る。
ストレートとカーブ。緩急あってこそ、それぞれが効果を発揮する。
目立つものを目立たせるために、目立たぬところは静かにさせたい。
連続性、という話で言うと、この度から背景とBGMも出てくる順番に並べて管理している。見返す時、聞き返す時、背景変化のライン、BGM変化のラインでそれぞれ追うことで、「色彩の変化に乏しいな」とか「静かなBGMが続いてるな」とか弱点を感知できる。
それぞれのラインにおけるチェックは前々からしていたけれど、ファイル管理があまく、いちいち探して手動でファイルを立ち上げなければならなかった。これが煩わしかったので、この度からは連続再生すればそのまま物語での登場順に並ぶようにした。
これでいくらか手間が省ける。
前回の制作をうけての改善、日々いくらかは進歩しているのだと感じる。
それにつけても個人制作には限界を感じる。
作業量が多いとかでなく、もっと良くしたいと思う箇所があるのにそれを改善出来ない歯痒さがある。
システム周りとか、インターフェースだとか、OP画面だとか。
もっと「手触りの良い」ものにしたい。物語にあったものにしたい。今はなんだが、ざらざらしている。これをもっとスムースにして、物語への没入感、物語へ入っていく段階を滑らかにしたい。
そこら辺、解決しようと思えば出来るのだろうけど、食指が動かない。アイディアが浮かばない。どうすればいいのやら。
どうしてもリソースをシナリオへ注いでしまう。シナリオでなら、他の作品に負けないアイディアを生めるような気がする。つまり〝勝負〟出来ている気がする。だからやる気がでる。けれどシステム周りは今更頑張ってもマシにはなろうが、勝負できるほどのものにはならないだろう。
我が輩にマルチな才能はない。というか、興味がわかなくなってきている。物語演出、情報構造、人間の認知過程――此れ等に対する技術研究と言おうか、突き詰めていくことに充実を感じる。途方もないものがまだまだ目の前にある気がする。この方向性で成長が見込めるような気がするし、結果としての物語体験は類似の少ない物になり得る気がしている。
「ここで勝負したら戦える」という方角がある。だからこそ、その他を疎かにしてしまいがちだ。それではいけないと分かっている。が、どうしても、気持ちがのらない。
ただ作品として皆様に届けるとき、ちょっとした配慮や努力が、皆様の「プレイ心地」を大きく改善することも分かっている
大切だと分かっているけれど、我が輩としては気持ちが乗らない場所、他者と比べて秀でているとは思えない部分、頑張ったところで勝負にならないと思っている項目は、他者に依頼する形をとっていくことも、近頃は考えている。
リソースが許せば、ね。
ただ我が輩は個人サークルを貫くので、創作仲間を募るつもりはない。他所様の力を借りることがあるのなら、それは外注で、プロフェッショナルな技術を提供して頂くという形をとるだろう。
ある階層の幻想の終わり
*まとめに向けてのスケッチ
*以下はkazukiが個人的に体験したり、見聞きした前時代的なエピソード。中には現代の価値観と照らし合わせると気分を害する物も含みますので、読む際にはご注意あれ。
*ハルカの国創作とはまったく関係ない、kazukiの一人語りなので読む必要もなし。
私たちは何処からきて、どんな夢をみたのか。
どこまで来て、どこへ行けなかったのか。
我々の正体とは何だったのか。
中流ごっこの終わり。
Kazukiのエピソード
小学生にあがったばかりの頃。
ゴミ出しに出かけていた祖母が、コミックボンボン(だったと思う)の束を持ち帰って我が輩を喜ばせた。我が輩はコロコロコミック派だったので、そこには読んだことのない漫画があふれていたし、またボンボンはコロコロよりちょっとエッチだったので、ませガキだった我が輩を喜は嬉しかった。
そうして喜んでいた我が輩をオヤジが見つけ、激怒し、祖母を痛罵した。烈火のごとく怒るオヤジに祖母は悲鳴のような泣き声をあげた。
我が輩もブルっちまって、ボンボンを読むどころではなかった。ちょっとエッチなボンボンの束は、出勤前のオヤジが掻き集めて元あったゴミ捨て場にたたき返した。
少年の頃、我が輩は持っているゲームソフトを売ることを許してもらえなかった。遊び終わったゲームソフトを売って、いくらかでも小遣いの足しになれば新しいゲームソフトが買えるのに、友達もそうして新しいゲームソフトを買うというのに、我が輩はそれを許してもらえなかった。
中古品を買うことも駄目だった。買うなら新品のゲームソフトだけで、中古コーナーに並んでいる廉価で面白そうなソフトには触れさせてもらえなかった。
「物を売るような真似をするな。中古を買うような真似はするな」
これもまたオヤジの方針だった。
もう他界した母方の祖父から、びっくりするような差別発言を受けたことがある。二十代の初め、仕事のついでに旅行がしたくて沖縄八重山諸島で職を見つけた。
そのことを祖父に伝えると、ひどく悲しい顔をして「なんでkazukiがそんなドカタのような仕事をするんか」と言う。「kazukiは頭がええんじゃけ、おらぁのようなドカタのような仕事をしちゃいけん」と言うのだ。
職業差別極まりない発言にびっくらこいたが、祖父に向かって職業平等について説こうとは思えなかった。ただ「ツアーガイドで海外のお客さんが来たら英語で対応したりするんだよ」と伝え安心させた。
ちなみに、我が輩の頭は良くなかったと思うが、祖父は最後まで「kazukiは頭が良い」と信じてくれいていた。祖父にとって我が輩が唯一の男の子(おのこ)の孫であった。
認知症にがすすんだ母方の祖母もまた、我が輩を「あんたは頭がええ。あんたはええ子」と可愛がってくれる。学業の成績はアホやったよ、と教えるのだが、そうすると祖母は「賢い顔をしとる」と切り口をかえ、孫の肯定を続ける。面はゆいばかりである。
そんな祖母が昔語りをよくする。
卒寿を過ぎた祖母の少女時代は戦前であり、彼女の青春時代は戦後である。その頃の話はまったくエキセントリックで、現代の人権や道徳を軽々と毀損する。
その中でも我が輩お気に入りは、彼女が下関で産婦人科の看護婦を勤めていた頃のエピソード。
戦後すぐだから堕ろす女性がとても多かったというのが祖母の談で、毎日「金盥いっぱいになった」という。
それを祖母が海に捨てにいくのだが、彼女は身長140㎝もない小柄で、それを捨てに行くのに金盥を抱き込むようにして持ち上げなければならず、その重いこと、匂いの酷いことには「えらいまいった」そうだ。
そうして、それを海の中に「あける」と、すぐに小魚たちがつつきに現れたそうな。「そじゃから彼処ら、市に並ぶ魚がおおけかったもんね」と祖母が懐かしむうちに、この話は終わる。
数年前の話。
父方の祖母から恵方巻きの安売りがあるので、買いに連れて行ってくれと頼まれた。
安売りがあるのはパチンコホール。要はパチンコ店が客寄せに恵方巻きの廉価販売をするというのだ。「一つ三百円で買える、他所で買ったら倍はするような大きいなのを」と祖母は倒置法を使うほどに勇むのだが、我が輩は「パチン○スのいるような場所に行きたくねぇぜ」とうんざり。
その時、我が輩はグスタフ・マーラーの交響曲第九を分からないなりに聞き、吉田秀和の解説本を読み、レナードバーンスタインの解説動画と照らし合わせながら必死に理解しようと努めていた。
そんなハイカルティベイトな時間を、パチンコホールで売られる廉価恵方巻きを買いに行くなどに邪魔されたくなかったのだ。
それでも祖母がせがむので車を出した。ホールにつくと、恵方巻き販売の列に並ばされた。そこはホールの中心通路で、とても目立つ場所だった。
まだ並んでいる客はいなくて、我が輩と祖母が先頭。販売開始より15分も早くついて、一番に並べたことを祖母は喜んでいたが、我が輩は列の一番に並んで物を待っているというのが恥ずかしかった。
パチンコ客からは珍奇な目でみられ、「そんなものよく並んでまで買うな」と嘲笑われている気がした。
次第に列へ並ぶ人々が増えていくのだが、我が輩たちの後ろに並ぶのは――ここでは描写し辛い様相の人々だった。
我が輩は自分の後ろに並ぶ人々を見ていて、血が凍るようだった。祖母は長くなっていく列を見返しながら「早く来てよかったね」と嬉しそうにした。
いよいよ列が伸びて、最後尾が見えなくなった頃だろうか。店員が歩み寄ってきて、我が輩たちに申し訳なさそうに告げる。
「今、恵方巻きを運んでいる車が遅れていまして、もう少々お時間をいただく形になると思うので、また改めて並んで頂いて……」
どれくらいかかるのだ、と尋ねると、「一時間少々」と返ってくる。
こんな場所に、こんな姿で一時間も居られるか。
こんな姿晒していられるか。
「馬鹿馬鹿しい、帰るで」と我が輩は吐き捨てるように言って、祖母の背中に手を添えた。足の悪い祖母を連れ帰ろうとした。
その時の、祖母の拒否。
列の先頭を離れたくないとした、踏み止まり。彼女の背中を押した時の、その場所に、パチンコホールの真ん中に根が生えているような居残り。我が輩を見上げて嫌だとふった首。
一時間でも待って、列の先頭に残り恵方巻きを買いたいとした彼女の心。我が輩は忘れられない。
我が輩は何事か怒鳴って祖母を引き剥がし、めそめそと泣く祖母を後部座席に詰め込んで、そこらのコンビニで二千円くらいする恵方巻きを買って、「こんなもんいるんならなんぼでも買うてやるわ、しょうもな」だとか言って祖母の隣に投げた。
帰りの車内で祖母が泣くので、我が輩も目の前が歪んでたまらなかった。
家に帰り着いてから、「ひどいこと言ってごめんね」と謝ると、「やっぱりkazukiは私の心がわかるんやね」と言われて、また涙が止まらなかった。
その時、我が輩は祖母の心が分かるのが嫌でたまらなかった。あんたの心じゃなくて、俺の心を分かれよ、と思った。
廉価品を買う列に並びたくなかった俺の心、パチンコ客に見られていたくなかった俺の心、自分の足の悪い祖母が一時間立ち尽くしてでも三百円の恵方巻きを買いたがった、それを見て凍り付いた俺の心を分かれよと思った。
我が輩は涙が止まらなくて、部屋に戻れず、散歩をした。泣きながら、自分はマーラーなんて聴くべきじゃないんだと思った。交響曲を理解出来ないのも仕方ない、当たり前だ。だって俺はあの列の先頭に並んだのだから。あの列の先頭を誇らしく思い、喜ぶ人が俺の祖母なのだから。そこに俺の根っこがあって、そこから俺はやって来たのだから。
俺はマーラーを理解出来るような〝流れ〟のなかにいない。
自分には無理なことが沢山あるんだと思って、涙がとまらなかった。
散歩から帰ると気分もかわって創作に戻れたけれど、今でも時折この日のことを思い出す。
マーラーの第九は今でも聴くけれど、やはりこの日のことを思い出さずにはいられない。
父方の祖母の話をもう一つ。
彼女は六人兄姉の下から二番目で、戦後に幼少期を過ごす。
長男が戦地帰りで、今でいうPTSDだったのだろう、酒を飲んでいつも暴れていたそうな。その長男が兄姉、自分、弟を殴り蹴る。それはまだいいのだけれど、自分たちの目の前で父や母を叩きまわす。それが辛くて仕方なかったと彼女は教えてくれた。
だからいつも一つ上の姉と弟と三人で逃げ出し、握ってきた小銭で饂飩の玉を買い、それを生で齧りながら涙をため「いつかみてろあの兄貴、私等が大きくなったらやっつける」と胸の内を滾らせていたらしい。
祖母の姉は去年亡くなった。コロナのことがあって葬式に参列出来なかったことを、祖母は残念がっていた。
ただコロナが流行る前、姉の様態が悪くなった折、オヤジが祖母に「会いにいってきや」とすすめて顔を合わせている。
その時、「兄さんをやっつけてくれんにゃこまるけ、はよ元気になってね」と声をかけたそうだが、姉の方は笑って「そねぇなもんは、もうおらん」と返したきたそうだ。2019年の夏のこと、彼女達が饂飩の玉を齧って泣いていた日からは七十年以上の歳月が流れていた。
祖母の姉は家族葬の中、大好きな孫たち(我が輩の再従兄弟たち)に見送られて旅を終えた。
もうおらん。
我が輩は祖母に聞かされた姉の言葉が、彼女達の戦いの、戦った日々への、手向けであるような気がした。戦いの終わりを告げるゴングの音のような気がしたものだった。
Thank for your fight. rest in peace.
彼女たちの日々に敬意を。
我が輩の彼等。
我が輩の彼女達。
我々は遠くに来たのだと思う。少なくとも、遠くを目指した。
戦後から高度経済成長を経て、新世紀へ。その七十年というフレージングの中で、我が輩たちは夢を見たのだと思う。
その夢の中で描いた自己像が、〝そこから歩いてきた場所〟を思い出した時、震えてしまう。その恐怖、その羞恥を隠すために、彼等は怒ったり、怒鳴ったりした。彼女達は故郷を忘れ去ることは出来なかった。
私たちは何処からきて、どんな夢をみたのか。
どこまで来て、どこへ行けなかったのか。
我々の正体とは何だったのか。
中流ごっこの終わり。
そう言ってしまえば、あんまり寂しい気はするけれど、それでもそれが日本の中でマジョリティが見た幻だったと思う。
我が輩は、我が輩自身を、日本の幻の中で生まれて、育てられた子供だったのだと思う。
我が輩は廉売品を買うなと育てられた。祖父に自分と同じ仕事をするなと言われた。
廉売品を買う列に並ぶことが悲しかった。
それでも我が輩は我が輩の愛すべき彼女たちの、故郷の暗さを、生まれきた場所の恐ろしさに惹きつけられて、彼女達の物語を忘れることも出来ない。
どうしようもなく、我が輩は〝そこ〟から来たことを感じる。誤魔化しきれない物語が、我が輩の中には流れている。
我が輩は時折それが嫌でたまらず逃げ出したくなるし、それでも時折泣いてしまうほど懐かしい。
我が輩は幻の中で子供だったのだ。
日本の、一つの時代に生まれて育った。その時代のフレージング、区切りが、今目の前にあるような気がする。今といって、今すぐじゃないけれど。
2050年には戦争経験者はこの世から消えるだろうし、高度経済成長期に「1億総中流」としてあらゆる世帯に少なからず蓄積した資本もある階層以下においては枯渇する。これをもって一つ時代とする。1950~2050年の百年をもって一つの幻の黎明期~黄金期~衰退期~終焉と考えるのはロマンチック過ぎるだろうか。まぁ我が輩はストーリーテラーなので多少ロマンチックに偏っていても許してもらいたい。
我が輩たちの子供世代くらいが、この時代の最後のフレーズではないだろうか。その先に新しい時代があるような気もしている
連続性の薄い、我々の価値観や道徳では乗り切れない世界が。新しいものを美しいと思う世界が。
新時代への興味は尽きないけれど、我が輩の出来る事は過去にある。また我が輩の愛情は過去へ向く。
1950年から2050年という100年間、これから過去となる時代に。
我が輩が勝手に一区切りとした、我が輩の勝手な時代区分に。
我が輩は夢の終わり、自分が育った幻の終焉を弔いたい。
自分の愛情と恐怖、憧憬と嫌悪への弔いこそ自分に出来る事だと感じた。自分のしたいことだと感じている。
今描いているハルカの国も、これから描く国シリーズも、それ以外の物語も、全てはここから発する物語でないかと思う。つまりこの動機は、近頃思いついたものではなく、ずっとあった自分の中の愛情だとか恐怖だとか嫌悪だとか懐かしさだとのかの総体であり、それを今は「弔い」と総称しているのである。
呼び名、名前は代わっていくだろけれど、我が輩の胸の内ある感情は変わらないだろう。その感情は我が輩たちの歴史でもあるから。
遠くへ。
それは我々の時代に限らず、人間が始まった時からの、人間らしい夢の見方だったと思う。
であれば、その弔いはやはり次の問いに集約される。
私たちは何処からきて、どんな夢をみたのか。
どこまで来て、どこへ行けなかったのか。
夢見た過程において、我々の正体とは何だったのか。
これを問うこと、問うた先を見つめることが、夢を見て時代に参加した人々、大きく言えば人間という過程に参加してきた人々への敬意になると思う。我が輩はその一部、極所に我が輩たちの歩みを偲ぶ故、弔いたい。死んでしまった、あるいはこれから死んでいく、我が輩の彼等、彼女等、我が輩、我が輩よりも新しいけれど、1950年からのフレージングに含まれる子等もまた。