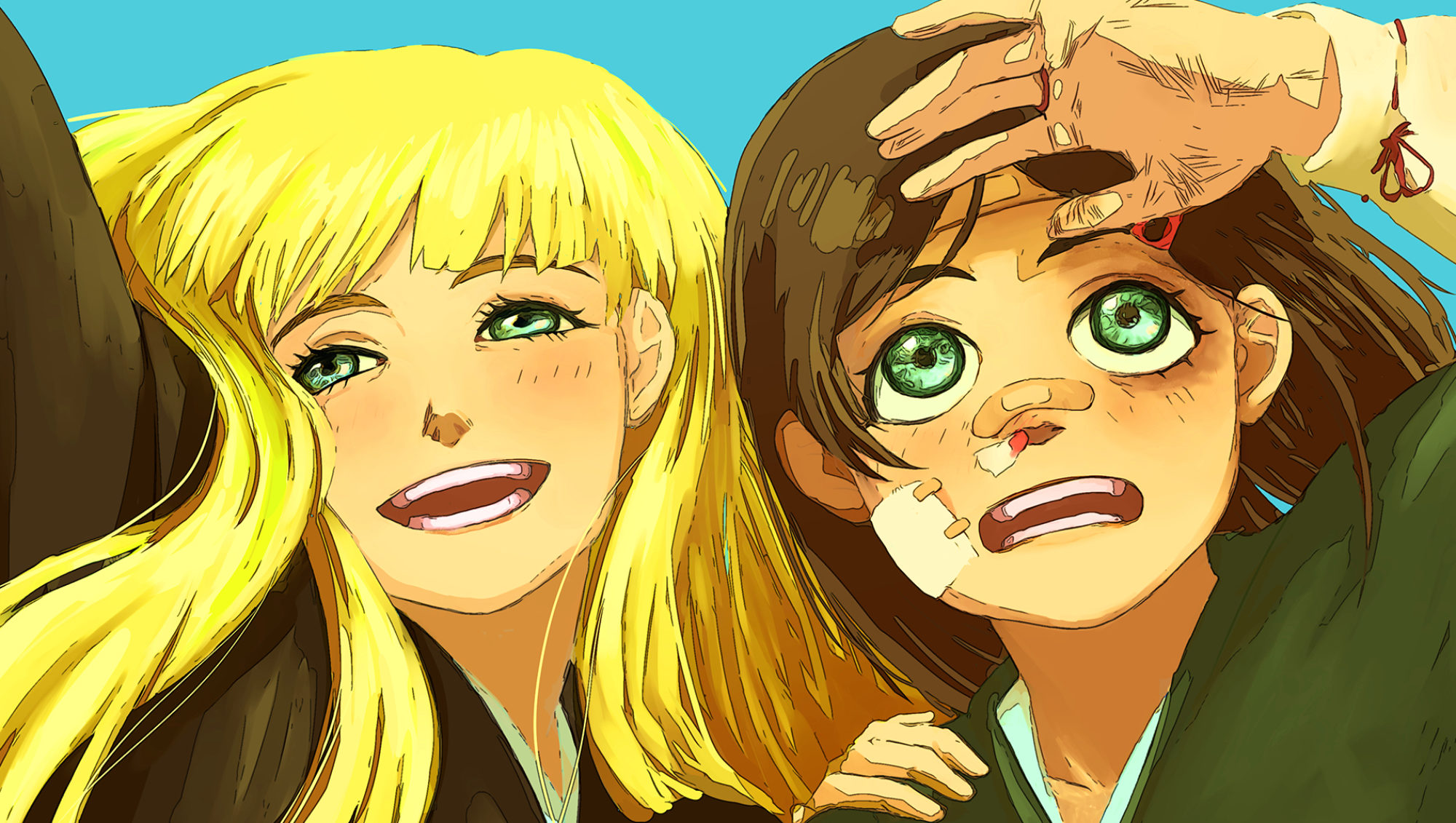精神力の省エネ技術
執筆において精神力の大部分がどこで使われるか。
物語のプロットを錬ることだろうか? 人物の会話劇にリアリティをもたせること? あるいは読者をアッと言わせるトリックを考えることだろうか。
我輩はそれらのどれでもなく、ただひたすらに執筆に向い続けるという自制力にあると考える。
日に二時間、毎日机に向かい続け、それを一度の抜けもなく一週間続けられるだろうか?
続けられたら大したものだ。恐らく、ほとんどの人は他人や会社からの強制もなく日に二時間の執筆を続けることはできない。
1日目、2日目は苦もなくできるかもしれない。しかし3日目、4日目ともなると机につくのも大変になってくる。一文書くたびに背もたれに身体を投げ出し、時計を見たり、携帯を見たり、横に積み上げている本をめくってみたり。5日目、6日目にはネットサーフィンをしているかもしれない。7日目に紛いなりにも机についているなら良い方で、寝てるか、ゲームをしているか、飲みに行っているか。
大体、そんなものだろう。
こうまで我輩が刺々しく、かつ批判的に言うのは経験則からである。
我輩はかつて小説家養成学校に通っており、クラスメイトは四十名ほどいた。
二年に上がる頃にはクラスメイト自体が三十名ほどに減っていたと思うし、そのうちで在学中に長編を完成させたことがある物は十名もいなかったと思う。
小説家になりたい、と志し、高い金を払って学校まで通っていながら、四人に一人しか長編を完成させなかった。それも十人中七人は十万字に満たない長編を一本、辛くも書き上げ、教師からの辛辣な添削をくらいあえなく情熱の炎を消したという、その程度のものだ。
上手い下手はおいて、我輩はよく書いた。いつも教師がひくくらいの原稿を持ち込み、何度も何度も添削をくらい、その度に書きなおしては長編を完成させた。二年の在学中で書いた長編は11本、短編2本。総文字数で言えば百五十万字は越える。
まぁそれでデビューもできなかったから文才の方は大してなかったのだろうが、書く力だけはあったと思う。
今でも執筆期間に入れば1日一万字をノルマにして6~9時間は書く。
集中の技術
さて何も自慢ばかりがしたいのではなく、我輩が言いたいのは、我輩が何故飽きることもなく書き続けられたかと言うことで、恐らく集中する技術があったからだと思っている。
我輩は精神論も嫌いではないが、どちらかと言えば理論の方を好むので、いかにして執筆を苦しまずに行えるかを考えていた。
その中で役に立った方法を理屈を交えながら少々紹介したい。
作業環境を整える
前回、意志のコントロールの仕方で、脳は否定を理解しない、という話をした。
作業机の上に漫画やゲームは置かないこと。出来れば遊びで使う机と作業で使う机は別々にした方が良い。可能なら寝室で作業するのも避けたい。寝室は頭が「寝る場所、休む場所」と記憶しているので、疲れるとすぐにベッドで横になったり、リラックスしたくなる欲求がおこる。
インターネットとのつき合いは難しい
十中八九、執筆の邪魔になるのは確かだ、調べ物には欠かせない。調べる時間と、執筆の時間を別にすることを試みたこともあるが、執筆途中に次々と調べたくなる箇所が浮上し、放置しているとどうにも気持ち悪い。この方法は失敗した。
とりあえず携帯で調べ、パソコンのネットはつながないようにしている。
パソコンでつなぐといつもの癖で動画サイトなどにとんでしまうのでいけない。しかしスマフォもどんどんネットサーフィンの快適さがあがってきているので、そのうち新たな打開策が必要となるだろう。我輩もインターネットとのつきあい方は未だに悩んでいる。
意志の種をまき、行動の苗をそだて、習慣をかりとる
まずはやはり意志がいる。毎日2時間、机の前に向かうと決意する必要がある。
決意の後はさっさと行動に移す。御託はいらない。意志と行動は光りと音ほどの差もあってはいけない。
さて、一週間も行動を繰りかえしていると、苦しい期間が終り、ぐっと楽にノルマをこなせていることに気づく。これが行動が習慣にかわった瞬間だ。こうなれば後は楽だ。持久走でいうところのセカンドウィンドウが吹き始めたところにあたる。後はこの習慣を切らさないようにノルマをこなし続ける。ただ忘れてならないのは、習慣は毎日行なうから習慣なのであって、人間易きに流れるのは簡単、一度気を抜けばまた最初からやり直しである。
いちいち感動しないし、落ち込まない
これは我輩の持論であり、あまり理解を得られないのだが、執筆中に感動したり落ち込んだりしないほうがいい。極力事務的に作業を行ない、するべきことをする。
よく自分の作品に泣いたり笑ったりできなければ、他人を泣かせたり笑わせたりすることはできない、というが、あれは第一稿が完成した後に泣いたり笑ったりすればいいだけで、執筆中は明鏡止水の心で挑むべきだと我輩は考える。
何故ならいちいち自分の手元で書かれていくシーンに泣いたり笑ったり感動したりしていたら疲れるからだ。とても何時間の執筆に耐えられない。
執筆とは日に三度口にする、日常の料理である。十代の女子が初めての彼氏のために振る舞う気合い入りまくり徹夜で仕込んだビーフシチューとは違う。結婚歴二十年でそろそろソファのクッションと旦那の区別がつかなくなってきた主婦がそれでもつくる朝食であり昼食であり夜食なのだ。
毎日毎日何の感動もなしに作りながら、それでもそこには野菜を多めにしようと無意識のなかに家族を気遣う心があり、クッションと区別のつかない夫の塩分を気にする心もあり、上手いとも不味いとも言わない男所帯だが皿が綺麗に片づくと、おかわりがあると仄かな喜びもあり――そうして何年かに一度、クッションと思っていたら夫だったものから「あれ上手かったな、あれ」なんて妙なところで言って貰える……そんなものなのだ、物語とは。
第一、自分の手元でできあっている出来たてホヤホヤの物語にのぼせ上がってたら、後で他人との温度差に悲しい目にあうのが必至。
料理が食べる人のためのもであるように、物語も読む人のためのものである。自己満足で終ってはならない。
良いシーンができたら「良かった」と思ってさっさと忘れ、上手くいかなければ「どこが悪いのだろう」と冷静になって分析をかければいい。
やることはわかってる。良かったら次、悪かったら問題の洗い出し。これを静かな心で、毎日淡々と繰りかえせばいい。そうしたらある日、終りが近づいていることに気づく。