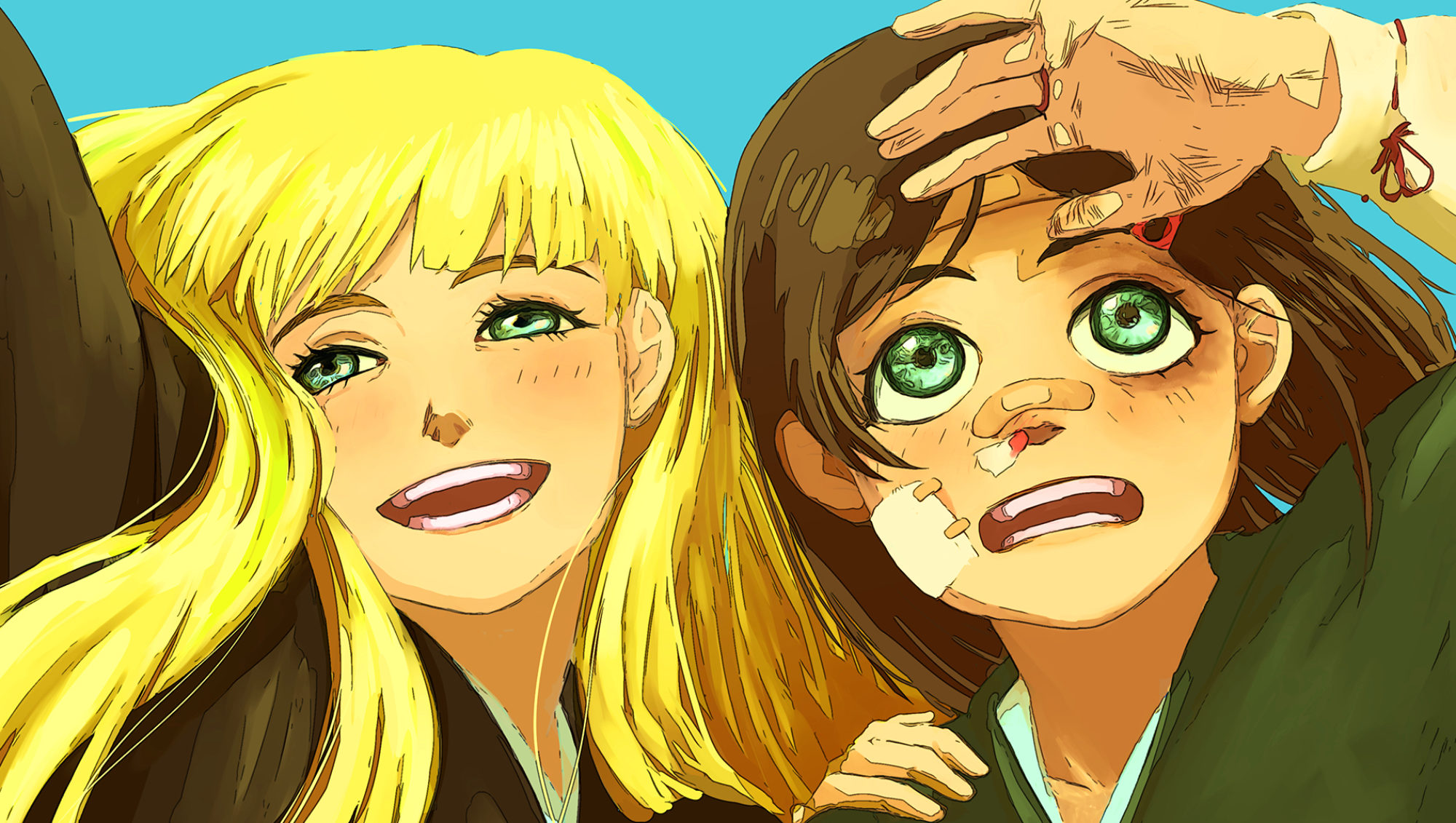進捗
ネーム 650枚(先月+40)
シナリオ 約180000文字(先月+70000)
9月は7~8月に描いたネームをシナリオへと移した。また前回までに書き終えたシナリオの加筆修正をした。
1970年代を舞台にした「夏の時代」を執筆中だが大きな問題がある。視点人物であるユキカゼの不在をどうするか。
子供たちは山を抜け出し万博に向かう。ユキカゼとハルカは彼らを送り出し居残る。カメラは子供たちを追跡し、彼等が出くわす感動を共にする。
ネームとしてビジュアル表現をしている限りは良かったが、文字媒体であるシナリオへと移すと途端に辛い。視点人物の不在がノベルゲームとして機能不全を起こすのだ。
春秋編を執筆する前から、この視点人物の問題には思い当っていたし悩んできた。
この度の物語、ユキカゼの所在ばかりが物語の所在ではない。ユキカゼが知らぬところでも物語は成長していく。ユキカゼが見つめた物語ではあるけれど、ユキカゼの物語ではないのだ。ユキカゼが何を見たかという能動性においては、彼女の物語であったとも言えるのだけれど。
これを解決する策として事前から考えていたのが、時間軸を長くとった視点。要するに、その瞬間は知らなかったけれど、後から見聞きして知り得た、という視点。
ユキカゼは手紙を受け取るのだ。長い長い手紙を、ある人物から、ある出来事の後に。そこを経て、当時では発見できなかったものを、ユキカゼは時を経て発見していく。
このような時間軸を俯瞰しているユキカゼをつくることで、視点の不在を克服していけないかと考えている。
しかしこの手法にも困難がつきまとう。
まず認知の格差を時系列でしっかり整理しないとならない。どこで、誰が、何を知ったのか。それをどう思ったのか。
また心の二重性もうまくコントロールしなければならない。当時の感情をとらえつつ、その後に芽生えた感情も、一つの視点、地の文の中で同居させなければならない。
また手紙によって何かを知らされたということは、手紙を書いた者の心も届いている。何故、そんなことをユキカゼに手紙を通してまで伝えたかったのか。伝達の動機というものが情報に交じり、これもユキカゼの視点として処理していかなければならない。
何重もの情報を取り扱いながら、地文として機能させることの難しさ。頭だけでは追いつかないので、ノートを使い、図を使い、年表を使い、なんとかこなしている。
近頃、とみに思うのは思考力が衰えてきては「国シリーズ」は書けない、40代でケリをつけないと「国シリーズ」は手に負えなくなるということ。
正直、今でも我輩のスペックをオーバーしている。ちゃんとコントロール出来るのかと不安で仕方ない。
まずは試してみたい。上手くいかなければ、また考える。
石牟礼道子
久しぶりにエキサイティングな読書体験をした。
石牟礼道子の「椿の海の記」、この本にはあらゆる意味で心を動かされた。前半分は単純に感激し、後半は作者との決裂に苦しんだ。
何故こうも作者と〝違う〟ことに苦しむのか。他人が自分と違うことなど当たり前なのに。
作者との違いを裏切られたと感じてしまうほど、読書体験において我輩は作者に同質化していたのだ。彼女が見つけるものがことごとく心地よかった。その心地よさをひきあげられた時、読書の中で孤独を感じた。
感動や快ばかりでなく、苦しみや孤立も提供してくれた読書体験。
我輩は今、多少むきになってこの作家を未だ追っている。
画角という思想
創作には画角というものがある。それはビジュアル表現をしない文体にさえ存在し、作品がとらえる世界を読者に知らせる。
何をどこまで視野におさめるか。どう捉えるか。そこに答える画角は、作者の思想であり哲学だ。
小津安二郎の映画に我輩が安らぐのは、彼の画角に我輩が親しむから。それは小津の思想や哲学に親しんでいることと同義だと思う。
画角を感じない作家に魅力を覚えないのは、彼等が思想や哲学が欠いた結果、デザイン性の劣る作品を提供するからだ。
凡才には画角がない。偉大な作家には、必ず画角がある。
石牟礼道子には画角があった。我輩はそれに親しんだ。しかしそれは我輩の追い切れない変化を遂げて、我輩を置き去った。我輩にはそれが素晴らしかった画角の劣化にも思えた。あるいは我輩がついていけない進化なのかとも考えた。
哲学思想が作中で劣化や進化することなど有り得るのだろうか? 考えられるのは、より大きな全体性をもった画角があって、我輩はその一部を覗いては感激したり、傷ついたりしていたという可能性。
止揚を待つ全体の中で、我輩は矛盾する部分を発見してのた打っていたのかもしれない。であれば、我輩は石牟礼道子の思想の大きさにあてられたと言うことになる。
一体、真相はどうなのか。はやるような、恐れるような気持ちで次の本を待っている。
代表作である「苦海浄土」が近々届く。しばらく、とことん、ぶつかってみたい。