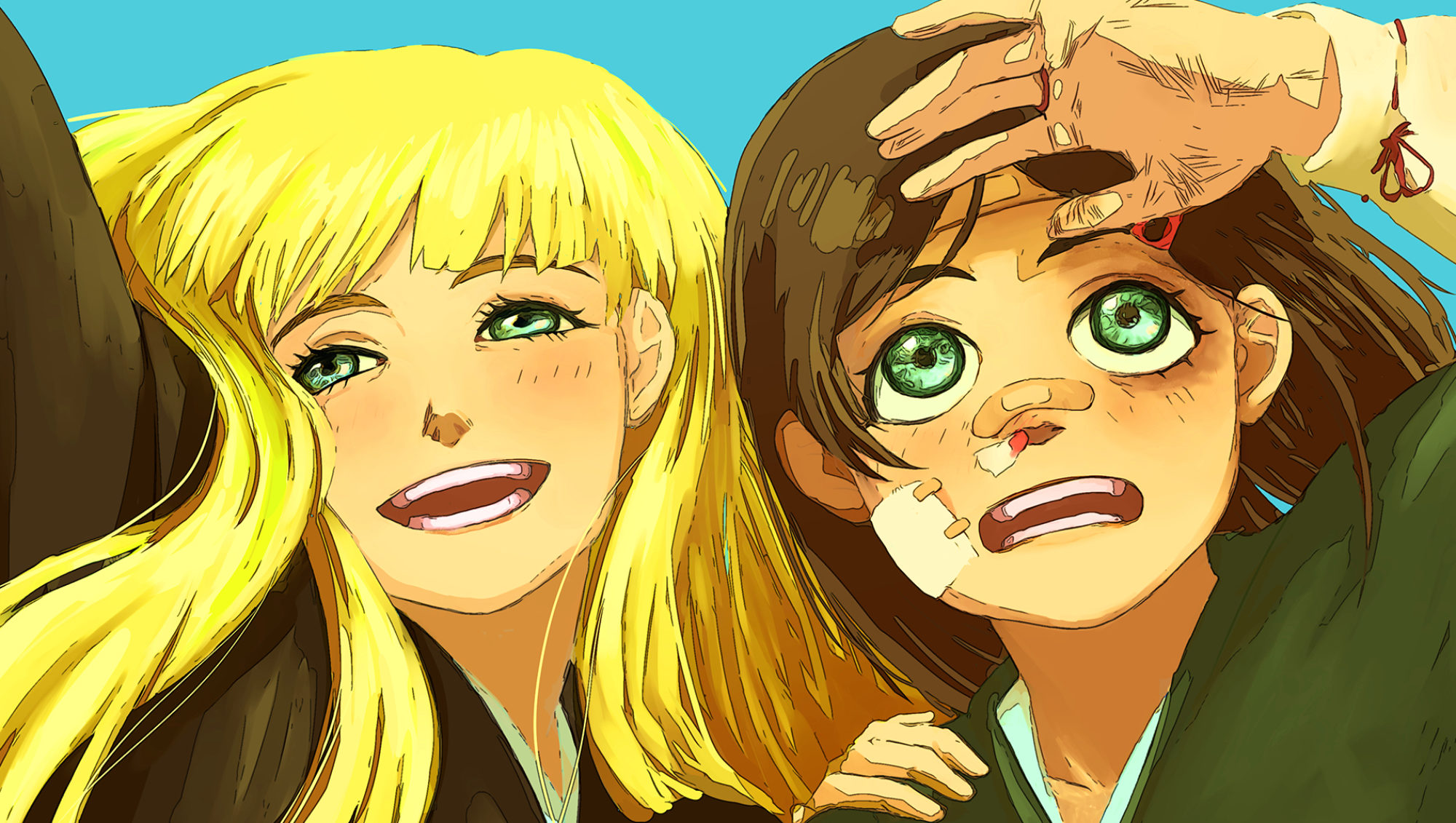進捗報告
ネームを150枚ほど描いた。これが冒頭部分にあたる。一度シナリオにしてみて状況を判断したい。
難しいのは冒頭も冒頭、ど頭からしばらく続くシーンで。これは決戦編の最後から続くシーンなのだが、台詞のないトーキーアクションになりそうなのだ。ひたすら絵で見せる方が迫力があると思っている。用意しなければならないビジュアルの枚数にも戦くのだけど、それよりも悩んでいるのはタイミングとテンポ。台詞、地の文のないシーンをどうコントロールしたものか。
前回、決戦編ではクリックによって演出やシーンが切り替わるようにした。全て読者側の任意でテンポが決まるようにしたのだ。
これはあまり良い結果にならなかったと反省している。一定のリズムでクリックを繰り返している読者にとって、特殊な演出シーンに切り替わったからといって指先のリズムを緩めるのも難しく、意図しないスキップを生んでしまったように見受けられる。
その反省を踏まえ、決戦編の一般公開Verには演出に任意のウエイトを置いた。星霜編までの方式である。
上記のことを考えると、クリックを任せきってしまえば意図しないスキップが発生する等、狙った演出から外れる可能性が大きい。
と言って、一連のビジュアル絵巻をただ黙って眺めているというのも辛い。一定以上の時間、コントロール出来るものがないとストレスになる。これは我輩自身、そう感じる。
折衷策として、重要な演出のみウエイトを指定し、ある程度はテンポ感を読者に任せる方式をとろうとは考えている。
この匙加減が難しそうだと、作る前から悩んでいる次第。
とにかく序盤の迫力を担保したい。迫力をつくるには演出が重要で、演出にはデザインされたテンポが不可欠。このテンポをいかにコントロールしつつ、此方側のコントロールを読者の非コントロール期間としてストレスに変えないか。
これは今回ばかりでない、ノベルゲームという「クリック」で進行を司っていく表現方法の一つの追求すべきテーマだと感じている。
物語を進めている。その読者体験を削がない演出方法を模索したい。
弔いと祝福
いなくなった人たちへ
これからいなくなる私へ
いつかいなくなるあの子達へ
やがて過去となる、私たちの物語
春秋編、永訣編とは何だろうか。毎日、考えている。毎日、答えを見つけるがまた考えてみれば新たに答えがでるので、模索の過程なのだとは思う。
その中で、ぼんやりと見えてきて、しばらく書き換わっていないのが上記のラインだ。
やはりこれは、いなくなる人たちの物語なのだと感じる。
過去にいなくなった人、今からいなくなる人、いつかいなくなる人。時間軸のなかで去っていく人々、それぞれへの弔いと、去って行く姿への祝福がこの物語がもつ眼差しというものではないだろうか。
そう、今は考えている。
最後の昭和編を通して、と言うより、ハルカの国全体としての最終章をもって、読者に体験して頂きたいのは主体としての減少だ。
自分が減少し、小さくなり、いなくなっていく気配を感じる。自分はいなくなるけれど、世界は止まらず進む。自分を置いて進み続ける人々もいる。
この世界から乖離していく体感、離れていく実感を体験してもらいたい。それすなわち、老いて死んでいくという過程の体験に他ならないと思う。
死を体感するエンターテイメントならありふれている。物語としても多くある。その中で我輩が演出したいのは、一生という時間軸のなかで「やがて」失われていく自己というもの。劇的ではない自己の喪失。劇的ではないからこそ、抗えない減少感というもの。
それを20世紀末という背景でやってみたい。
20世紀末とはすなわち、我輩の世代が、自己の世界観を作り上げた時代であるし、今ではかつてとして語られる〝昔日本と言っていた何か〟の揺り籠だと思うから。
もうあの時代の日本は残っていないだろう。それでもまだあれを日本だと思っている人々もいる。我輩もその一人かもしれない。頭ではなく、身体や感覚があの時代に居残って動けないでいる可能性はある。
我輩はそこに一つの墓をたてたい。自分が日本だと思っていたものの墓。墓は弔いである。
もうないのだと、消えていくのだと、見送る標として墓をたてたい。その思いもこの度の時代背景には託している。
我輩はハルカの国を通して、自分がどこにいるのかを学んだ。どこで生まれたのかも学んだ。どこからきたのかも学べたと思う。祖父母の時代、九州でボタ石をひろっていた何かが、今は我輩としてここにいて、そこからの結末を待っている。そう思っている。
これからの時代は、あそこからの延長線ではなく、一つの夢が終わった後の新たな時代になるだろう。新たな夢をみる時代になる。
新たな時代のプレイヤーを世代で区切れば精度に欠く。その人の能力、環境、資本、これらの総合的な結果として誰かは新たな時代のプレイヤーであろうし、誰かは閉じていく時代の影法師だと思う。
我輩はどちらだろうか。我輩に帰属先への意識はない、ただ、我輩が居残るここに墓をたてたい。弔って見送りたいのだ。その行為は一体、どちらの時代に属する者の行為になるのだろうか。
墓と弔いと祝福。これが今、我輩にとって何よりのリアリティなのだ。我輩の〝今〟なのである。
春秋編から永訣編を経る、昭和編。
この舞台には今までにないほどの思い入れがある。その思いの分析と描写が、上記した墓と弔いと祝福になる。
現状の課題
視点者としてのユキカゼ、ユキカゼが見ている対象としてのハルカ。この二つをよくよく考えなければならない。
前三部作がユキカゼの物語だったように、後三部作はハルカの物語になる。御仁とは誰だったのか。御仁と呼ばれたその人は、どんな人だったのか。それが明かにされる物語になる。
だがそれは同時に、それを見つめ続けた目という、視点者をつまびらかにしていく過程でもあるはずである。
何を見てきたか、「見てきた」という動詞によって、その述語の主語は特定されるはずだ。
ユキカゼは何を見て、どう感じ、何を考え、いかに動いたか。
人はきっと見ることから始まっている。他者を発見し、その発見の衝撃が自己の体感となり、誰かを見つめている自分を見つける。ユキカゼは彼女が見てきたものによって、彼女なのだ。
だからこれから描写されるのはユキカゼが見てきたものであり、見つめたというユキカゼでもある。
この観点から、ユキカゼの視点でハルカを描写しつつ、同時に、何かを見つめた視点という形でユキカゼをも語りなおしたい。それがハヤと御仁という100年の時を経た一つの現象の描写になるだろう。
ユキカゼの「見つめる」という動詞を、どう能動的な行動として、物語の筋にしたてていくか。これも一つの課題だ。
昭和編、物語として大きなアクションがある。しかしそれは、進み続ける時代の中で、その進行による軋轢が高まり、ついに大カタストロフに至るという言わば外からくるアクション。時代や世界がもつアクションである。
視点人物のユキカゼが能動的に起こすアクションではなく、ユキカゼが巻き込まれていくアクションなのだ。
その中でユキカゼが何をするかと言えば、やはり「見つめる」ということになる。激動の時代に溺れる人々、自分を含めた渦中を見つめる。乗り越えようとしていく自分や、御仁、あるいは新しき子供たちを見つめる。何故、「のりこえる」ではなく「それを見つめる」がユキカゼのアクションなのか。それはやはり、ユキカゼの物語が、星霜編で一つの終わりを迎えたからだ。ユキカゼは星霜編で決意した。あの決意以来、彼女は決意によって示された行動の中、その方角の歩みのなかにいる。
ユキカゼは決まった。だからこそ、ユキカゼの視点は彼女から離れたのだと思う。己さえ見下ろせる俯瞰へと至った。
その視点がやはり、ユキカゼなのだと思う。ユキカゼの瞳、化けながら涙を流すという希有な瞳、その瞳がこの度の物語の動詞になる。
ユキカゼは動くだろう。しかしそれは、ユキカゼの視点によって発見された、彼女自身という対象でしかない。
ユキカゼの視点、つまり読者と限りなく近いものが、この物語の動詞にならなければならない。筋として成立しなければならない。
「見つける」「見つめる」という動詞を、エンターテイメントとして成立させなければならない。
その難しさを、今は感じています。
いなくなった人たちへ
これからいなくなる私へ
いつかいなくなるあの子たちへ
やがて過去となる私達の物語
去って行った人々への眼差しがこの物語だとも書いた。
それは、ユキカゼの目であり、「見つめる」という動詞であり、すなわち、読者そのものでもあるのかもしれない。
提供したいのは、人々を「見つめる」という体感だ。いなくなっていく自分さえも見つめるという体験だ。
弔いと祝福に至るという、視点の体感を演出してみたい。