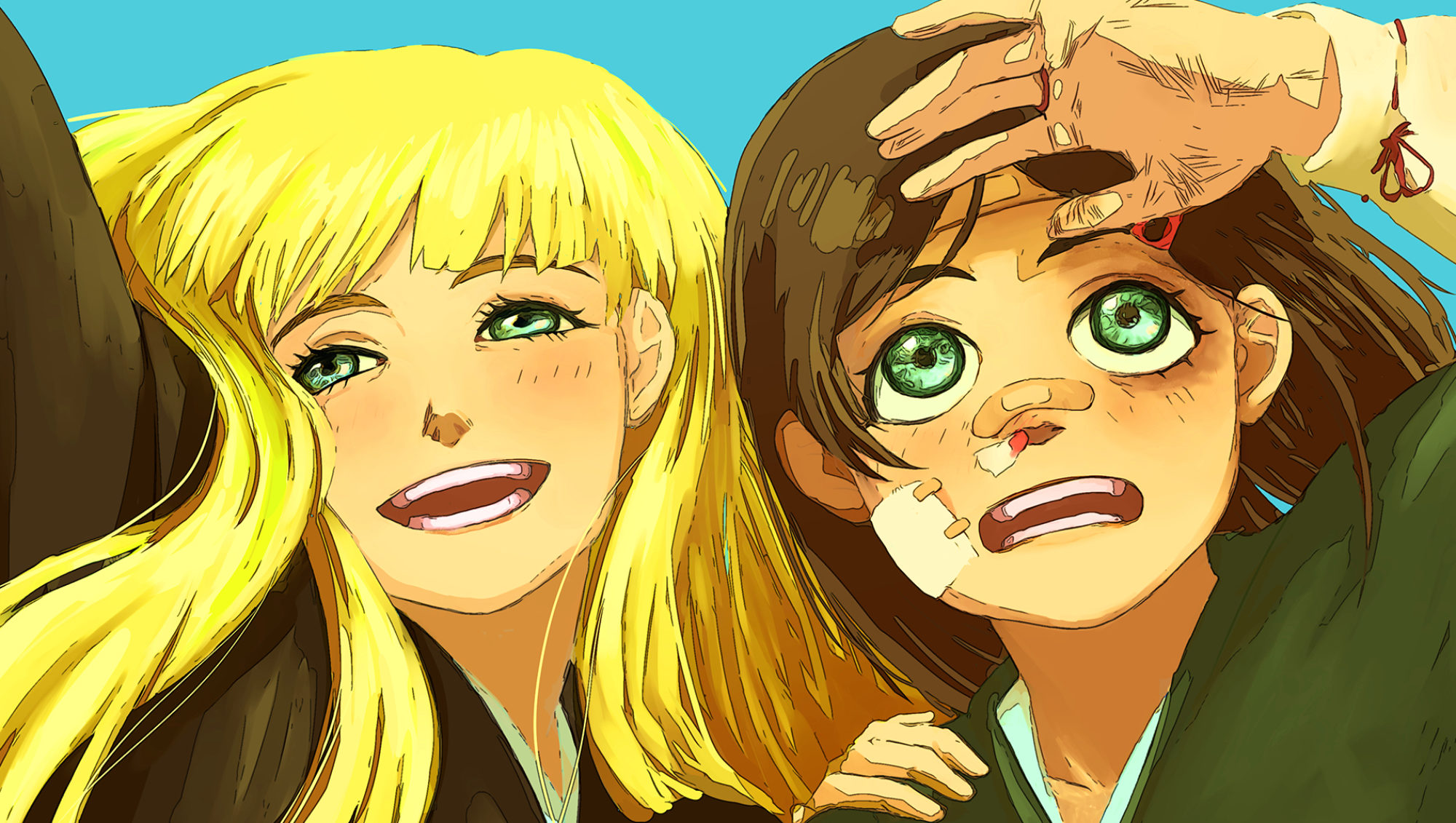進捗
みすずの国のリメイクが完成した。
この度は回想機能を実装し、イラストや音楽を鑑賞可能にした。その機能の実装にやや時間をとられた。BGMもオリジナルのものを揃えたので、こちらも楽しんでもらえれば幸いだ。
今すぐお披露目したいのだけれど、我輩の計算不足、Steamのストア開設が完了出来ていない。まだしばらくかかる様子。(今確認したら免許証の英訳をよこせと十日前にお知らせが届いていた。登録してるんだからメールで知らせてくれ)
これまで販売拠点としてきたDLsiteやBoothと異なり、販売開始までの手続きが煩雑であると聞き及んでいたので後回しにしていたら、そのツケが回ってきた。
写真付の証明書の提出、税関系の質問回答、申請後一月ちかくの審査期間、ゲームの事前レビューの厳しさ等、予想通り手間が多く、予想以上に待機時間が設けられている。下調べくらいしてスケジュールを立てておけば良かった。
Steam以外の販売サイトでの先行発表も考えたが、この度はSteamを中心に発表していく方針をたてていたので、時期は揃えようと思う。
Steamでの販売は簡体字、英字への翻訳がないと販売がふるわないという話だが、今回はSteamに出店することを目標とし、小さな一歩を刻んでいきたい。簡体字への翻訳には意欲があるので、そのうち行うかもしれない。
ハルカの国春秋編のシナリオ執筆も進めている。
みすずの国の完成をもって、ハルカの国より他に仕事はなくなった。仕事と言って同人活動なのだけれど、他にやることもないのだからまさに仕える事、仕事だろう。資金の方は春秋編完成までは何とかなりそうだ。作品づくりに集中できる環境と境遇に感謝している。と言って、何が起こるやら分からないので警戒もしている。
現状、最も警戒しているのは春秋編の肥大化だ。春秋編は1960年から1970年代後半までの十数年を、三つの時期に区切って語られる。端的に言うのなら三つの物語によって構成される。一つ目の物語を書き終わり、二つ目の物語を執筆途中だが、荒く見積もって一つにつき15~20万字の文量が予想される。下手すると二つ目の物語は30万字をこえるかもしれない。(三つ目の物語は10万文字程度でおさまりそうだから、バランスも悪くなりそうでこれもまた悩み)
物語が長大化すると労力が跳ね上がる。正方形と立方体の関係のように、物語の長さが倍になると、それを完成させる労力はまた倍も要求されるのだ。
物語の規模は必要十分に収めたい。しかし必要ならば作るしかない、だから日々伸張していく物語を警戒しながら既に恐れている。
今年のはじめ、たねつみ完成の慰労会に参加した際、制作中のハルカの国の話を少しして、自作品が世に伝わらないことを嘆いた。
たねつみのプロデューサーから「連作ものだから途中の作品が世に広まり辛いのは仕方ない。良い作品だから、完成すれば少しは注目を集めるのではないか」と慰められたが、その言葉は染みた。
我輩もそう思う。
ハルカの国も完成すれば、少しは日の目もみよう。しかし「少しは」なのだ。プロデューサーは「今よりもっと」という意味で使ってくれたのだろうが、我輩は己の運命を予感している故に落胆を通り越しておかしい気持ちさえした。
俺はほんとに、なんてものに人生をかけてるんだろう。俺の人生はぶち壊されたのかもしれない。
冗談でなくそう思った。
日々、伸張していく物語が恐ろしい。これは紛うことなき、我輩のリアルな感情だ。
妹の結婚
先月、沖縄旅行から帰ってくると妹が結婚していた。
旦那を連れて婚姻届の保証印だけもらいにやってきて、半時間ほど談笑して帰っていった。
親父とお袋には前もって面会していたそうだけれど、我輩や他の家族は相手を知らないどころか、妹が結婚することさえ気づいていなかった。
突然、バスケ日本代表の比江島選手そっくりの義弟が出来てしまったことに、我輩も驚きを隠せなかったもの。
とは言え、妹は三十路をこえ働き自立しているいい大人、結婚といえども当人同士のこと。
驚かされたけれど、我輩は事後報告で十分だった。
しかし古い時代を生きてきた祖母は突然結婚した孫娘に、まるで狐狸にでも化かされたように目を丸くしていた。
妹が帰った後、自分の驚嘆を誰かに伝えなければ気が済まなかったのだろう、我輩を捕まえてしみじみ零した。
「近頃の結婚はあねえなもんかね。わたしや、相手の親の顔もしらんで」
我輩も知らないし、親父やお袋も知らないらしい。
後日、妹に「相手の両親に挨拶へいったのか」と問うと、「そういうの別にいいらしい」と返ってきたからさすがに不安になった。
我輩で不安に思うのだから、祖母の困惑は一入だったろう。
「近頃の結婚は金がかからんでいいねえ」
など嫌味を漏らしつつ、いよいよ異国の異文化に拐かされたような面で煙草をのみ、その口から当惑した彼女の魂のような煙を吐いていた。
その祖母の姿から我輩が受け取った小ささ、寂しさは、困惑する祖母の感情ではなく、彼女に代表される我が家筋そのものだったと思う。
子共の頃、ホームビデオでみた両親の結婚式は、赤い絨毯が敷き詰められた会場に、白いクロスのかかったテーブルと、礼服の上に日焼けした田舎顔をのせる男女がならび、紋付き袴の新郎に、白無垢角隠しの新婦と、重苦しい形を必死に倣おうとする仰々しさにむせ返っていた。
集合写真など、内閣の組閣かと思われる堅苦しさで、両家がシンメトリーの形であわさり並んでいたもの。
それが1980年代の結婚式だった。
そこから一世代くだって、半刻の談笑に簡略化された。
それは文化歴史が途絶えたと言うのでなく、祖母の代まで手に出来ていなかったものへ両親の代で参加をこころみ、けれど結局、力を失い萎んでしまった文化模倣の姿だったろう。
困惑する祖母も、あのはりきった式典と、紙切れ一枚で終わった報告の落差に、一体、どちらが自分達の正体か分からなくなったのではないだろうか
その困惑が、吹き出されることも忘れられた紫煙として、彼女の口から立ちのぼったのだろう。
我輩はたとえ結婚式が催されても、スーツを新調するのが嫌だったので祝儀だけ多めにつつみそれで許されようとしていた。だから妹が「式はあげない。ドレスの写真だけ撮る」と言った事には心底ほっとしたものだ。
同時に、幼い頃みた、中世の教会のような仄暗い照明のもと、赤と白、黒に飾られたあの式典の歴史も、一世代かぎりの幻に過ぎなかったなとしみじみ感じた。
真似事なんてものは、真似る当人たちにその気がなくなれば廃れるもの。妹などは祖母や両親がこころみた飛躍の物語に気づいてすらいないと思う。見つけられてさえいない物語が終わったのだ。
後日、比江島似の義弟から、磯で釣ってきたという桜鯛が届けられた。
兜も見事な鯛で、妹に煮付けられたのが恐竜の化石のような強面で煮凝りに混じり盛られていた。
刺身にする柵も綺麗で、一晩寝かせたものを厚くきって食べると、噛みきれない野生を感じた。
祖母は巨大な兜煮と格闘し、箸で戦うことを諦め指でほじりながら、妹が作ったわりに味付けが出来ていることに驚き関心しながら、言っていたもの。
「ようこねえな頭を煮る鍋があったもんじゃね、あの子の家に」
結婚式もあげない新婚夫婦の台所に、巨大な鯛を煮付ける寸胴鍋があることが、祖母には不思議でたまらないようだった。