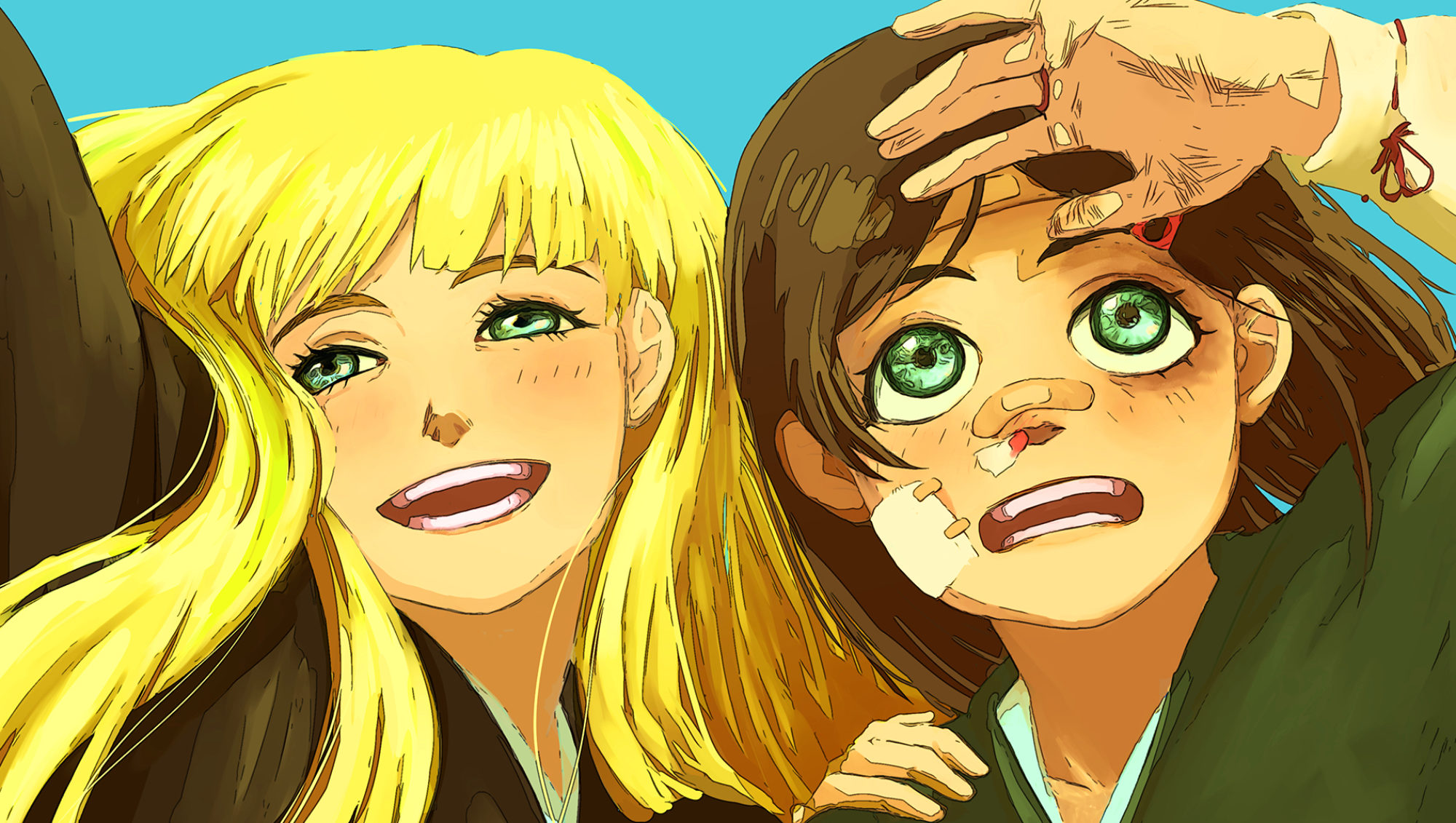以下は思考のスケッチである。
年の最後の最後まで、一体何をそんなに考えているのか、衒学的に「思考」しているくらいなら手を動かせ、作品を作れと指摘を受けそうなのでスケッチの列挙に留めて、時間と労力を必要とする「まとめ」は止める。
今の自分の考えをコミュニケーションに晒すと、どうしても伝える工夫が教える気持ちよさに転じて、自己拡大を目的とする表現になってしまう。そういう学んだことの援用によるアカデミックな衒いがもう本当に嫌なので、そういう方向に流れることを避ける意味でもスケッチの列挙に留める。
一体何をそんなに考えているのか、それが何の役に立つのか。この問いに関して説明し易い部分を並べると、以下になる。
現状、決戦編は大正13年を舞台にしている。この二年後には昭和が始まり、間もなく我が輩の祖母が生まれる。我が輩が連続性を体感出来る過去まで、ハルカの国は接近してきた。
史料を読んでいてそれを強く感じる。祖母が間もなく生まれようとしている気配を、震災手形の累積による景気不安、その後の世界的大恐慌に感じる。こういう「オレのばーさんが生まれそうな予感」、つまり「オレが始まりそうな予感」の気配を感じて、それが生々しく我が輩にも響いてくるために読み飛ばすことが出来ない。考え飛ばすことが出来ないのだ。
また、これまでは「戦後」としてふり返ることで見つめてきた時代を、過去(大正)から未来(昭和)に突っ込む方向性で追体験することの興奮も強い。
ハルカの国の創作を通して、我が輩なりに尽力した感情移入、時代の肌感覚への獲得努力の結果、「ばーさんが生まれた時代」「オレが始まる時代」が後ろにあるのではなく、前にあるという感覚を体験している。
「ばーさんが生まれそうな気配」というものを、物語の延長に予感するのは不思議な感覚で、この味わったことの無さが熱量となってしまい、読むことや考えることを手軽にやめることが出来ないのだ。
決戦編からは舞台を天狗の国に移すので、我が輩の祖母が生まれる昭和日本を描写することはない。だけれど、社会として連続しているために天狗の国にも昭和は香ってくる。この昭和の香りが天狗を天狗たらしめる。黒船という他者の登場が、諸藩に点在していた藩人たちに日本人という輪郭を与えたように、昭和の香りが日本人の存在感を強烈にして、それらではない自分たち、他者に並ぶ自己を天狗へ強烈に意識させていく。愛宕や鞍馬という有限な一区間に閉じ込められている存在を浮き彫りにしていく。
この無限ではなく有限な自己像を浮き彫りにされていく過程、つまり「人間に比べてなんか小さく感じられる自分たち」という感覚に苛まされ、天狗の国は「信じられる何か」「他者(人間)との比較の中で、納得できる自己像」を求めて紛糾する。その過程でイカズチ丸の反乱があり、その余波と言おうか帰結と言おうか、納まりきらなかった不信によって天狗の国は解体していく。その後に「信じられるもの(国)を探す」雪子ちゃんが、同じく失敗した父権制を乗り越えようと「信じられる自己像」を探すハルタに出会ってラブコメをする。
話が脱線したので戻すが、とにかく、我が輩にとって「クソデカ感情」を持たざるおえない「祖母の物語」や「雪子の国」へ連なる前作までの国シリーズがようやく、とうとう、ついに、しかし想像していたより遙かに大きな迫力をもって迫ってきている。そういう緊張感と興奮のために、読書と思考が止められないのだ。
決戦編のシナリオがなかなか上手くいかず、「この時代の愛宕って何なのだろう」と不安になり、改めて史料整理を始めたことを切っ掛けにして、上の様な状態に陥った。
これが我が輩の思考が止まらなくなっている、説明し易いところの原理である。
史料によって掻きたてられる思いが、我が輩の思考を回転させるのだ。
説明し難い部分は、以下の感覚様相になる。
本当につまらない場所から、世間や歴史や地理へと繋がっていく努力がしたい。
こういうつまらない庭で、くすんだ珪石だとか花崗岩の砕けた真砂を見つけて、それがどんな風に地球の一部かを納得していく過程が、慰めになる。
他所の物語を援用しない、「今、ここ、我が輩」から世間に繋がっていく努力は、とても慰められる。
自分の庭にあるもの、わずかなものへ向き合うことが、分かり易い見え易い「他所の才能」に目移りすることより大切だという感。高い盆栽を買ってきても、他所の松はこの庭では根をはらない。大樹にはならない。
土の研究が必要なのだ。土から力を引き出す技術と、ここなのだ、という決心が。逃避不可能感、亡命不可能感への実感が。「本当に逃げられない」と思える場所、自分の土のようなものまでの探求、ある種の絶望感の体験が。
きっと、この自分の縁にまつわる「もっと良い物があれば良かったけどな」という「つまらなさ」や、「逃れられなさ」の体感が、国シリーズの人々を肥やす。彼等は大衆だから。
我が輩と同じ、珪石と真砂の庭で何かを見つけなければならなかった人々だから。彼等はまったく普通の体験しか生涯をとおして経験しない。表層がいくら劇的であっても、それは珪石と真砂の庭で起こった、日常体験だ。日常口語体系によって表現される、素朴で卑属なものだ。その庭から憧れた他所の物語にはしたくない。他人の庭の写生を一生懸命しているのなら、それでその写実性をその庭の主に褒められたら、あんまり虚しい。
とっかえひっかえのイミテーションによる体験偽造を続ければ、いつか取り返しのつかない場所に行ってしまう。恐ろしい場所で空っぽな老いを見つけることになる。この回避には、このつまらない庭から始める他ないぞ、という強い衝動。
スケッチ1 カゾクという日本の始まり
八紘一宇、あまねく人々の頭上に屋を架しカゾクへ。
日本人というのは、なんと「家族」というものに悩まされてきた民族だろう。明治期から始まる自己像の七転八倒ぶりは凄い。そこには、日本から世界への接触という同質から異質への混乱と、藩から日本へと転じる異質から同質の混乱が混在する。
使節団として欧米列強を経験した人々の卑下から始まり、日清、日露と勝っていく過程での自信獲得。その全課程において、家族的に他者を消化していくことの能力が問題視されている。
家族的にしか他者を理解できないから日本の他民族化(帝国化)は不可能だとか、いや他者を家に呼び込めばそれは養子となり区別なく家族化するために、日本の家族の消化力は強い、だから他民族の融合も可能だとか。
それぞれベクトルは違えども、他者を論ずる論調、つまり対人関係を論ずる論調の全ての中心点は家族から出発する。(ちなみに日本の家族とは取りも直さず家長父系家族のことである)
日本の家族感に他者を消化する力があるのか、あるいは無いのか。そこが論点の重心となって、それ故の自己像、その自己像故の国際社会での振る舞い方、向かうべき未来の方向性が語られている。これは別視点をとれば日本の家族は他者の「他人感」の中に消化されてしまう可能性があるのか、という問題でもある。どんなことがあっても家族という結合は分解不可能で、それ故に家族でない他者が存在する集合に混じっても日本人は、家族として日本人で存続可能であるか否か、という論争。つまりどんな異文化と隣接しても、日本的家族は再生産され続け、そこでの日本的価値観は再生産されるのか否か、という問題。これによって海外進出、また外国人との接し方をコントロールしなければならない、というのが明治~太平洋戦争までの「日本人とはどんなか」という議論の主題だった様に我が輩には見えた。
黒船によって「日本人」となった日本列島民族が、「オレ達ってどんなだ?」と模索する時に肌感覚で感じてきた社会である家族を持ち出して、その延長線で「他民族の父にもなりえるか」と論じてきた風景。あるいは「他民族に支配されたとしても父を中心に日本人(家族)であり続けられるか」という風景。
この風景は、父親像の模索、父親へのイニシエーションに対する国家規模の苦悶として我が輩には映る。
自分たちはどれだけ立派な父親になれるだろう、養子をとっても家族をまとめていけるかな、日本人的じゃない隣人が引っ越してきても我が家に悪影響はないだろうか、という様相。
その「父親像会議」が明治~昭和初期までの戦争とその結果を受けながら変転していく模様が、日本の近代的ナショナルアイデンティティの七転八倒風景として我が輩には映った。
大前提の「家族」という類型が、他人と接する力、他人を飲み込む力、いざとなれば他人から自己を守る力としてどれだけ効力を発揮するかが問題であり、家族的類型の超克の可能性はいっさいなされていないところに、日本における家族の強さ、家族という価値観の大切さ、宗教観が見て取れる。
他者と接していく過程で旧来日本型家族じゃなくなっていっても良い、新しい日本型他者理解を模索する、という議論はされなかったし、そもそも前提として日本人は皆、日本人的家族の絆によって結ばれており、家族じゃない日本人は存在しなかった。家族じゃやない日本人は列島にはいない、ことを大前提として議論されていた。非家族的人々の存在の指摘があった場合、それは国家運用というマジョリティに作用するほどの力を持ち得ない勢力としてほとんど無視されている。
日本人にとっての家族の重さ、家族への信心、家族という呪いと祝いの力強さを改めて思い知る体験だった。
スケッチ2 神聖家族の偽造と、その偽装行為への怒り
日本の一人当たりのGDPが低下していると近頃騒がれるが、我が輩の経験に照らし合わせれば、それも仕方なかろうと思う。
最初に断っておくと、日本人の能力が低いとはまったく思っていない。むしろ日本人の製造
能力、本質的な価値生産能力は高いと感じる。「良いものを良いと言う」プロデュースが恥ずかしくて苦手なために、最終的な価値として転化する能力は欠けるが、価値を生み出す可能性のある「ほんもの」をつくる力はあると思っている。
その理由は、日本人はオタク気質が国民にひろくその資質を認められ、集中して「とことんやる」こと自体を楽しむ性質があるからだ。オタク的であること、酔狂であること、「バカじゃやないのw」と笑われるほど異常性を発揮することに、一種の祭的昂揚感を覚える。この資質のために、有能な人間も冷めておらず、「ひかれるほどガチること」を好む傾向があると我が輩は見ている。
祭り好きのエンタテイナーが多く、またそういうエンタテイナーを「愛すべき馬鹿」「能力の無駄使い」として尊び、愛し、親しみを向ける民衆が多い。「何の意味があるん?」「金に何の?」という覚めた態度をとる傾向が少ない。この「祭り好き環境」のために「心のそこからマジでやってみたい」、その結果として皆を笑わせたい、という「採算度外視」「マジ」の気質が育ち、価値のなかに「効率」や「意味」を含みたがらない。
祭りだぜ? サムいこと言ってんじゃねぇよ! という調子が、やっぱり日本人は好きだと思う。
こういう祭り好き気質から言って、「異常なもの」「酔狂なもの」を作らせたらなかなかの力とモチベーションを発揮する民族だと我が輩は日本人のことをとらえている。
つまりプロダクトまでの段階なら日本人は「オタク魂」があるので強い。が、「効率」を評価するビジネスが入るとオタクだから燃えない。好きなものを自分の吐血によって潤したい、自分の愛情に死地を見つけたい、そういう極端な基盤で育った「異常なほどのロマンティック」民族が日本人だと思っている。
そういうロマンティックな民族が何故、生産力の低下に陥っているかと言えば前記したような「効率」という「愛情」と対立する資質の欠陥、「効率」によって評価される「ビジネス」の冷たさへのモチベーションの無さが一つの原因ではある。
我が輩の私見ではあるが、プロダクト能力の高い人間ほど「採算度外視」「効率無視」「お祭り」「異常性の発揮」を好む傾向がある。こういう人間たちの情熱に点火出来ない剥き出しのビジネスモデル、冷めた資本主義価値が日本の効率、というかモチベを低下させているとも思う。
しかし最大の日本人生産能力低下の原因は、家族への不信、家族的関係性へのペシミズム、ちょろまかし合いの構造にあると感じる。
家族的にしか他者を理解できない日本人は、会社でも他者に家族的振る舞いを求める。端的に言えば、日本は職務範囲や職務義務を規定した契約をしない。そういう契約的、限定的な関係性を嫌い、「とにかくうちに入ったからには、うちが面倒をみて一人前にする」「君も会社に対して精一杯頑張ってくれ」「なんでもチャレンジする気持ちでいてくれ」と家族的全面協力関係で結ばれようとする。終身雇用は企業との結婚と称されてきたが、まさに会社は家族として社員を迎え入れ、家族としての無私の献身を期待した。職務範囲だとか、他人のような「冷たいこと」を言う相手を嫌った。
この家族的関係性は家族的に献身することへの義務と、家族的に扱ってもらえることの権利が両立する間は機能していたが、家族としての献身ばかり期待され、報酬分配の際には「ビジネスだからね」「結果が全てだから」と資本主義的な言い訳で非家族的、家族としては受け入れがたい格差や差別を会社から受けることによって崩壊が始まる。
オヤジ(会社)の裏切りによって、子が「おめぇなんか、オレの親じゃねぇ!」と背を向けることから歯車がかみ合わなくなる。
我が輩の世代ともなると終身雇用だとか、家族的社会関係なんてものに元より期待していないし、望んでもいないので、逆の裏切り、ちょろまかしの構造をもつ。
我が輩のかつての同僚、後輩が口にしたものだ。
「どれだけサボるかが給料の価値を決める」
給料は上がらないので、固定的な給料の価値をあげるために、仕事量を落とすことが肝だというのだ。外回り行くふりをして、どれだけ車内で寝たり、ゲームをしたり出来るかが大切。仕事の間にしっかり休んで、趣味のバス釣りには元気満々でいられることが大切と語っていた。
「バレたら怒られるやん」と言ったら、「怒られる前にやめるから大丈夫」とのことで、すげぇ奴だなとある意味感心した。
評価基準もない、義務もない、交渉の権利もない、あがったとしても微々たるものでしかない、そんな硬直した報酬体系と、「家族のような献身で何でもしてもらいたい」職務体系が調和するわけがなく、思いっきり反目しあって、雇用者VS被雇用者のちょろまかし合戦が展開される。「家族」という関係性に隠れた、面従腹背の戦いが繰り広げられているのだ。
生産能力の低下、というトピックで語っているので従業員の目線で「ちょろまかし構造」を語る。
生産力をあげないことが給料の価値をあげる。首にならないギリギリをせめ、職務責任のない仕事をダラダラと最大時間をつかって最低のクオリティで保ちつつ、元気いっぱいに趣味や副職にエネルギーを費やすことが攻略方法となっているわけだ。
ここまで露骨でなくとも「頑張った分だけ損」の構造なのだから、生産能力があがる由もない。
「頑張ったらこたえる。いざとなれば守る。我々は一蓮托生。だから無私の気持ちで頑張ってくれ」という会社からの家族的眼差しへのペシミズム、信頼感のなさが、家族の権利(職務責任のない固定給)だけちょろまかしてやろうという気質を育てるのだ。
我が輩は以前の仕事にも情熱をもってあたっていたが、上司から「正社員は家族」「お前のことも息子と思っている」と言われた時は「うぜえ」「きめぇ」と強烈な嫌悪感を抱いた。
これはやはり日本人が「家族」という関係を、本当に純粋な心からの信頼から成り立つと、一種神聖な理想としてとらえているために、軽々しく、しかも「ちょろまかし」という己の願望を満たすために口にする「嘘の父親」へ、激烈な嫌悪感を覚えるのだと思う。
少なくとも我が輩は、単純に家族的関係性が嫌いなのではなく、家族への複雑で巨大な感情のために、自分と軽々しくそういう関係を結ぼうとする者、そういう関係的につながろうとする他人を嫌悪するのだ。
日本人の生産力の低下。
これは「嘘つきな父親」に対する子供たちの嫌悪感、報復行為としての背信に起因していると思う。
もはや企業や会社というものを「父親」としては見ず、「父親ぶる嘘つき」「嘘つきが父親として接してくる」というキモさを若者は抱えていると思う。
このキモい連中とどう接するか、どう距離をとるか、どう「ちょろまかされないようにするか」という関係性の模索にエネルギーが使用され、とてもオタクらしい「ガチ」を発揮する環境ではないのだと思う。
参加費をとる飲み会での上司の説教とか、女性社員へのお酌への期待だとか、「金もねぇくせに父親ぶる嘘つき」共への嫌悪感で、日本の純粋なオタク的若者達は疲れているのだと、我が輩は観察している。
本当は祭りが好きで、ガチってみたい、人生で本気を出してみたい若者が沢山いるのじゃないか。しかし彼等のエネルギーに発火する組織、チーム、会社構造を作れていないのだと思う。
家族は日本人にとってあまりに神聖であり、理想だ。
これの偽装、未遂は純粋な若者であればこそ反感を覚えるので、今すぐやめるべきだ。
会社は家族じゃない。
職務範囲、職務義務を明確にして、掛け替えのない家族、ではなく、掛け替えのある契約的他者として接した方が、「嘘つきと付き合うキモさ」を取り除ける分、マシな結果にはなると思う。
ただしこの場合でも日本人が本来的にもつオタク気質の爆発、採算度外視のガチは発揮されない。この能力の発揮には、「効率」というパラメーターを含有するビジネスでは難しいのだ。祭りのような、酔狂な場でこそこれは発揮される。
だから日本人の〝仕事〟を減らし、酔狂に費やすエネルギーを増やしたほうが、良い物が日本に溢れると思う。
日本の仕事が週四日制とかになれば、本当に沢山の価値が生まれると思う。オタクは物作りが好きだから。作ったもので人を驚かすのが好きだから。
オタクは休みの日に休んだりしない。バカンスには行かない。何かを作っている。何かを学んでいる。日本の労働者、オタク達は「ちょろまかしの構造」から抜けだし、「祭り構造」へ移ることで、日本の生産力は上がると我が輩は考えている。
だから未来には沢山の祭りがあって欲しい。沢山の祭りが始まることを願っている。メタバースとかで。
そうして「今日は祭りですよ? 仕事なんかしちゃいられませんよ!」という町民、村民気質が発揮できる大らかで、ノリのいい、異常な炎のような日本社会が復活してくれないかと願ってやまない。
一生を「父親ぶる嘘つき」とのちょろまかし合いで終えるのは、あまりに虚しい。
スケッチ3 カゾクとチチを乗り越えて
家族や父親像への神聖は、日本社会にとって構造的なものだろう。現代、それが崩壊している過程にはあると感じるが、崩壊を論じられるほどにそれらは過去において確立されていたのだ。
我が輩もこの価値観に深く浸っており、上記したように「父性」を粧うちょろまかしには強烈な嫌悪を覚える。これは宗教的憎悪感といって良い。
しかし、我が輩の場合、この家族や父性への感情が純粋ではありえず、かなり捻れた構造を持つ。
第一に父性、父なることがあまりにも神聖であるため、それを達成している現人神をこの世に誰一人として見つけることが出来ず、「理想の父」の達成への不信が強固であるということ。
これは「父」を粧う相手への嫌悪の大きさでも測れる。我が輩は権威主義でありながら、その権威の絶対性に強烈な猜疑心を持っているため、「本当の父」と他人を認めることがまずもってない。
我が輩はオヤジ(ものほんの)に対して愛情はある。尊敬もしている。権威の象徴として敬いもする。しかし純粋宗教概念まで高められた「本当の父」を、彼に二重写しすることはない。
端的に言って、我が輩は権威に対する理想があまりにも高すぎるために、誰一人、この世に存在するどんな権威に対しても、尊敬の念を持つことが出来ない。
この姿勢のために権威主義を非難するリベラリストと思われることもあるが、本質はバリバリの伝統主義者、権威主義者、それも妥協を許さない原理主義者と言っても良いほどの過激さをもつ。
ただこの〝純粋なる父〟を「稚拙」と諦めているために、そんなものになれない人間や、社会集団を認めることが出来ている。「そんなご立派な奴、いねぇわな」「皆仲良くクソみたいなもんだよな」という明るいペシミズムというか、理想に対する脱力主義でバランスをとっている。
もちろん、この脱力感は、父になれない我が輩を肯定するために成立している。
もし我が輩がバリバリのエリートで、高収入で、結婚していて、妻子を養いながら両親の面倒を見る理想像を地でいっていれば、我が輩の本心にある「父親原理主義者」の顔がのぞいていたかもしれない。完璧な「父」ではないかもしれないが、その可能性があることに安居し、今よりずっと傲慢で父親になれない他者、父性を認めない他者を廃絶していたと思う。
我が輩は理想を達成できないために、理想の否定を含んだ精神構造、理想という絶対性に対するプラグマティズム的相対性を獲得しているのだ。
理想が高すぎるために、理想が自己を否定する。そのために理想を茶化す、鼻で笑うという行為が態度となる。これがまず一つの捻れだ。
我が輩の理想の父とは、家族のために責任をとって詰め腹を切った、カゾクへの献身を果たした霊である。家族(特に子供たち)のために激痛を乗り越えて、死ぬことを受け入れていった人。それが我が輩の理想の父だ。つまり生きて娑婆の空気をすい、風呂上がりにビールを飲むような、昭和的牧歌風景に溶け込んでいるのは我が輩の「父」ではない。それは愛すべきオヤジだ。
父親原理主義者である我が輩は、父たるものには究極の献身、カゾクのために死ぬことを求める。その時がきたら家族を命懸けで守る、では駄目。既に死んでいなければならない。それもロマンシズムな英雄死ではなく、本当に本当に生きたいけれど「しょうがないか……」とどこまでも寂しく虚しく激痛を受け入れて死ななければならない。(こっわ……)
幼少期から死に対する強烈な恐怖があった我が輩は、この死という究極を他者のために受け入れるというウルトラ行為こそ「優しさ」だと信じ込み、この優しさを発揮する可能性を探していた。
その中で、発現の可能性を見出したのが家族のために死ぬ父親であり、家族のため死ぬことは父親であることへのイニシエーションに転化していった。
この物語の強化は極まり、家族のために虚しく死んでいない父親はまだ父親の資格がない、というウルトラ理論を完成させたようなのだ、どうも。
死への強烈な恐怖と、父への強烈な憧れが上記の物語によって昇華されている模様が見て取れる。
こうして理想の父によって死への恐怖を克服した我が輩であるが、それがあまりにウルトラ過ぎて、そのイニシエーションを自分が通過する度胸がどうしても持てず、自己否定に陥った。
自己否定の解決として、世の中の父親っぽいもの全て「ウルトラを通過していない偽物」と否定し、自己を「父にはなれないけれど普通の人」という解釈で承認した、という寸法だ。
父性への捻れ構造として、第二の捻れは、上記した「ウルトラな父」へのイニシエーションを現代社会で見出せないために、父性を獲得する構造への不信がある、ということ。
初代ウルトラマンは人間たち(子供)を守るため、ゼットンに挑み死んだ。こういう父への儀式が、現代にはない。父親が傷つき死ぬ機会がない。サラリーマンとして擦り切れていくオヤジたちは多いが、それは現代社会の中で雄の意義を失っていく矮小化の哀愁であり、父へのイニシエーションとは我が輩には映らなかった。
社会というものが巨大になり過ぎ、一人の雄に対して決意や献身を要求するような構造がもうない。保険や終身雇用、年金構造にとりこまれて、瞬間的ウルトラ行為である激痛をともなう死はなくなり、緩慢な無痛の人生への耐久がオヤジに要求されるものとなった。
ストレス社会なんてのは、我が輩が探すウルトラな瞬間的激痛イニシエーションの対極にあると言って良い。
この社会風景に、「もはや父になる機会はどこにもないのではないか」という不信がある。我が輩としては「あー良かった。これで皆、我が輩と同じ父親未満」なわけだが、この社会風景が「本当の父親なんているわけがない」という不信を育ててはいる。現代社会において「激痛をともなうウルトラな死」は探さなければならない行為であり、見つけてまでその行為に殉ずることは我が輩にとってロマンティックが過ぎる。
「父になる」とは世界から強制を迫られた時、その恐怖に戦慄しながらも背後をふり返るとカゾクがいるために、「しかたないか……」と諦める命と、受け入れる苦痛でなければならない。
死ぬ必要もない場所で腹切って死ぬことは、我が輩にとっては「他者のロマンティズム」であり、ご自由にどうぞの範囲であり、尊敬の対象ではない。
そうして、我が輩にとって現代日本社会で父になれる瞬間、ウルトラな死は存在しない。たとえそれを自称する行為があったとしても、「他にやりようあったやろ」とか「もっと頭使えよ」とか思ってしまうだろう。
父親になれる資質があったとしても、父親になれる機会がない社会、「父になることはない」社会への不信感(安堵感)が、二つ目の捻れとして我が輩の中には存在する。そのため父親ぶる存在、父の延長である権威に、「そんなものは有り得ない」という否定と嘲笑、ペシミズムを持っている。
この「父になれない社会」、父親可能性への構造的不信は、父親になれない我が輩を安堵させるものではあるが、根本的には父親原理主義者である我が輩に「不信」という緊張感を強いる。何を見ても、誰を見ても「どうせ父にはなれない」「父はいない」という否定しか出来ない。誰かが父親的なものを信じていても「偽物に騙されやがって」と信心自体を嫌悪してしまう。
この「全方位への不信感」はやはり疲れる。
その救済行為として、ウルトラ行為によって「社会不信」を跳躍しようとする癖が我が輩にはある。
これが自覚的である。自覚的であるからすっごい嫌だ。
以前のブログでも書いたが「キリンの国」の圭介のある部分に強烈な忌避感を覚える。あるいはハルタや、五木に。
社会構造への不安という「大きくて複雑で困難な問題」をすっ飛ばして、弟であるキリンや、妹(娘)であるホオズキの救出、死んだ母娘への献身を示すことが可能なウルトラ行為を設定し、そこへ挑むことで「理想」を達成しようとする下心があるようなのだ。
無意識に書くもの全てに、そうした「社会不信の跳躍」が見てとれ、「お前それでええんか」と毎回思うが、しかしながらウルトラ行為を目の前にした時、我が輩の「男の子」たちはそこへ泣きながら殉じる。と言うより、作者の我が輩が逃げることを許さず、突き落とす。
逃げるような奴は我が輩の「男の子」じゃない! と言わんばかりに。(己はそれが出来ないために世の中の悉くを否定したのに!)
圭介が嫌い、ハルタが嫌い五木が嫌い、と言うより、そういうウルトラ行為という我が輩のマスターベーションへ自分の愛した「やさしい人」を突き落とし、自己の世界観の肯定を繰り返すことに嫌悪と、それでもやめられない病的な心理を自分に嗅ぎ取るために、「こいつヤバ……」とひくのである。分かっていて、ひいていて、やめられない。マジひくわ……と自分でも絶望感がある。
我が輩の初期社会である家族は、男2に対し女4で形成されていた。かつ、我が輩以外の男であるオヤジは、ほとんど仕事で家にいなかったし、海外出張で長期離脱することもあった。
家では父性を神聖として、その権威によって家を治める女たちが我が輩を四方八方から教育している。モノホンがいないのだから、父性の神聖は高まるばかり。
また我が輩は長男でもあるから、父親になることも期待された。
その過程で、「いつか父親になって家族のために究極の献身、死ななければならない」「強烈な苦痛を受け入れなければならない」と思い込み、怖がりの我が輩は恐怖に悶えながら、父権というバケモノに恐怖で給餌し、ふくふくと肥えさせていった。そうして、自分の客観性ではどうしようもないウルトラモンスター「カゾクとチチ」という価値観を確立したのだ。(と今のところ分析している)
またこの価値観が、二十世紀末の片田舎では是とされたわけだ。漫画やアニメのメディアもこういう価値観を肯定するものが多かった。余談だが、近頃鬼滅の刃を見て凄く癒やされたのは、あの物語のなかにウルトラな行為があり、兄が妹のために血を流す機会が沢山あったためだろうと分析している。鬼滅の刃が父権的というのではなく、「ウルトラな父」という理想を持つ我が輩にはそういう風にしか見れなかったという話。
我が輩の「ウルトラな父」は、我が輩自身の「オレにはとても無理だ」という成人後の挫折切っ掛けでしか否定が始まらなかった。その挫折の切っ掛けも、とにかく死ぬのが恐い、死ぬときの痛みが恐いという、慢性的恐怖からくるある日の諦めで、劇的な経験でもなかった。
つまりかなり長い間「ウルトラな父」を否定することも出来ず抱えており、否定過程も瞬間的なものでなく、ずるずると諦めていったという「すっきりしない感」がある。故に今でも理性的、客観的な視座だけでは克服しきれないものがある。
社会学と出会うまでは、社会的権威に対する不信感と、父親的なものが好きな権威主義的傾向の矛盾を解決出来ずに苦しんだ。
社会学と出会い、我が輩なりの分析を行うことで、自分の中の捻れ構造を発見し、対処のしようも出てきた。
その対処の一つが、上記したような物語による「ウルトラ行為の設定」と、我が輩のもう一つの理想である「やさしい人」による行為の遂行、つまり我が輩の中にある価値観の肯定だ。
もちろん、物語はその極所場面においても、これだけを意図しているわけではない。複合的な意味が「他者への献身」「死の覚悟」というものにはある。前述したように、我が輩は「死」や「痛み」を強烈に恐れているので、その「受け入れ」には色んな意味があるのだ。その色んな意味の中に、毎度、少なくない割合として、「ウルトラな父」へのイニシエーション的意味合い、現実では叶えられない我が輩の理想の達成がある、と思うのである。
「ウルトラな父へのイニシエーション」
我が輩はこの捻れ構造の解消的オナニズムを乗り越えたい。カゾクとチチという価値観を克服したいと常々思っている。
そのヒントとなっているのが、我が輩のもう一つの理想、家族という輪郭を超えた存在、他人。家族という利益構造の外にいる人。
この他人の中の「やさしさ」。
ほがらかな、一切劇的でない、日常の中でのささやかな思いやり。
目があって「どうも今日は暑いですね」「ほんとね」と声をかけて、にこっと笑うような風景。
こういうウルトラと対極にある、ありふれたもの。
一つ一つはまったく難しくない、思いやりの積み重ね。ただし、それは家族という利益還元の外にある他者へ向けられたもの。
この日常的でありふれた優しさ、日常口語体系によって表現される他人への思いやり――「やさしい人」を、我が輩は「カゾクとチチ」を克服するために探求している。創作のなかに見つけようとしている。
このカゾク的起源のない他者からなる、弱い絆。弱い共同体。カゾクのような絶対不変なものではなく、一緒にいたり居なかったり、役割も不変ではなく入れ替わりや変化があり、別れゆくこともある「今、ここ」を共有しているという環境依存型共同体。
これを信じられる「瞬間」を獲得することで、我が輩は「カゾクとチチ」という実現不可能なウルトラを超克し、不信構造から脱出出来るのではないか。
そう考えている。
それを託しているのが、ハルカにとってのユキカゼだ。
このためにも、ハルカの国では、かつて一度も我が輩が許していない「ウルトラ行為」の失敗――父の献身の失敗が登場する。予定。それに耐えられるかどうかは謎だが、それをしないことにはハルカの国を描く意味がないと思う。
父を母に読み替えて、必ずしも父性的ではないハルカによる行為にはなるが(しかしながら神という究極の父性属性をも持つ)、そういう緩衝処置を施さないことには達成を想像だに出来ないところに、既に我が輩の弱腰を見る。
普通の人にとっては何でもないことだろうが、我が輩にとって、ある意味理想郷である物語のなかに、ウルトラ行為の失敗、背任を持ち込むのは「美しさ」の穢れにつながる、滅茶苦茶嫌なことなのだ。それでも我が輩は硬直する「美しさ」を嫌う。美しく保たなければ「美しさ」ではないナイーブなものを、我が輩は「美しさ」と認められない。美しさはあくまで外部に発見するものであり、手元でこねて作り硝子ケースで守るものではない、という「天然物思考」のために、他者から見れば「なにを大袈裟な」と思えることを、色々大掛かりな仕掛けを用いて挑戦しているのだ。(と、思う。無意識で思いつく物語を分析するに)
決戦編の執筆が難しいのは、ユキカゼという理想の描写が終わり、いよいよハルカという本質、我が輩の嫌悪的部分とその克服に取りかかったからかもしれない。その挑戦が以前までのシナリオより難しいのかもしれない。
お気づきの方もいると思うが、我が輩は賢狼ハルカを一ミリも尊敬していない。
我が輩は彼女を、現実社会に対する不信感と同じく、「失敗する人」と捉えている。
そう考えると、ハルカが我が輩なのだろうか?
それだとちょっと良く書きすぎている。
けれどユキカゼが我が輩の理想である「やさしい人」であることは確かだろう。物語の最後に、我が輩は読者に、我が輩が憧れたこの「やさしい人」を献げたい。と言うより、たぶん、自分が見つけたいのだと思う。カゾクを越えた、自己のエコーチェンバーを越えた、摩擦の手触りがある、日常口語体で同じ営みを語ってくれる他人を。
やさしい人に出会うため、家族と父を乗り越えたい。
でもきっと、我が輩は一生〝ここ〟に居るのだと思う。克服する「瞬間」、祭りのような、歌のようなダンスのような一瞬がたまに訪れるだけで。
と言うのも、不変的「カゾク」という永遠性を信じていないから。「やさしい人」があるという瞬間への信心しか、獲得を試みる気持ちさえ起きないのだ。
我が輩にとっての「祭」思想は、「カゾクというチチ」という不変的権威主義へのカウンターにもなっている。
死や崩壊、役割の代替を含む、流転する動的秩序「祭」と、その中で一時の共同体として信じられるかもしれない他人の誕生。それらへの憧れと探求。
不信という緊張状態の克服行為。
これが我が輩の、一部の精神構造だと思う。
年末にはゴッホが福岡にくるので行ってくる。
その他は創作を続ける。コミケに向かわれる人は、お身体に気を配られて。
今年は何も発表出来なかったことに、本当に悔いが残る。今年が終わっていくことに焦る。
来年はきっと形にして、皆様に届ける。ここに誓って、締めにしたい。
今年もお世話になりました。
来年も、どうぞ、よろしくお願いします。
良いお年を。