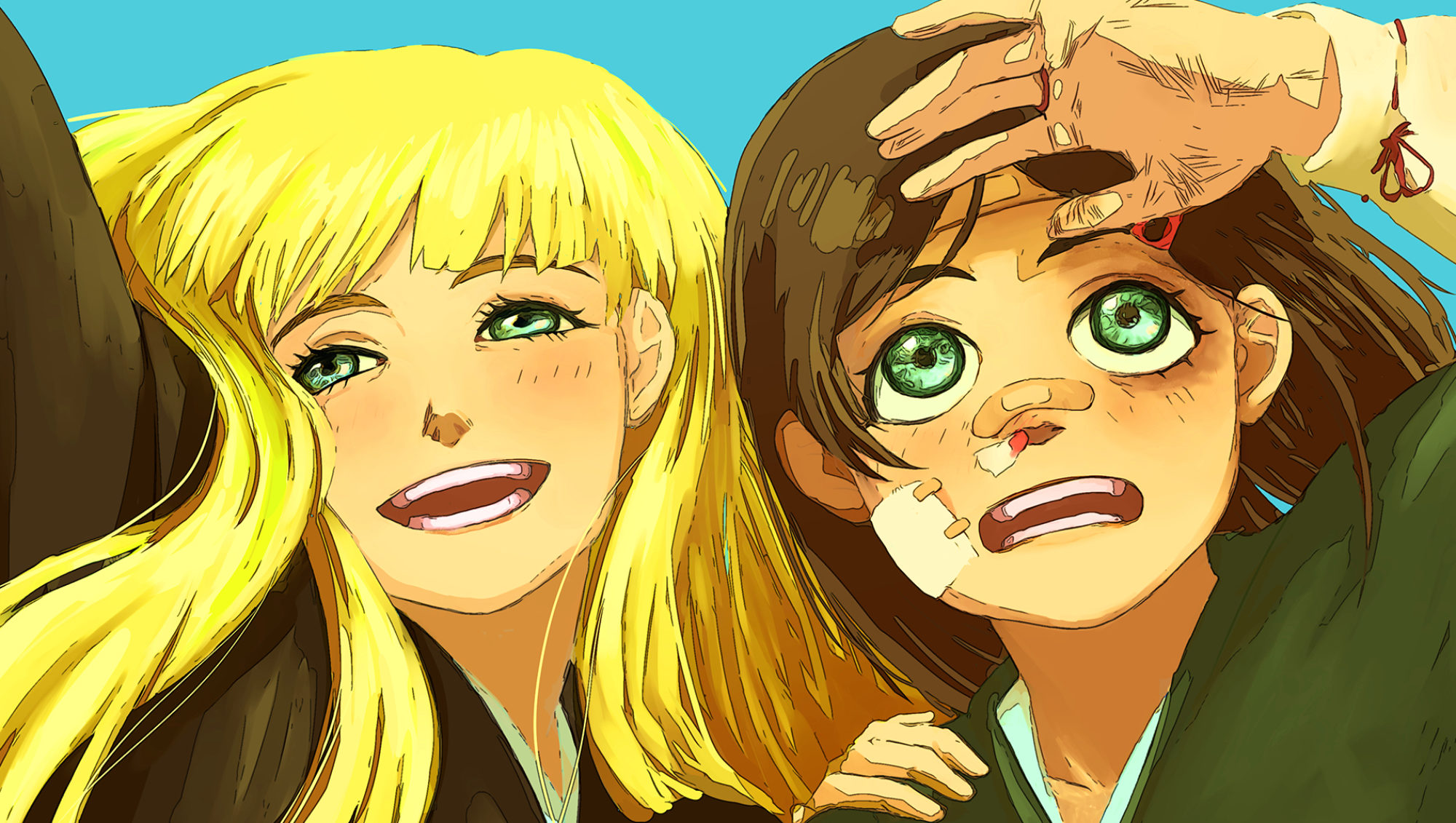旅行へ
先日、親父と旅行に行ってきた。
親父はこの十一月で退職するのだが、その前にまる二年分残っていた有給休暇の消化ということで、十月からは仕事に出ていない。
まる二年どころか四十年働いてほとんど有給休暇を取ったことのなかった、典型的な日本企業戦士である。
趣味もゴルフ、釣り、パチンコと、世の通例に漏れない。
およそ性格もそのようで、お調子者のところもありつつ、理屈屋の頑固者、加えて気分屋で怒ると周りに気をつかわせるあたりは、オヤジ目オヤジ科、学名Nipponiaoyajiといった具合だ。
旅行の目的は種子島からあがるH2型ロケットの打ち上げ。
「下町ロケット」のドラマを見てから興味をもったという、これまたニッポニアオヤジらしい動機である。
ロケット打ち上げというメインイベントをおさえつつ、鹿児島観光を行なった行程は以下のようなもの。
鹿児島・知覧武家屋敷・知覧特攻平和館
↓
種子島・ロケット打ち上げ・島内観光
↓
屋久島・島内観光
以上を三泊四日だが、実質まる五日で巡った。というのも交通手段が車だったのだ。
「ロケット見にいくか?」と誘われた際、もっとも危惧したのはこの交通手段。
鹿児島まで片道5時間。
親父と二人、何を話すのか。気詰まりしそうで不安だった。
それでも親父の話に乗ったのは、退職祝いにもなるとも思ったし、単に足を運んだことのない鹿児島に興味があったということもある。
だが出発の前日まで、我輩は「親父と二人きりの車内かぁ」と憂鬱だった。
というのも、我輩は親父のことがかつては苦手であり、嫌いだったからだ。
嫌いな親父
子供の頃、親父のことが嫌いだった。と言うより、合わなかったというのが近い。
思いだすのは小学三年の頃に書かされた「将来の夢」という作文で、「コンビニ店員になりたい」としたところをやたらに怒られたこと。
当時、我輩にアルバイト、正社員などという概念はなく、身近な仕事として存在し、お菓子がいっぱいあるし最高じゃん、という程度の考えだっただろう。あと周りの連中が「サッカー選手」「消防士」「社長」「歌手」と判で押したようなことを書いているのが気に入らなかったのだと思う。
当時から、我輩は皆がやっていることに価値を見いだせないアイデンティテイのこじらせ方をしていた。
職業に貴賤なし、なんていうリベラル思考はニッポニアオヤジにはなく、男子たるもの大志を抱けとばかりに大きな夢を描かせようとしてきたのがひたすら鬱陶しかった。
この「男子たるもの」という思考は親父の金科玉条であり、脆弱な夢をもつ息子を薫陶したいと思ってなのか、キャンプに、釣りに、科学博覧会、スポーツ観戦と、勝手に企画し、家に引きこもって牧場物語をしていたい我輩を連れ出していた。
それでいて我輩がつまらなそうにしていると機嫌が悪くなり、帰りの車では家族全員がハラハラしてすっかり疲れ果ててしまったものだ。
妹と我輩が同じ事を言っても、「男がつまらんこと言うな!」と我輩だけ張り飛ばされることもしばしば。
当時から平等にだけには敏感だった我輩は、このような振る舞いを大変理不尽に思い、「オヤジは妹が好きなんだ。俺は嫌われてるんだ」と拗ねていた。
親父が海外赴任する際、妹は大好きな父親がいなくなることで体調を崩したが、我輩は嘘泣きしながらも身中パーリーナイ。これで煩く言われずゲームができるし、成績が悪くても怒られない。
親父のいない世界が、どれだけ輝いてみえたことか。
そんなこんなで、二十歳を過ぎるあたりまで、我輩は親父が嫌いであり、親父の車の輪音がするだけで気分を害される思いだった。
しかし、二十歳を過ぎてから、それが変わり始める。
発芽
中学生まで我輩は完全なインドアオタクであり、漫画やアニメ大好き、休みの日は一日中ゲームをしていたかった。
ToHeartに出会い、グッズを買いあさり、部屋にはポスターもはりだして、それを友達に見せびらかせたりと、オタク的であることに自己のアイデンティティを確立していた。
それが高校生にあがる頃、熱が冷めて集めていたグッズやビデオセット(当時はビデオだったんですよ、お若いの)を友達に譲り始める。アニメや漫画は相変わらず好きだったけれど、グッズの収集癖は中学時代で満たされ、以後、再発したことはない。もともと物を大事にしないタイプで、執着心も薄く、何より面倒が嫌いだったから、綺麗に飾り立てておくことが億劫になったのだ。
友人宅で飾られているバスフィッシングのルアーセットや、箱の上に新品の如く並んでいるバッシュセットなどを「おお、すげー」と思うこともあったが、「俺はいらねーな」と羨ましくは思わなかった。むしろ物を持たないことを良しとして、彼らがルアーやバッシュ、雑誌のバックナンバー3年分によってアイデンティテイを誇るのと同じように、我輩は「いつでも全部捨てられる」という心持ちを誇りにした。この信条は引っ越しをやたらと繰り返すようになる二十歳以後は大変助けになって、今も特に惜しい物はない。頭の中身とクラウド管理しているデータだけあれば十分である。
上記したように二十歳を過ぎると家を出ることが多くなる。
この頃には漫画やアニメもほとんど見なくなり、かわりにキャンプや旅行といったアウトドアにはまり始める。
大阪、沖縄、海外、北アルプス、北海道にはそれぞれ住み込みで働き、稼いだ金は旅行で消し飛ばした。
二十歳からは小説も書き始め、エンターテイメントは消費するより、創作するほうが断然面白いと感じるようになる。
なんでそんなにうろちょろするのか、知らない場所に行くのは恐くないのか、とよく聞かれたが、恐いのが逆に良く、知らない場所に自分の身を空き缶を投げるような安易さで捨ててみることに快感を覚えていたのだ。俺は自分をどこにでも放り込める、そこでやっていく力がある。それを証明し続けることが生甲斐だったように思う。
男なら裸一貫、女々しいこと言わずに世を渡ってみろ。
そんな気概が当時の我輩にはあった。今となっては勘違いも甚だしく、お前一人の力ちゃうやろ、と思うのだが、当時は己の勇敢さに悦に入る若輩者だったのだ。
そんな時、ふと思い起こすのが幼少の頃たまらなく嫌だったニッポニアオヤジの信条、「男らしく」。あの頃は拒み、身中で舌をだし、後ろ足で砂をかけていたものが、どういうわけか自分の中で芽をだし根をはり、そこに依っているのだから不思議だった。
親父が俺のなかにいる? なんだか癪に障るが、否定しようのない深いところでそれを感じるのだった。
それを如実に感じたのが、国シリーズ。とりわけキリンの国を作った時。
第一案を友人に完ボツにされ、空きれい状態になってしまった我輩は、どうせなら本当に好きなこと、愛しているものを見つめなおそうと一度立ち止まった。エンターテイメント技術や流行云々、当時研究していた効率的な承認欲求の満たし方などは一度手放して、興奮ではなく、静かに心から愛しているもの、本当に美しいと思えるものは何か、考えてみた。
その答えが、冒険だったのだ。
我輩は知らない場所に旅立つ時の、あの不安と、興奮、どきどきする気持ちや、新し風景との出会いを何より愛していた。
夏の森の朝や、暁から桃色に目覚めていく空、夕景のなか銀色に光る海、季節それぞれがもつ風の匂いを、堪らなく美しいと感じていることを思いだした。
同時に、それらは、憧憬であることも思いだした。懐かしい、記憶のなかの風景であることを思いだした。
それらが嫌々ながら連れて行かれたキャンプ場の蝉時雨であり、エサのつけ方が下手だと怒られた潮の匂いであり、ドライブスルーで食べた自動販売機のハンバーガーやたこ焼きやコーラの味であることを思いだしたのだ。
本当に人間は不思議なものだと感じたものだ。
当時は嫌でしかたなかったことが、どういうわけか愛おしくてたまらないものに変わっているのだから。何よりも強烈な思い出として蘇ってくるのだから。
キリンの国は、我輩がもう一度出会いたいと願う風景を描いた。それらは、ニッポニアオヤジがいた風景。当時はゲームボーイでポケットモンスターをしていたかった風景だったのだ。
老いの静寂
そんなわけで嫌いだった親父のことを、二十歳過ぎてからは嫌いではなくなり、むしろ言葉を交わさなくともどこかわかって居られるような親近感を覚えた。もちろん、全肯定などしない。相変わらず不機嫌になって人に気をつかわせるところもあるし、身内の恥をさらすようで嫌なのだが、女性問題で一騒動したこともあった。おかげで母親は五年以上家に帰ってこない。外ではたまに会って飯を食っているらしいが、とりあえず我輩の家には母親がいなくなって、代わりにヨークシャテリアがやってきた。
ただ、この度の帰省では親父の存在を有り難く思うことが多い。
まったく仕事をしていないわけではないが、自宅で出来る小遣い稼ぎ程度しかしていない。あとはゲーム制作、ゲーム制作、ゲーム制作の日々。
さすがに半年も過ぎると家族の目が痛い。祖母と叔母がそれとなく就活をすすめてくる。折り込みチラシの求人広告を「これどう?」と勧められるのは三回過ぎるとかなり嫌気がさす。「KAZUKIも早くまともになって、お嫁さんもらわないと」「親戚の〇〇は今〇〇の工場で働いてるんだって。KAZUKIも応募してみたら?」「このままじゃ結婚できないでしょ? いくら自己責任でやってるからって、いつまでも好きなことしていられないよ。そういう世界は才能がある人だけが生きていけるとこなんだから」
この類いを日々聞かされていると、さすがの鉄面皮の我輩も心に毒がたまってくる。「そやなぁ、早くまともにならんとなぁ」と適当に受け流しているのだが、どうしようもなくザルの目にこびり付く何かがあるのだ。
もちろん、「やっぱりまともになろうかな」とは我輩はならない。「うるさなってきたから、また家でるか」という発想にしか行き着かないのだ。
そんな我輩が今回実家に居続けられたのは、のどごし生とメビウスのおかげだ。
親父が酒飲みなので、我が家には常にのどごし生と焼酎が切らされることなく常備されている。それを親父が夕食の際、自分と我輩のぶんを二本、冷蔵庫から取り出して「ん」と寄こしてくる。晩酌の相手が欲しいからだと思っていたが、「はよ働け」「はよまともになれ」「はよ結婚しろ」と言われた後にグダグダ言わずに寄こされるのどごし生は有り難かった。
また煙草を切らした時に、車がないので(愛車のワゴンRは帰ってきたら廃車にされていた)親父にたよると、「一つもってけ」とメビウスを一箱くれる。金を払おうとすると「いらんそんな小銭」と言われるから、親父が溺愛しているヨークシャテリアの積み立て貯金箱に五百円寄付しているが、これも有り難い。
酒と煙草が親父からもらえる。大人として認めてもらえているようで、ちょっと擦れてきた心には嬉しかった。
親父は相変わらず「人と同じことしててもつまらなん。サラリーマンなんかになっても面白うない」(自分はサラリーマンなのだが)と思っているようで、我輩が志すことをビールと煙草で応援してくれているようでもある。少なくとも否定はしてこない。
父という役目の終わり
さて前置きが長くなって、本題のほうが駆け足になりそうだが、旅行について。
結論から言って、旅行は楽しめた。心配していた車内も苦にならなかった。お喋りに花が咲いたわけでもないが、一時間以上黙っていることが辛くなかった。喋りたいことが出来れば喧々諤々の徒になることもあったが(近づく選挙とこれからの日本についてとか)、話題がなくなればただ黙っていて、それが許される車内だったように思う。
二十年ぶりくらいに親父と旅行したわけだが、以前は親父の特等席だった運転席に我輩が座ることもあり、サービスエリアでは喫煙所で顔をあわせることもあった。運転するのも、金を払うのも、酒を飲むのも煙草を吸うのも親父だけだったが、今はそうではなくなっていた。
印象深かったことを二つ。
知覧特攻平和館にて、特攻隊の手紙が展示されていた。
その夜、酒を二人とったりやったりやったりとったりしながら、ぽつと親父が漏らす。
「あんな手紙読めんよ。わちはこうして息子と旅行もして酒も飲めるけど、あの人らはそれが出来んかったんじゃけ。生まれてくる子供に長生きしてくれ書いてあった手紙なんて、どねーな気持ちで書いたんじゃろうか思うと、読めんて」
親父に息子と言われたのが、なんだが妙な気持ちがしたものだ。
特攻隊のことについて。あるいは戦争のことについて。我輩はあまり他人と語りたくない。悲しいとか、可哀想とか、そういう一つの記号で言えない感情があるから黙っておきたい。親父がどう思ったのかは知らないが、我輩は親父がこちらの「せやな」の一言と、その後の沈黙を尊重してくれたのように思えた。
最後、屋久島の土産屋でのこと。
屋久杉が妙に気に入ったようで、そこらへんの道に落ちてそうな木片、切り株に云千円、あるいは万の値段がついているのを「これもいい、あれもいい」と親父が物色している。我輩は外のベンチでアイスを食べ、煙草を吸っていたのだが、そこにいそいそとやって来た親父が「もう少しおってもええ?」と聞いてくるのがおかしかった。
同時に、親父の顔を見ると誰か知らない人のように見えた。
我輩が親父と思い、常にあてはめていた像は二十年前以上の親父であった。しかしその像と今目の前にある人はどこか違った。大きくて見上げるようだった親父が、今では我輩より目線が低い。
その時、気づいたのだ。
これは父だったものなのだと。
この眉に白いものが交じりはじめた、どこか見覚えある人間のようなものが、我輩の父親役をつとめたのだと。
ニッポニアオヤジとは生き物ではなく、ある演劇の一つの役目であった。
それを必要とした我輩のために、この人間はその役をつとめ、今、それが終わったのだと。
我輩もまた息子という役を担い、それを演じてもいた。
けれどもう役がなくとも二人は存在し得るし、同時に、息子や父親がいなくとも生きていける。
我輩はこの老いた男に父親だった影を見つめながら生きていくのだろうし、彼もまた三十路を過ぎて鬚を生やし自分と同じように酒や煙草をのむ男を息子だったものと思い過ごしていく。
旅の終わり、親父が「もうわちは色々行けんが、かーくん(我輩のこと)はこれから何処にでも行けるな」と言っていた。「せやな」と相変わらずな返事をしながら、我輩は胸を締めつけられるような寂しさを禁じ得なかった。
福岡の小倉を過ぎ、山口の下関に入ったとき、我輩は何かを関門海峡のむこうに置いてきたような気がした。
それはあの日々と同じように、いつか我輩にとって憧憬となり、もう一度出会いたいと願う風景として蘇るような気もした。
余談になるが、笑えたことを一つ。
屋久島に泊まった朝のこと。親父が「ほれ」と写真を見せてきた。それはベッドに寝ている親父が難しそうに眉をひきしめている姿で、一体なんのつもりでこんな写真を撮ったのかと訝った。だいたい、どうやって寝ている自分を撮ったのか。
しかし、それは親父ではなかった。
我輩が親父に見間違ったそれは、我輩だったのだ。
我輩はおかしさと驚きで、しばらくそのニッポニアオヤジと似た生き物を眺めていた。
屋久島で買った九千円の切り株は今親父のテーブルの上にある。そこに杉の幼木をおいて、「これを三千年育てて、縄文杉にするから、わちが死んだ後は任せた」と親父は言っている。我輩はヨークシャテリアに小便をかけられるか、引き抜かれるかが関の山だと思っている。