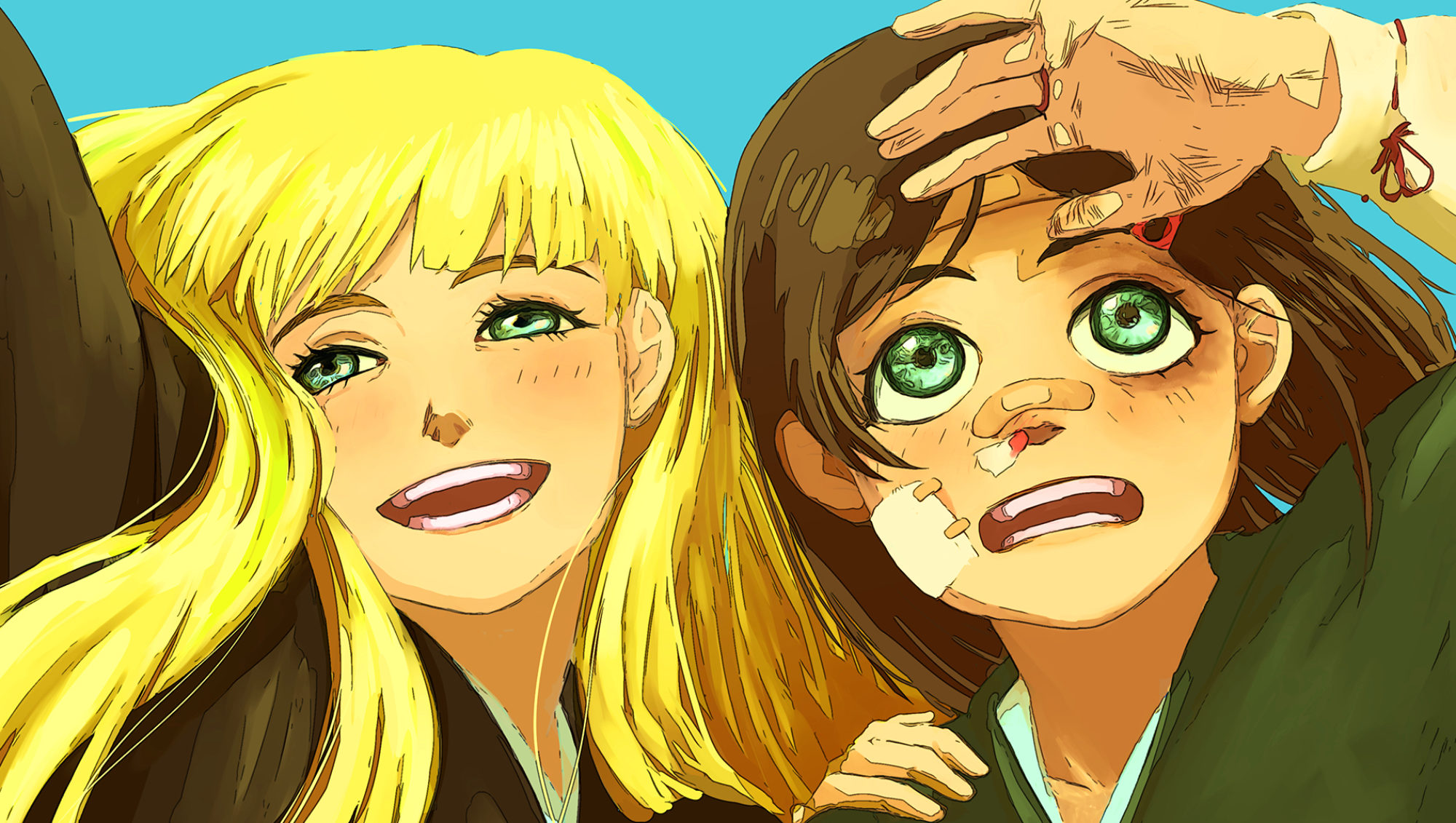語りたいことが幾つもある。
ラインナップとしては
1、 今後の成長に対する見込みと、根拠 星霜編の工夫と今後の伸び代
2、 国シリーズ完成に向けてのロードマップと段階的目標
3、 物語の必要性、今後予想される人間の混乱に対する貢献
と言うことを語りたい。
語りたい、と言うよりは言語化というメタ認知を行い、自分自身の行為を整理したいのである。
星霜編の創作期間、色々と考え、考えたことを試した。それが終わり、散らかった部屋を片付けたい。散らかりきって足の踏み場もない、というのが現状である。
何から手をつけていいのかわからないから、このブログ執筆も難航している。
我が輩の大掃除につき合うことが、皆様にとって何のメリットがあるのか。
整理していく過程で露見していくものを観察して頂き、今後の判断に役立てて頂きたい。
我が輩が連呼する「ハルカの国完成への自信」、「今後の成長」、ここへの信憑性、もっと言えば国シリーズにつき合うか否か。
Studio・Hommageとしての我が輩の活動を期待出来るのか、信頼出来るのか、その判断材料にしてもらいたい。
言うなれば、整理に託けて、皆様への「Studio・Hommageプレゼン」も兼ねている。
どうぞ、よろしくお願いします。
星霜編への工夫
今回は星霜編に施した工夫について語りたい。
前記したブログでも、FC活動報告でも「自信がある」「自信がある」と繰り返した。星霜編に自信があるし、ハルカの国に自信がある、と。
その根拠はなんだったのか。また未来の作品に対する自信の根拠は何なのか。
そこをお話したい。
物語の遅延
星霜編以前の作品は、早期のストーリーライン提示、というものを心掛けてきた。
目的の提示と、その方法が物語の序盤で示される。
みすずの国は「天狗の国へ行く」だし、キリンの国は「御姫様に会いに行く」だ。雪子の国でいえば「幽霊の正体を突き止めよう」、ハルカの国越冬編は「ハルカを倒す」、決別編は「猪を倒す」だった。
もちろん、これらは物語の本質ではない。本質はストーリーラインに沿って物語を歩む内に見えてくる人間模様であったり、市井の暮らしであったり、あらゆる風景にこそある。
ストーリーラインの役目は、目的と方法を示すことで、物語のレギュレーションを決定し、これからの予想を読者の中に育てることにある。
これから起こることを限定し、読者に「きっとこういうことが起こるだろうな」「こんな面白いことが起こりそうだぞ」という予感を抱いてもらうことを目的としている。
読者の中にわくわくする気持ちを育てるのである。
我が輩は露骨にこの方法を使い、ある程度物語の型が整ったところでメタナレーターを流す。登場人物の口から「○○するぞ!」とこれからの予定に対しナレーションさせるのだ。この宣言を切っ掛けに物語を発展させ、エンタメ要素の強いシーンを展開していく。
物語とは無秩序状態にある世界に対し目的を設定することで有意な行動を限定し、その価値観(レギュレーション)によって目の前に生じる物事を判断していくことだ。
目の前で起こっていることがバスケなのかサッカーなのか判別出来なければ、ボールを蹴った相手が正しいのか、ボールを持った相手が正しいのか、判別出来ない。
価値の判断が行われなければ、行動結果がスタックされず、前進感が生まれない。
ルールのわからないゲームの進行は理解出来ないし、選手の喜怒哀楽も共感出来ないのと同じ様に、物語もストーリーラインというルールがなければ前進を感じられないし、人物への感情移入も起こらない。
スポーツがルールによって進行する様に、物語はストーリーラインによって物語られるのである。
よく言われる「物語がなかなか始まらない」「序盤がダレる」というのは、ストーリーラインが示されず、起こっていることの価値判断が出来ない状態だ。
これを避けるためにも、早期のストーリーライン提示を行い、「この物語ではこういう行動に価値があって、その価値基準で物語を追っていきますよ」という約束を読者と結ぶ必要がある。
余談になるが、上記した「早期のストーリーライン提示」を突き詰めたのが「なろう系」と言われる作品群だ。
「なろうのランキングがヤバイ」とTwitterに流れてきたので見にいくと、全て同じ作者が書いたのかと思うほ並ぶタイトルが似通っている。
「○○で働いていたら過小評価を受けクビになったが、△△に拾われ能力を再評価されて厚遇される。一方、○○では自分が居なくなったことでシステムが回らず大混乱、いまさら戻ってこいと言われても~」
みたいな〝タイトル〟が並ぶ。あらすじではなくタイトルで、このバリエーションがずらりと並んでいる。
もはや様式美と思えるほどの陳列っぷりで、我が輩は「AIが最適解を求めた結果じゃなかろうか」と疑ったほど。
PDCAサイクルを高速で回せるなろうだからこそ、こういう結果に行く着くのだろう。
我が輩はそこに一人一人の作家と言うよりは、生態系、進化過程を見るようで、ゲームのシュミュレーション結果を見る思いがした。
かつてライトノベル批評を試み、ライトノベルはなろう系の「早さ」に負けると我が輩は予想した。なろうが台頭することで、既存のライトノベルはライトではなくなり、相対的に「遅い」エンタメになる。結果、「早さ」で競っていた既存のライトノベルは武器を失い、なろうにシェアを奪われると予想していた。
予想していたと言えば先見の明があるようだが、事実は当時から「なろう系」が台頭してきており、既存のライトノベルが「負け始めて」いた。つまり予想ではなく観察結果なのだが、その傾向が極まるだろうと予想していた。
なろうはどんどん早くなる。高速化していくと。
ここで言及している「早さ」こそが、ストーリーラインの提示の早さになる。
ストーリーラインが提示された段階で物語独特のエンタメが開始するのであれば、この開始ポイントが早ければ早いほど読者の待ち時間は減らせる。
つまりストーリーラインの提示が早いほど、即効性のある物語となり、それを「早い物語」と形容しているのである。
なろうはこの「早さ」を極める電撃作戦、孫子も説く戦略の基「巧遅拙速」によって、ライトノベルという相手を完封するだろうと、当時から顕在していた傾向が極まることを我が輩は予想してはいた。
しかしここまで極まるとは予想出来なんだ。
なにせ他の物語作品が、少なくとも冒頭の数十ページ、多ければ全体の三分の一を使って提示するストーリーラインを、物語が始まる前、タイトルの段階でババーン!と示してしまっているのだ。
この圧倒的な早さには、生半可な質では太刀打ちできない。目的を達成する機動力が、既存の物語作品とは違う。
我が輩はなろうという環境によって極まった〝速度〟に、戦く思いがした。
なろう、恐るべし。
なろうは現状、最速の物語様式を保持している。
話を戻す。
余談に逸れてまで伝えたかったのは、ストーリーライン提示の早さというものがいかに大切か、それがどれだけ読者を惹きつけるのに重要かということ。
物語の速度が重要だと、我が輩自身も考えているということを伝えたかった。
その上で、星霜編は「物語の速度」を落とすために工夫したことを伝えたい。
過去作品では「物語を早く」するために尽くしていた努力を、星霜編では「物語を遅く」するために尽くした。
なろうではタイトル時点で完了しているストーリーラインの提示を、可能な限り遅く、ギリギリまでねばった。
物語を意図的に遅く、ストーリーラインによって提供される面白さを排除するために工夫をした。
前作までの価値観で言えば「物語を退屈にする」ために努力をした。
この方向転換に、我が輩がアホほど繰り返してきた「星霜編の試み」がある。
ここを紹介したい。
「あえて退屈」に
星霜編、シナリオ段階ではオブザーバーから「序盤が退屈」「物語の始まりが遅すぎる」「物語の半分近く何の物語なのかわからない」という指摘が入った。
要するにストーリーラインを提示するまでの時間が長すぎる、物語が「遅すぎる」と指摘されたのである。
これに対し、我が輩は「あえてだから」と弁解し続けた。
序盤が退屈なのは狙ってやっていることで、物語に進行感がないのは意図的な表現なのだと。
ユキカゼの四十年間の停滞を表現するには、物語が淀んでいないといけない。何をしていいのか、何が出来るのかわからないという時代の中での混乱を描くために、物語は緩慢でノロノロしていなければならない。
そのために、ストーリーラインを抜き、物語の開始を遅らせて、退屈にしているのだと伝えた。
これにオブザーバーからは難色を示された。
「いや、意図とか表現とか置いといて、面白くないやん」
「お前が散々嫌ってきた遅い物語になっとるぞ、これ」
指摘された通り、我が輩は遅い物語を嫌ってきた。
だからこそ、自分の作品は「出来るだけ早く物語を始めよう」と心掛けたもの。そのために工夫をこらしたし、技術の向上もその方向へ磨きをかけた。
我が輩にとって遅い物語は禁忌であった。
そこを覆し、その上で面白くないのだから、オブザーバーが「止めといた方が良くないか?」と止めるのも無理ない。
しかし、今回は「ユキカゼの停滞」を描くために物語を遅くする必要があり、ここを覆しては星霜編の意味を確立出来ない。
だから物語は遅いことを前提とし、この遅い物語をいかに楽しませるかが課題となる。
オブザーバーが促す遅さの改善ではなく、遅くて退屈なまま面白いと感じてもらうにはどうすればいいか。試みる方向性はこっちだと我が輩は認識していた。
この課題に対し、ストーリーラインではない別のライン、物語らないラインを採用することで解決出来るのではないかと我が輩は考えた。
物語の遅さを克服する方アイディアがあったので、オブザーバーの制止を振り切り、試みてみたのである。
それが今までとは違う方向性、我が輩にとっては挑戦だった。
人間の生理的カデンツ
楽典用語にカデンツというものがある。和音の進行において、流れが自然となる進行を指す。
気持ちの良い、必然的な音の流れ、とも言い直せるだろう。
この必然性の気持ちよさ――カデンツは、音楽だけに限らず人間生理にも存在すると思う。
例えば、食べる、という行為。
肉汁したたるステーキをフォークで刺し、あーん、と開けた口に運ぶ――。
シーンが切り替わって、人物が満足した様子もなく、かといって空腹とも無縁な顔で歩いている。
例えば、殴る、という行為。
男が噛みしめた歯を剥き出し、固めた拳を、ぐぐぐっ、と振りかぶり相手に向かう――。
シーンが切り替わって、人物が頬を腫らすこともなく優雅な様子でコーヒーを飲んでいる。
例えば、凍える、という状態。
さむ!、さむ!、と肩を丸くし、腕をこする人物が、雪の降る道を歩く――。
シーンが切り替わり、人物が熱くも寒くもないような顔で会話している。
このような演出が続いたら、皆様はどう感じるだろうか。
我が輩は「気持ち悪い」と感じる。
ステーキを口元まで運んだなら、それにかぶりつき、「んー!」と旨味に悶絶するところまでが見たい。
振りかぶった拳は相手の顔面をとらえ、バキイ!と衝撃音が鳴って欲しい。
凍えていた人物には、温かい湯につかって「だっはぁ……!」と深々溜息をついて欲しい。
人間の欲求、行動には期待される解決先というものが存在し、それが叶えられるか否かは別として、必ず期待されたことへの答えを我々は望む。
ある欲求や、ある行動を描いた時、それが向かいたがる解決先が有り、そこへ向かうエネルギーが生じる。
この必然性に向かうエネルギーの流れを、人間の生理的カデンツと見なせるのではないかと我が輩は考えた。
この欲求の発生と解決の間には、音楽のカデンツと同じ様に進行感が生まれるはず。
この進行を利用すれば、生理的に気持ちの良い物語進行が描け、ストーリーラインの欠如をある程度補えるのではないか。
そう考えたのである。
炭坑→東京のカデンツ進行
冒頭の炭坑では、汚い、暑い、狭い、臭い、不味い、などおよそ人間が解決を望みたがる不快感を散りばめた。
これを未熟なクリに「嫌だ!」「東京に帰りたい!」と喚かせることで、東京に帰ればこの不快は解決するのだという方向性を示した。
東京に帰ると、汚いは綺麗に、暑いは涼しいに、狭いは広く、臭いは良香に、不味いは旨いへと転じる。そこをいちいちクリが「美味しい!」「綺麗!」と解決の快感を叫ぶ。
炭坑では赤黒く醜く描かれていた世界も、炭坑を発つと同時に清涼感のある青や緑に転じ、その清涼感からさらに転じる形で温もりのある橙色に転じていき、色彩としても生理的心地よさに向けて解決感を出している。
冒頭に示された不快が解決に転じるまでの流れで、生理的に気持ちの良い進行――カデンツを作った。そのカデンツによって確保された時間の内で、人物の関係性を示したり、舞台設定を提示したりと、情報を捌く。
このように生理的カデンツを利用することで、本来は進行感が生まれない情報処理にも前進を感じてもらえ、退屈の回避が出来るのではないか。
そう考えたのである。
人間の生理的カデンツによる進行感。
これが我が輩の採用した第一の物語らないラインである。
バッソコンティヌオ(通奏低音)の遠近
また楽典用語になるが、バッソコンティヌオ、繰り返される低音という意味で、通奏低音というものがある。
楽曲を通してバスに流れる低音で、最低音を保留することで、ソプラノメロディがどう変化しても曲の性格を保つ力がある。
この最低音の保留という方法で、物語の不連続感、散発感を回避しようと試みた。
ストーリーラインが存在しないために、シーンが散発的になる。シーン同士の関係性が弱く、発展性がない。
これが物語の流れを阻害し、「つまらない」という忌避感に繋がる。
ここに物語の本質的な恐怖をバッソコンティヌオとして定期的に登場させる。かつ、その音が次第に大きくなり近づいてくる演出をとる。
この方法により、散発的で関係性の弱かったシーンが、「恐怖が近づいてくる」という軸において連続性を持ち、その並びに発展性が生まれる。
以前、流行った「100日後に死ぬワニ」はこの手法で、まったく無秩序に思えるに日常の散発を一本にまとめあげている優れた作品だった。「100日後に死ぬ」という低音が、その上で起こる日常を味わい深いものにし、一日また一日と過ぎていく日々に意味を持たせていた。
所謂「時限爆弾」によって物語に緊迫感を保つ方法だが、明確な時限爆弾をセットするのではなく「なんか不穏な感じ」「微弱な不安」を感じさせることで、物語にストーリーラインを生じさせないまま、「不穏さ」によって進行感を持たせようと試みた。
「不穏」な象徴として鈍い赤色を使い、それを定期的に登場させ、物語に緊張感を持たせようとしたのだ。
ある時はユキカゼの夢の中に燃える獣として現れ、ある時は夕暮れとして、ある時は火事の炎として。
クリティカルなことが起こらない前半の東京において、不協和音のように醜い赤色を登場させ、平凡な日常を引き締めようとした。
色だけでなく、オトラが語る「ほどけ」や、弥彦が忠告した「来年からの不景気」も、ユキカゼに不穏な影を落としていたと思う。
それらを「物語の本質的な恐怖」の象徴として扱い、それらの接近感によって、ストーリーラインのない物語に進行感を与えた。
これが第二の物語らぬラインである。
記号の文脈
上の二つと比べると進行感を生む力には乏しかったと思うが、シーン同士の関係性を生むのに役立ったものとして、記号の繰り返しと、その変移の調整というものがある。
例えば、おんぶ、という記号。
他者を背負う、という記号は「ハルカの国」を通して象徴的に繰り返される記号である。
この、おんぶ、が繰り返される中で、その中身を変移させていき、おんぶ内で起こることに文脈を作った。おんぶ、という記号に発展性を持たせたのである。
初めはユキカゼがクリを負ぶい、次はオトラがユキカゼを負ぶい、最後はクリがオトラを負ぶう。
行動のおんぶだけでなく、意味の上でのおんぶとして、クリはオトラに何度も負ぶわれた。
このような「負ぶい返し」によって三人の関係性の移り変わり、時の経過を演出出来ていたと思う。
オトラがユキカゼに背負われ、尾道から東京へ帰る。これは長女の交代(家長の交代)を意味しており、必然、オトラが皆を守っていた前半東京とは暮らしが違ってくる。その演出にもなっていた。
小道具としての記号も、その扱い方を変えて文脈をつくり、時の経過を与えた。
オトラの小道具で、時計だけが妹達に受け継がれなかったのは、時計の意味が終わったからだ。
遅れ続ける時計を必死に合わせ人間たちに着いて行こうとしたオトラは、尾道で力尽きた。その象徴として、懐中時計の再登場はなかった。
全ての記号とその繰り返しを意図的にコントロール出来たとは思えないが、幾つかの記号、重要だと思えた記号内の変遷は、過去作に比べ格段に注意深く扱った。その効果は多少なりともストーリーラインなき物語の牽引に貢献してくれていたと思う。
記号が語る変遷もまた、物語らぬラインの一つだろう。
編を超えた対立構造
これは星霜編内のラインではなく、越冬編、決別編と対を成すという意味でのラインなのだが、困難や恐怖の質を、明治と大正では変えた。
明治編では、酷寒の冬や、巨大な猪として、ユキカゼの肉体、リアルに訴えてくる困難が目前にあった。文字通り、ユキカゼは困難に直面し、一瞬、一瞬、そこから逃れなければ身体感覚として苦痛を味わい、肉体の損傷としての死を余儀なくされた。
リアルな死が隣になり、だからこそ鼓動の一つ、呼吸の一つとが生として激しく燃えていた。
しかし大正編の困難は、ユキカゼにリアルとしては迫らない。
ユキカゼの前に吹雪きはないし、口を開けて迫ってくる化け物も存在しない。
逃れなければ死んでしまう実体を持った恐怖は何処にもいなかった。
それでも「何か」が迫り、ユキカゼの身体ではなく、ユキカゼの生態系、ユキカゼを支えているもの、エコシステムを削っていく。
大正編において、ユキカゼは剣だけがあればいい孤独でもなく、浮き草として関係性を持たぬ独立存在でもなくなっていた。
第一次世界大戦景気というグローバル経済に巻き込まれ、物価や株価に振り回されながら、住む場所や、仲間たち、食い扶持である仕事を得ている。
ユキカゼという存在は、痛覚をもった身体以上に拡大し、痛みを感じられないなかで傷つき、何かを失っていく。
欧州の景気動向などユキカゼは知るよしもなく、知ったところで如何ともし難いのだが、それらは確実にユキカゼが依存するエコシステムを揺るがした。船景気の減退は、ユキカゼから仕事と居場所を奪い、三人の解散を強制させたのだから。
明治編と違い、大正編は痛みを伴わない恐怖がユキカゼを襲う。
痛みのないまま、何かが失われていく。
この身体性の喪失が、ユキカゼに恐怖を「痛み」ではなく「混乱」としてもたらす。
ユキカゼは星霜編において命の危険に一度も会うことはないが、星霜編の戦いは越冬編、決別編以上に厳しいものだったと思う。
この困難、恐怖の移り変わり、リアルからフィクションへの変移が、明治と大正の大きなコントラストとなっており、時代の変化を演出した。
もっとも、これは演出のためだけではなく、「ハルカの国」を通して見せたい本質の一つでもある。
生きることの本質から身体性を失うと、我々は混乱する。痛みのない喪失に人間は耐えられない。
星霜編でユキカゼが直面した恐怖こそ、現代に生きる我々には近しいものだったのではなかろうか。
その他
ストーリーラインの補助、物語らぬラインという意味では、上記した工夫が主になる。後は細々としたものがこれらに準じる。
ラインに限らず工夫という意味では語ることに尽きないが、これ以上ひけらかしても同程度の内容を並べていく作業に過ぎない。読んでいる皆様も退屈されるだろうから、止しておく。
上記程度の工夫をこらしたのだな、あの程度の工夫に頭が回るようになったのだな、と思っていたければ目的は成功している。
偉そうに語っているが、恐らく他の作者もこれぐらいの工夫はしている。と言うのも、我が輩は星霜編創作過程で幾つも工夫を思いついたが、その多くは他作品からの着想、流用による。
漫画、アニメ、映画、小説、ゲーム、音楽。将棋やボクシングからもアイディアを得ることがあったが、要するに、何かを本気で極めんとしている所には技術が存在し、それは他ジャンルへの流用を耐えうるだけの普遍性を持ち合わせたものが多い、ということ。
我が輩が思っていた以上に、世の中の優れた物には工夫がされていたということを、この度思い知らされた。
今後の伸び代
我が輩が今後の成長を疑わないのは、バリエーションが増えたことに根拠を持つ。
今までは「物語を早く」するために腕を磨いていたが、今回は「物語を遅く」するために工夫を凝らした。
つまり、今後は物語の速度を意図的にコントロールし、その調整によって表現に幅を持たせることが出来ると考えるのだ。
現状、なろうで極まる傾向に象徴される様に、エンタメにはとかく早さが求められる。
この最速の争いに参戦するよりは、速球と遅い球を投げ分け、落差による速度で太刀打ちしていきたいと考えている。
遅いけど、面白い。
その上で、いざストーリーラインが提示されるとテンポが上がり、面白さの質が変わる。
もともと、ノベルゲームは遅い物語を得意とする。
日常シーンの描写でじっくり関係性をつくり、中盤から終盤にかけてストーリーラインを提示し、大団円に向かう。
我が輩はこれを退屈として避けてきたが、実は遅い球を投げる技術がなかっただけではないかと反省している。
コマは回転速度が上がると安定する。逆に、回転速度が下がると安定させるのは難しい。
物語もこれではなかろうか。
物語は早くするよりも、遅くする方が難しい。このために遅く語る技術が廃れ、早さだけが向上の方向性として残ったのではないか。
この早さにだけ価値を見出すとき、ノベルゲームという媒体は、なろうであったり、Youtubeであったり、早くコンビニエントな他媒体にどうしても遅れをとってしまう。太刀打ちできる武器が少ない。
遅く語る技術を習得し、それを向上させ、早さとコンビニエントを追求するエンタメとは違う面白さを提供する方向は、戦略として有りだと我が輩は考える。
この速度を目的に合わせ調整するという技術の向上をもって、我が輩は今後の物語のクオリティアップを予感している。
それは現在傾向を強めている「早いエンタメ」とは違った、独特なものになるのではないかとも思っている。
この早さの幅を持たせる技術の他に、時間感覚を調整する技術にも試みた。
ある瞬間にあるシーンを思い出してもらうにはどうすればいいか。回想シーンを挟むことなく、ふとあの頃のことを思い出してもらう方法はないか。長い時間が流れた体感を与えるにはどうすればいいか。
そもそも、人間はどうやって時間を体感しているのか。時間とはそもそも何なのか。人間の記憶と、その想起方法はどうなっているのか。
一つのシーンに対し、多くのシーンが重なって見える、物語全体が想起されるような交響の技術はどうやって確立すればいいか。
ここらにも頭を悩ませたし、今でも悩ませている。
これは最終的に目指す「100年の物語」を読者に体験してもらうため、是が非でも習得しなければならない技術だ。
どうすれば皆様に「100年」を感じてもらえるか。我が輩はどんな「100年」という体験を皆様に提供出来るか。
ここを突き詰めている。
今回はここに関して子細は語らない。まだ言語化出来る段階にないと思うし、この技術の成功の如何は、ハルカの国完成をもって皆様に判断してもらうしかない。
であるから、今、「こんな技術を確立した」とひけらかしても、その有用性を証明出来ない。
ハルカの国完成の暁に、成功しましたでしょうかと、改めて尋ねたい。
星霜編の困難
最後、星霜編創作の困窮っぷりを告白して今回は締めたい。
星霜編、1年以上の制作期間を要した。
まーじで、地獄だった。何度モチベーションが尽きて、創作に向かえなくなったことか。
去年の二月、まだ平成で、令和の元号も発表されていなかった頃。星霜編の第一項が仕上がる。
これが総没。
第二項は決別編発表後の十一月に書き上げたが、大正東京が描けずに自主的に没らせた。
そこから東京を描くために冒頭を九州筑豊炭坑へ移し、コントラストによって描く方法をとるが、駄目。
この時、もう起きるのも嫌で一日二〇時間くらい睡眠をしたことがあった。
寝過ぎて腰も痛いしで眠れなくなり、起きて誤魔化し程度に作業して、かすかな眠気を覚えたらそこに逃げ込んで寝る。
寝逃げを極め、現実を拒否していた日が二三日あったのだ。
それでも我が輩は根が呑気なので、「気分転換に旅行に行こう」と切り替え、「旅している途中に何か思いつくだろ」と根拠もないままモチベゼロの身体を旅路に向かわせた。
昨年末、コロナの名前がチラホラと聞こえてきた中で、尾道~東京とロケハンをかねた旅にでる。
新幹線にのって作業場である山口から離れる時、涙が止まらなかったので相当ストレスが溜まっていたのだなと自分でびっくりしたもの。
泣くほど頑張ったんだなぁ俺、と酔っていた部分も否めないが、尾道に着くまで涙腺緩みっぱなしだった。
ロケハンの旅については以前ブログに記したので重複しないが、旅行中に読んだ吉田秀和の「決定版 マーラー」が切っ掛けとなって星霜編の構成を考え直し、帰宅後、「今度こそ頼む……!」と懇願する思いで書き直したのが今回のシナリオ。
書き直した結果、今までの二倍の文量となった。
オブザーバーからは「やりたいことはわかるけど、序盤が退屈」と上記した指摘を受けながら、上記した通りの弁明を並べ、スクリプト作業に入ったのが今年の四月。
ここから八月末までスクリプト作業が続き、九月、十月、スチル絵を描いて、なんとか先日公開にこぎ着けた。
最後、体調も悪く、本当に、ほとほと疲れ果てた。
成長を感じられる、実りの多い創作期間であったのは間違いないし、今までとは違う次元に到達出来た気はしているが、ふり返ってみると、疲労感が凄まじい。
遊んで頂いた方々から感想を受け取り、上々の評価に喜びを噛みしめながらも、「ち、ちかれた……」と安堵による腰砕けが今の我が輩を最も良く表している。
星霜編。
本当に疲れた。
疲れすぎて、星霜編をテストプレイをすると色々なことを思い出し、見るだに疲労するほど疲れた。
創作期間中、辛い、苦しい、疲れたとネガティブな発言をすれば皆様を不安にさせるだろうと思い、完成した暁には叫びたいと思っていたので、今ここに至り、感慨の極みにある。
もう、超、疲れた。
マジで苦しかった。
モチベーションが底をついた時は、本当に辛かった。
それでも「やめたい」とはは思わなかったから、本当に創作は好きなのだろう。
やる気を完全に失っても「どうしたらいいかなぁ」と考え、根拠はないにしても「旅行に行こう」と何かを変える努力をしたことは、ふり返っている今となっては褒めてやりたい。
毎日、毎日、全力を尽くしたとは言い難い創作期間だったが、それでも六割くらいの力を維持し、止まることなく歩き続けた日々に今は感謝している。
今回の創作を通して、何より痛感したことは、自分がやったことは、ちゃんと自覚的に認めてやらないと誰も褒めてくれないということ。
褒めてもらえなければ、努力は続けられないということ。
自分が今何を試みているのかを自覚し、その成果を見張り、適当な評価を授けていく重要性をとことん痛感した。
自分くらい酷使すればいい、ぶん殴って作業をさせればいいと思っていたが、どうもそれではいけないらしい。
自分の行動に意味を感じ、成長、前進を実感出来なければ、人間の身体は気力を失う。
これは頭でどう頑張っても補えるものではなく、人間は身体から活動エネルギーを得ているのだと痛感させられた。
自分に自分がやっていることをちゃんと説明する。
重要性を説き、努力する必要を身体にわかってもらう。
腹の底から行動というものを理解する。
行動の結果を、しっかりと自覚してやる。
その大切さと難しさに今回は直面し、その技術がないために打ちのめされた日々でもあった。
だから今、我が輩は身体の声を聞き、それを労っている。
ちょう、つかりた……。
うん。
でもそろそろ回復したくない?
やりたいこと、幾つか出て来てるのだけど。
現状、こんな感じである。
次回は国シリーズ完成に向けたロードマップについて語りたい。