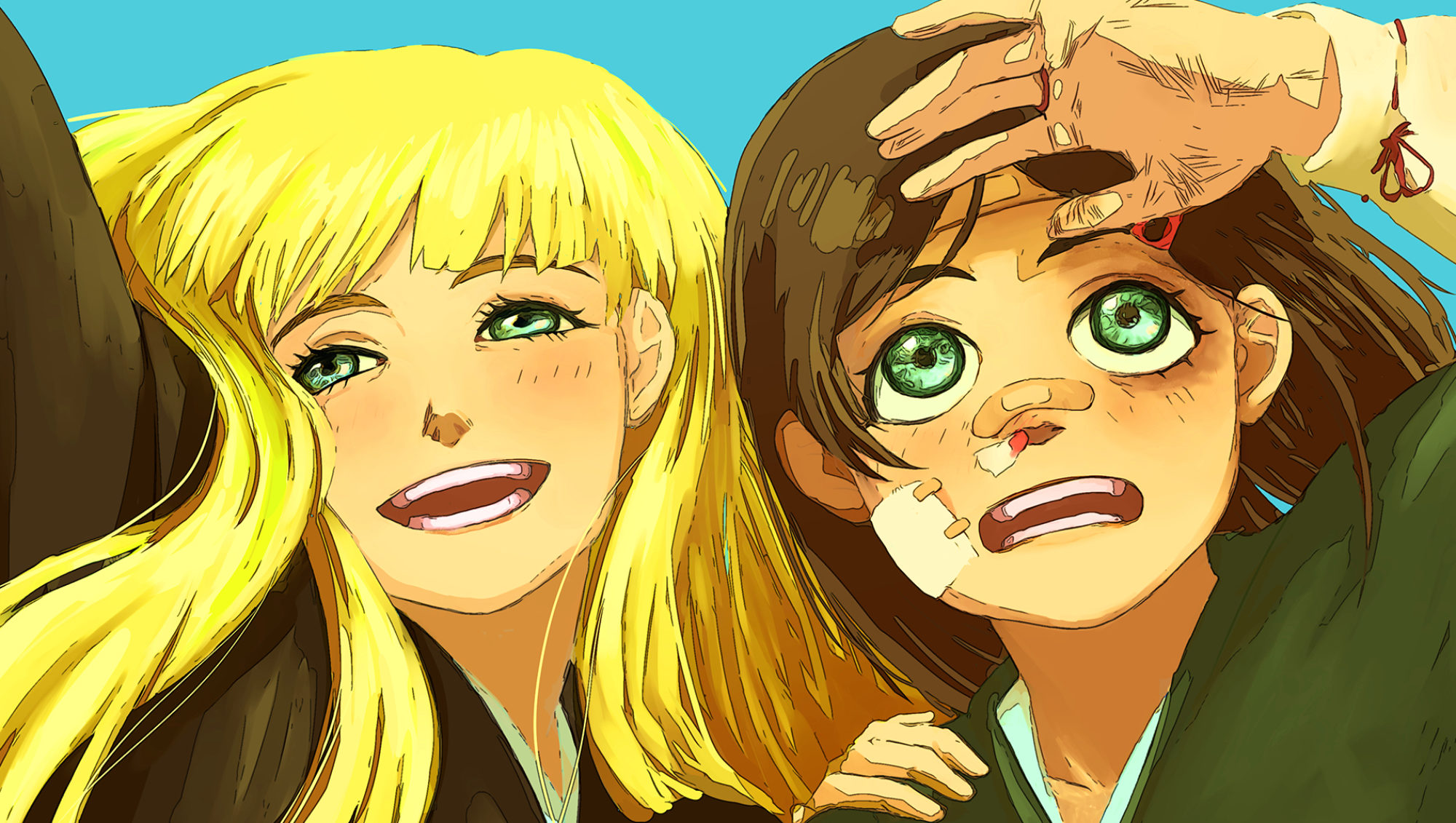季節は「まれびと」と言う。またを「まろうど」。
現代語に訳すれば客人。
山、あるいは海、あるいは空の彼方より訪ね来て、人々の暮らしを変えていく。
いにしえ。
季節の節々に催された祭は、「まれびと」という季節神を迎えるためのもてなしであった。
人々は季節を待ち望み、また恐れた。
そのために「まろうど」には敏感であり、彼らの気配を感じれば敬った。
ハルカの国のハルカもまた、まれびと。
春の訪れとともに里におり、冬を乗り越えた人々を労う。
ハルカのような神々が、かつての日本には全国津々浦々に存在し、彼らを招く座が人々の心にはあった。
訪れるのは季節神ばかりにあらず。
招かれざる客も、時折訪れる。
忌日、というものが幾日かあり、例えば事八日(ことようか)と呼ばれる二月と十二月の忌日には一つ目小僧がやってくるという。
その日は子供たちは早くから家に帰り、夜は戸締りをして外に出ない。
またザルを吊るして、一つ目小僧を避ける。目の多いザルを、一つ目小僧は恐れて近づかなかったと言う。
まれびとにしろ、一つ目小僧にしろ。
かつては「よくわからないもの」「目には見えないもの」の気配がそこら中に漂い、それらは時の巡りとともに我々に近づいたり、離れたりした。
その恐ろしさや、畏怖が、人々の想像力をどれほど豊かにしたかと近頃思う。
外は鬼が歩くと言われ、ぴたりと閉じられた家の内で静かに寝つく夜。子供には恐ろしい一夜であっただろうが、恐ろしい故に豊かであっただろう。
十一月一日より「クリスマスケーキご予約受付中」の幟がたったコンビニ駐車場。
なんだか季節が商売っ気ばかり匂うようになって、味気ねぇなぁと。
秋深まる頃、しみじみ思った次第であります。
肌寒くなってまいりましたが、風邪菌など身体に迎えていませんでしょうか。
ハルカの国 進捗
大正、星霜編。
未だにシナリオを書いております。
ネームも新たに250枚描き加えて、足した分、助長と思えるところをせっせと抜く作業。
シーンや出来事をがぱっと抜ければ楽だけれども。もうそういう時期は過ぎて、あとは台詞一つ抜いたり、地の文短く書き換えたりで、研磨によって総量を減らしていく。
時折「増やす作業ならわかるけど、減らす作業に時間かける意味は?」と問われるが、増やすより減らす方が重要なのがシナリオだと我が輩は考えている。
逆説的な話だが、シナリオとは「何を書かないか」を意識し、「いかに書かないか」へ挑むことが本質だと思っている。
「書かなかったもの」とは、「書いたもので縁取ったもの」。つまり空間。これこそ物語の本質と考えるために、書いてしまったものを削る。空間を大きく、深く、豊かにするために削るのである。
とまぁ、格好の良いことを言っている一方で。
文字、読むという行為のリスクに怯えている、という側面もある。
我が輩、字を読むのが嫌いだ。
文字から情報を得て、それを頭の中で再構築するのに、エネルギーを使う。
集中力も要求されるし、「読む」という情報取得方法は時間もかかる。
様々な労力を要求された後、結局、「得られるものが労力を下回った」と思える内容だった時の徒労感が嫌いなのだ。
手前がこういう了見だから、他人に文字を読ませる「申し訳なさ」は日頃から意識している。
文字を読んでもらったからには、それなりの何かを提供しなければならない。
感情、ストーリーラインの展開、謎への探求、人物関係の変化、展開への期待――何かなければ、脳内のドーパミンが枯渇して読書なんてまどろっこしいことやってらんない。
実際、ドーパミンの減少は集中力の低下を招き、情報処理能力を下げる。処理能力が落ちれば、読んでも読んでも内容が頭に入ってこない状態に陥る。所謂、「文字の上を目が滑る」という状態。
これを避けるために、どれだけの事が出来るか。
見直しながら、どれだけの事が出来ているだろうかと自問する。
それが我が輩にとってシナリオを直すという行為であり、価値を減らすことなく文量を減らすという形で行動に移される。
であるからこそ「減らす」「消す」という行為には、時間を取られてしまうのだ。
実際、添削前の我が輩の原稿は読めたものじゃない。
いらんことは書いてあるし、書きすぎて品がないし、情報の重複は多いし、リズムは悪いし。
皆様の元に届くのは二回も三回も書き直した後のもの。
生まれたては醜いものなのです、とても。
と言うか、物語を理解していない。
削っていく中で、「これは削れないな」と思える本質を見つけていく。粘土ブロックを削いで削いでいくなかで、作品の形を探っていく。そういう工程でさ。
明治決別編。
天狗征伐のくだり。本当はどういう風に攻め入って、どういう展開になって、現場はどうだったとか、細々と書いていたんです。地形図とか、布陣とかも用意して。人間側の兵器も調べて、スケッチしてた。
でも、駄目でした。
「あー文字の上を目がすべるう!」となって、全部消しました。
手前が書いたものでも「腐った文章書きやがって」とイライラすること、よくあります。
「最低でも10%は無駄な部分がある。10%は削る」
スティーブン・キングが教本の中で言っていたこと、今でも杓子定規に守っておりまさ。
キャッチコピー
ハルカの国。
各章にキャッチコピーをつけている。幾つもつけている。
何故、同じ作品に違うコピーをつけるのか。
一つには宣伝用というのもあるが、もう一つ大きな役割として「視点の座標を定める」というものがある。
「こういう視点を忘れないでね」という自分への戒めとして幾つか考えるのだ。
例えば「強さは、私のものだった」というフレーズはユキカゼ視点のものだし、「はじまりは、明治」はもっと高い視点のもの。時代というものへの意識配分を忘れるな、という戒めである。
決別編は「私は私を取り戻す」とユキカゼ視点のストーリーラインを設定しつつ、「激動の時代、市井の人々」というコピーで「世界の中心なんか存在しないのだ」という戒めを自分に課したつもりである。政府や国家というものがいかに激動のなかにあっても、関係なく毎日を過ごしている人々がいる。彼等が片隅なのではない。誰もが片隅であり、当事者以外は「しょうもない」ことなのだと。
キャッチコピーは物語を練る前に思いつくこともあるし、書いている途中に思いつくこともある。思いついたものが機能不全に陥り、捨てることもよくある。
大正星霜編、「居場所を探していた」というコピーで最初はやっていた。しかし段々とピンとこなくなり、途中で捨てた。
元から合っていなかったわけじゃない。「居場所を探していた」というコピーでやっていたところ、次第に窮屈になって捨てたのだ。ヤドカリは成長に合わせて宿替えをする。物語も成長すれば元の揺り籠を捨てるものなのだ。
話は逸れるが、台詞にしろ、アイディアにしろ、キャラにしろ、シーンにしろ。温めていたものを大切にしない方がいい。温めていたものに合わせて、物語を歪めるのは悪手だと感じる。かなり浮く。浮いた上に、「言いたかったんだね、この台詞」「やりたかったんだね、こういうこと」と作者を見抜かれてけっこう恥ずかしい。読者の視点から見ても、作者が匂ってきて物語から覚める。
合わないな、調和しないな、と思えば大切にしてきたものでも諦める潔さは必要だろう。
大正星霜編。
今のところ、新たに思いついたコピーで満足しながらやっていけてる。窮屈さも感じない。
作中で思いついて、自分にとって星霜編はそういうことなのかな、と納得も出来たので気に入ってもいる。
「老いていく私へ」
元々は「老いて死んでいく貴方へ」と挑発的なメッセージを考えていた。が、外連味を強く感じたのでやめた。
今では「私」というのが気に入っている。
私はユキカゼであり、我が輩でもある。また、大正星霜編を遊んでもらった後は、皆様のことになるかもしれない。ならないかもしれない。
老いへの忌避
今でも時折、自分が三十歳をこした事に困惑することがある。寝起きなど、唐突に混乱するのだ。
「え? 俺三十過ぎてるの? もう二十代じゃないの?」
一体、二十代に何の未練があるのかしれないが、事実、我が輩は時折三十代であることを受け入れていない節がある。
結婚してないから? 恋人もいないから? 就職もせずぷらぷらやっているから?
色々自問するが、はっきりとはしない。
ただ、二十代ではなくなったことが、二年経った今でも何処かで受け入れ出来ていない。
同時に。
自分が四十、五十となっていくことをリアルに感じられる。
それに伴い、我が輩より年配の家族がいなくなっていくことも、頭と心、両方で理解し始めている。
ある日、目が覚めて。
ふと「ヨークシャテリア、死ぬな」と思う。今日明日じゃないけど、恐らく2、3年の内に寿命がくる。そう遠くないうちに祖母が、父親も、母親も。
明日、明後日の話じゃない。
けど、彼等はいなくなる。そういう事実を受け入れられる朝があるのだ。
そこで「俺もいなくなるんだな、その内」と妙に納得してしまう。
「こえ~」と思うのだけど、その恐怖があればこそ、自分が死ぬこと納得し始めたなとも思う。
朝飯食って散歩する内に忘れてしまうが、定期的に「死ぬな」と納得してしまう時が巡ってくる。こういうことは、二十代にはまったくなかった。
老いた自分を信じられない我が輩と、老いていく自分を納得してしまう我が輩と。二つの物が混在していて、気持ちが大きく揺らぐ時がある。やはり三十代はホルモンバランスが変わるんだな、としみじみ実感する。
「老いていく私へ」というコピーの「私」を自分だと思った時、不思議に心が安らいだ。
あの安らぎは何だっただろうと考えて、類似品を過去に見つける。
アパートの換気扇。
油にホコリがくっついて、焦げ茶色にネバついて、見るのも嫌だった時期がある。
洗い物する度に目に入って、「はぁ」と重いため息をついていた。でも洗うのがめんどくさくて、見なかったことにしておいた。
それをとうとう、洗った日。べっとりとした油をスポンジで拭い取っていったあの時感じた安らぎ。家のなかに見たくないものが無くなっていく安堵に似ていた。
それは部屋が綺麗になる嬉しさとは別物。とにかく、シンクの方角を見ても目を瞑らなくていい、誤魔化さなくていい、という事実が嬉しかったのだ。
あの「忌避」からの開放感に、とてもよく似ていた。
忌避していたものを、物語に招き入れる。汚くて嫌だったもの、認められなかったものを、少しずつ物語に招いてやる。そうやって物語が濁っていくことに、今は安堵感を覚える。
多感な青春時代。
物語はネバーランド、ユートピア、理想郷として我が輩を助けてくれた。
三十を過ぎて、我が輩はその王国を内側から壊している。
一体どういうつもりなのか。
忌避を忌避したままでいるのが、嫌なのだ。目をきつく瞑っていると、肩が凝る。疲れてしまう。
年をとって世界が綺麗であることより、披露を和らげることに力を注ぐようになったのかもしれない。
あるいは目をつぶって得られるネバーランドの「胡散臭さ」にほとほと嫌気が差したか。
老いていく私へ。
このキャッチコピーに、わくわくはしないだろう。綺麗なものが見えてきそうにもない。
最終的にはこのコピーも捨ててしまうかもしれない。
けれど今は、我が輩はこの視点をもって物語を見つめていたい。
見たいと思う物が、今は理想ではなく、忌避の先にある。
恐ろしい場所へ行ってみたい、恐ろしいものを見てみたいという願望が強く強くある。
もしかすると、これも「わくわくすることをして、綺麗なものを探して」いるのかもしれない。
濁りを招くことで、物語をたくましくしたい。迫力を持たせたい。
そういう雑種的な強さ、混沌としたものの強さを、今は美しいと思い始めたのかもしれない。